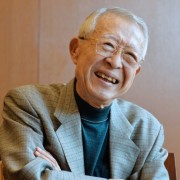書評
『ホモ・デジタリスの時代:AIと戦うための哲学』(白水社)
歴史のアイロニーに耐える信念
この本の表題は難しいが、原書の表題は明快である。原題は「時代は変わったというべき……」。副題は「懸念される変化の(うなされるような)編年史」である。明らかにこのほうが、内容を正確に表している。ちなみに驚くべきは著者の博覧強記であって、全巻に先学の時代批評の引用がちりばめられている。総二百ページの各ページに平均して二編以上、さながら「時代批判史で綴る五十年の現代史」というべき観を呈しているのである。
著者自身の現代の把握は、基本的に一種の下降史観に貫かれている。工業化とともに大量生産を興し、テイラー方式の流れ作業で頂点を築いた資本主義は、この五十年間で限界を見せ始めた。多彩な社会変革は試みられたものの、どれもがその内部に矛盾を露呈し、わかったのは資本主義は不幸だが、その代わりになるものはないということだった。
物語はまず一九六八年、パリの学生の反乱「五月革命」に始まる。おりから先進国には消費社会が訪れ、おとなたちは物欲に溺れて安逸と従順の日々を送っていた。これを退屈と感じ退廃と見た若者はパリを筆頭に、世界中で体制転覆の過激な運動を起こした。
当時、著者は十代半ば、多感な少年として体験した事件は今も記憶に新鮮なのだろう。評者の私も米国のヒッピー、日本の新左翼全学連の紛争を目撃して、あの数年間には独特の印象を抱いている。しかし、真相はけっして見た目に現れるものではなく、経済の長い下降はこの六〇年代に始まっていた。
生産性は向上したが、その結果として消費が均霑(きんてん)すると、需要は伸び悩んで企業の利潤は減少した。これはやがて雇用の削減を呼び起こし、社会はしだいに「さらば、プロレタリアート」の時代に移行した。たんに失業者が増えただけではなく、工場で労働者を繋いでいた階層的社会、それを原型とした社会秩序そのものが信頼を失っていった。
「五月革命」の若者が夢見た新しい社会、階層も権力もない開かれた人間関係が、このとき具体的な代案を出せなかったのは皮肉であった。この夢は遙かに迂回して二十一世紀前半、「デジタル社会」の到来によって歪んだかたちで実現した。夢破れた七〇年代の理想主義者は、せめて「共同体生活」に活路を求めて、無残に幻滅するしかなかった。
私産を放棄し、全収入を供出し、はては夫婦関係すらも共有しようという破天荒が、近代社会を経験した常識になじむはずがない。別の背景から生まれたイスラエルのキブツも含めて、結局「共同体主義」なる理想はこの一時代の歴史の挿絵として消え失せた。
「五月革命」の絶対自由主義への幻滅は、他方で政治的なテロの季節を開いた。十年後の七八年、イタリアのモーロ元首相が極左集団に誘拐、殺害され、八〇年には極右武装集団によるボローニャ駅爆破事件が起こった。今世紀まで続いた先進国でのテロの脅威も、想えばこの時期に端を発していたのだった。
不安と混迷の十年に終止符を打ったのは、レーガンとサッチャーの保守回帰だった。保守派が時流を簒奪(さんだつ)したのは、彼らの自助努力論と伝統的な美徳回復の標榜によってだった。労働者を含む大衆がこれを支持したのは、彼らがプロレタリアートではなく、職人や農民のような自立した存在に憧れていたからだった。もちろん実現したのはこの憧れではなく、格差拡大と個人負債の増大、やがてリーマン・ショックに繋がる世界的な経済危機である。
同じ時期に冷戦終結とソ連崩壊の大事件が起こったが、著者はこれを大衆の付和雷同現象、ポピュリズムの台頭の背景として指摘する。社会主義と自由主義、二つのイデオロギーが動員力を失ったとき、民衆は多様な小さな思想運動に蝟集(いしゅう)したのである。ル・ペンに代表される欧州の極右勢力は世紀末にかけて伸張し、世紀を越えると英国のEU離脱、トランプの扇動政治となって徒花(あだばな)を開いたのだった。
繰り返す歴史のアイロニーのなかで、しかし最大のものは現代の「革命」、電子通信機器の飛躍かもしれない。国家も階級も超えて個人を直接に結び、自由な空間を開いたという意味で、これは「五月革命」の夢の到来のようにも見える。ロボットと接続した電子機器は第三次産業を拡大し、人間を物質あいての労働から解放するともいわれる。
だが実際は、モノを構想し商品化する労働が優遇される半面、第三次産業の大半を占める「フェイス・トゥ・フェイス」の仕事は冷遇される。電子産業の内では雇用と利益は背反するから、労働者を激減させた「GAFA」と呼ばれる四大企業が市場を独占した。電子機器の利用者は逆に機械に服従し、中毒症状を呈して「私」の喪失に瀕している。
下降史観もここに極まったように見えるが、感動させられるのは、著者がそれでも投げやりにも捨てばちにもならず、電子産業の規制や未来世代の教育に期待するなど、アイロニーに耐える小さな努力を信じていることである。
ALL REVIEWSをフォローする