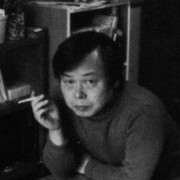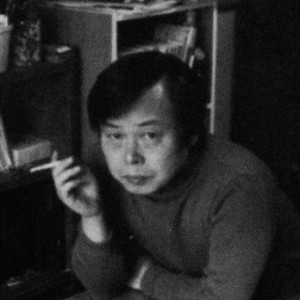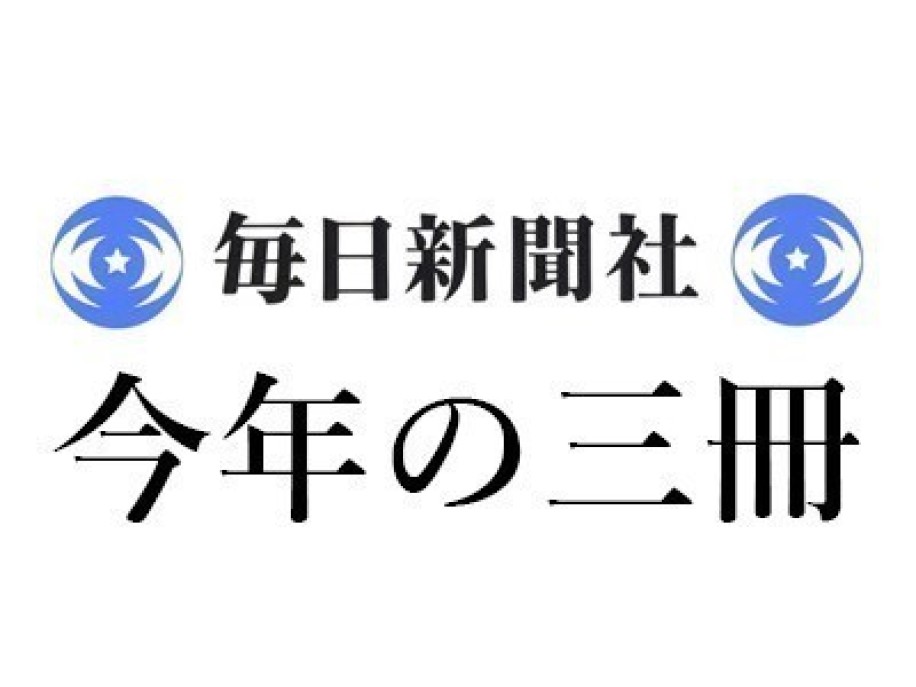書評
『一切合財みな煙』(河出書房新社)
優雅で小粋な生のエスプリ
漢詩はあったし長歌もあった。しかしなんといっても短歌・俳句のほかの近代詩は西欧文学受容以後のことだろう。翻訳詩が新風を吹きこんだ。そこで詩人はまず外国文学者、訳詩人であることが多かった。とりわけ大正時代、日夏耿之介(ひなつこうのすけ)、堀口大学、西條八十、と翻訳詩人たちが花と咲いた。オペラを通じてバタくさい歌詞が大衆化もした。げんにエッセイ集のタイトル『一切合財みな煙』は松井須磨子歌う『カルメン』(北原白秋作詩)の主題歌。自らも『カザノヴァ回想録』やレニエの翻訳者で詩人の窪田般彌が、大正期の、昭和にかけてはその残り香の、西欧詩の魅力を縦横に語る。しかも上述の何人かの大正詩人の謦咳(けいがい)に接した著者ならではの懐旧談で、肉声で大正詩話を語れる人はもうこの人以外にはいないだろう。昭和期からは、斎藤磯雄、吉田一穂、西脇順三郎、北園克衛といった、いずれも昭和詩人でありながら反昭和的な詩人たちの素顔を、現場でスケッチして貴重な肖像室を構成した。
小論ながら夭折(ようせつ)した三富朽葉(みとみくちは)のボードレールの小散文詩訳についての指摘、オペラに執心した荷風の逸話、漢詩の日本語訳に清新な息吹を吹きこんだ『車塵集(しゃじんしゅう)』の佐藤春夫。とりわけ出発点で一体だった日夏耿之介と堀口大学が、やがて反時代的な高踏詩人と、あくまでも同時代のダダ、シュルレアリスムに開かれた『月下の一群』の「新精神(エスプリヌーヴォー)」の詩人に分裂していく過程を語った文章が重要だろう。欲をいえばこのあたり、もうひとくさり名調子を聞かせてほしい。
ほぼ同時にひさびさの詩集『老梅に寄せて』(書肆山田)が出た。こちらは楽屋裏にエッセイ集を置いての名人会のおもむき。『一切合財みな煙』と韻を踏んで、
この世に残るものは何もない/この何もないが残るだけ
と老年の哀歌をうたいながらも、かつては若く美しかった女たちの老梅(ろうばい)ぶりに周章狼狽(ろうばい)する諧謔(かいぎゃく)に遊び、優美なロココ詩と大正文学の煙と消えても匂いたつ残り香を、江戸俳諧風の小粋な洒脱で吟じつつ風刺のカラシもきかせた、近頃痛快な詩集なのがうれしい。
朝日新聞 2002年12月1日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする