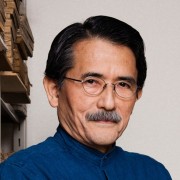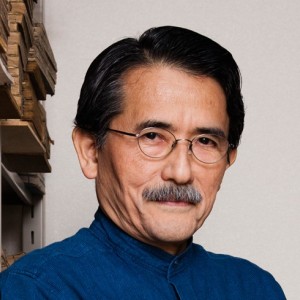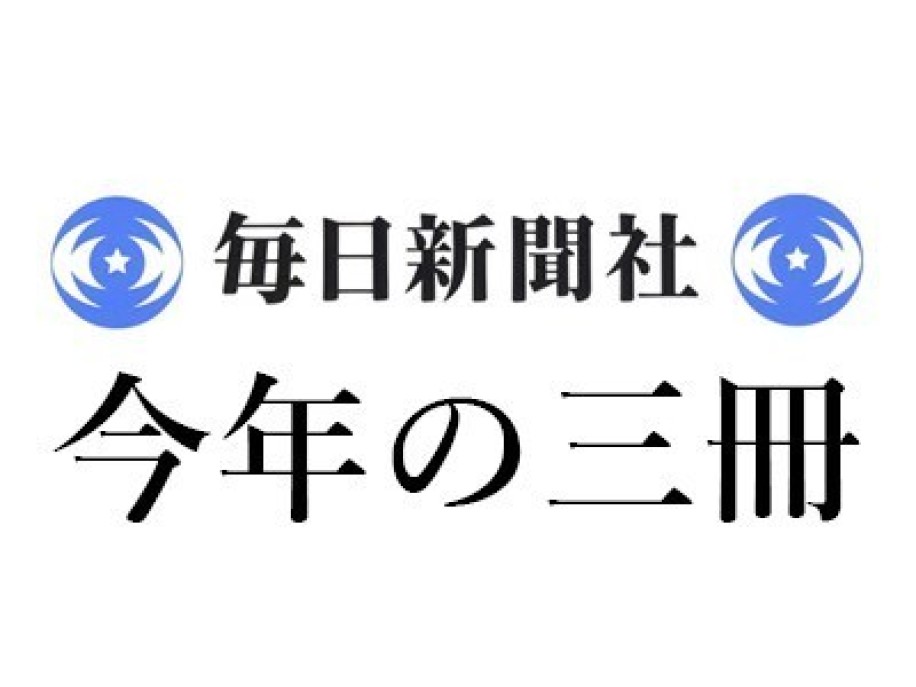書評
『海の夜明け―日本海軍前史』(徳間書店)
少々私ごとを述べると、私の家はもと田安徳川家に仕える下級武士であったが、維新後、曽祖父の代から軍人の家となった。だから、旧日本海軍のこととなると、何やら親しみのようなものを覚えるのだが、ではその日本海軍がどのようにして呱々(ここ)の声を上げたかということになると、まるで知らないまま過ごしてきた。
夙く安政二年(西暦1855年)の十月、長崎に幕府の海軍伝習所という学校が出来た。
これはいよいよ周辺海域に列強の軍艦が出没して、風雲の急なることを痛感した幕府が、遅ればせながら、幕臣を主として人材を選抜し、オランダ軍人のペルス・ライケンらの教授団に西洋航海術を中心とする技術教育を伝授せしめ、以て我国独自の海軍を立ち上げようという試みであった。
本書は、この日本海軍の黎明期に光を当て、いかにして彼ら伝習生たちが悪戦苦闘の末にその技術を習得して独り立ちしていったかというところを、丹念に辿った歴史小説である。もとより群像小説だから、誰が主人公というのではないが、著者の目は、主として鶴松という塩飽(しあく)水軍の家の下働きだった男に注がれている。
あるときは史実から離れ、あるときは史実どおり具体的に、筆者の筆遣いは自由自在である。そうして、読者は、たちまち咸臨丸の内部に自ら搭乗しているような痛快さを味わうことが出来る。
日本の近代は、こういう青年たちの涙ぐましい努力と頭脳によって育てられてきたのだということを、この本は教えてくれる。
そうして、明治維新といっても、決して薩長土肥だけの手柄でない。幕府もまた多くの人材を出してこの時代を支えたのだと思って、少しうれしくなった。
夙く安政二年(西暦1855年)の十月、長崎に幕府の海軍伝習所という学校が出来た。
これはいよいよ周辺海域に列強の軍艦が出没して、風雲の急なることを痛感した幕府が、遅ればせながら、幕臣を主として人材を選抜し、オランダ軍人のペルス・ライケンらの教授団に西洋航海術を中心とする技術教育を伝授せしめ、以て我国独自の海軍を立ち上げようという試みであった。
本書は、この日本海軍の黎明期に光を当て、いかにして彼ら伝習生たちが悪戦苦闘の末にその技術を習得して独り立ちしていったかというところを、丹念に辿った歴史小説である。もとより群像小説だから、誰が主人公というのではないが、著者の目は、主として鶴松という塩飽(しあく)水軍の家の下働きだった男に注がれている。
あるときは史実から離れ、あるときは史実どおり具体的に、筆者の筆遣いは自由自在である。そうして、読者は、たちまち咸臨丸の内部に自ら搭乗しているような痛快さを味わうことが出来る。
日本の近代は、こういう青年たちの涙ぐましい努力と頭脳によって育てられてきたのだということを、この本は教えてくれる。
そうして、明治維新といっても、決して薩長土肥だけの手柄でない。幕府もまた多くの人材を出してこの時代を支えたのだと思って、少しうれしくなった。
初出メディア
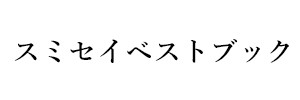
スミセイベストブック 2005年1月号
ALL REVIEWSをフォローする