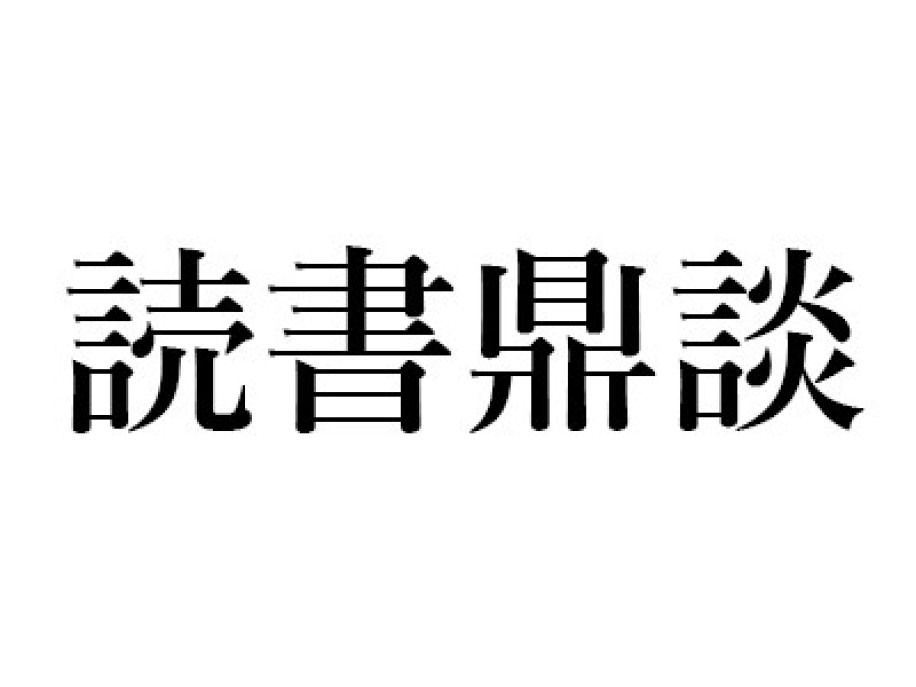書評
『戦争と広告 第二次大戦、日本の戦争広告を読み解く』(KADOKAWA/角川学芸出版)
日本人の変わらぬ現実あざむく手口
著者は一九七五年生まれ。戦争を知らない世代が意味深い仕事をした。日中戦争から太平洋戦争にわたる「戦時下の日本」を、当時のグラフ雑誌を通して見ようというのだ。主として『写真週報』。政府また軍部直々(じきじき)のプロパガンダ誌で内閣情報部創刊。これを補って、もう一つが『アサヒグラフ』、朝日新聞社の発行。ともに戦時下の日本と日本人を伝えるとともに、当の発行者が何を国民に求め、いかなる誘導を図ったかを色濃くとどめている。それが陰に陽に軍国主義の下支えをした。
グラフ誌は写真を大きな武器とした。それにキーワードがかぶせてある。「一億、今ぞ敵は米英だ!」「新体制の躍進」「前進する日本軍」「空前の大戦果」……。戦線の拡大とともに新しい項目が入ってくる。「大東亜共栄圏」「南へ! 南へ!」「アジヤ ワ ヒトツ」。つかのまの勝利が、なだれを打つような劣勢にうつると、「特別攻撃隊の勇士」「決戦熾烈(しれつ)」「われら一億英魂に應(こた)へん」「撃ちてしやまむ」。
プロパガンダ用であれば、民衆にウケることは派手にのせるが、政府や軍部に不都合なことは省く。隠し、すりかえる。戦果は誇示しても、同時に受けたはずの損害は「微少」で片づける。全滅は「玉砕」といった詩的用語に美化し、追い立てられても「転進」である。特攻こと特別攻撃隊は敗色濃くなってから編み出された戦術と思われているが、真珠湾奇襲攻撃で「甲標的」と呼ばれた特殊潜航艇乗組員に、すでに使われていた。出撃すると、帰還はほぼ不可能。
「純忠比なし軍神九柱」
兵士は死ぬための人材であり、死ねば「神」として祀(まつ)るプログラムは当初からあったわけだ。
「滅敵の闘魂を沸(たぎ)らせつゝ聖寿の万歳を奉唱し、決死敵飛行場を急襲せんとする」(『写真週報』1944年12月13日号)記事と写真で、命をかけて出撃する男の美しさを強調している。どの顔も死を間近にしていながら動揺をたたえていない。「この記事や写真は、決して語らず視覚化もしていないことが二点ある」
写真は出撃までのものであって、その後のこと、戦果はもとより部隊についても何一つ語っていない。語れないからである。実のところ、この空挺(くうてい)隊は台湾の高砂(たかさご)族を中心に編制されたものであって、皇国の守りのために台湾人が動員された。
さらに「崇高な特攻魂」の写真に欠けているものがある。そえられた文言からも見てとれる。「淡々といでたち」「淡々と出撃して行く」「淡々として大空翔(か)けて征(ゆ)く」。無表情こそ「皇国としての特攻隊の特徴」であって、特攻魂なるものの容(い)れ物としての無機的な身体にすぎない。「悠久の大義」「神国不滅」「護国の霊」……。時代の常套句(じょうとうく)によって呪縛し、古歌にちなんで部隊を命名して、死を運命づけて送り出す。「大東亜戦争」と称した戦争の特異さ、異様さがうかがえる。
過去を検証するだけではない。若手研究者は冒頭で、二○一四年五月、安倍首相が集団的自衛権の必要性を記者会見で説明した際、使用したパネルの母と子のイラストをとりあげた。視覚が何を誘導するか。さらに終章には、大阪の「ピースおおさか」、東京の総務省委託の平和祈念展示資料館、広島県呉市の大和ミュージアム、靖国神社の遊就館などが紹介してある。章名は「二一世紀における大東亜戦争」。政治的効果を狙った視覚文化と語り口、現実をカモフラージュする手口において、日本人は少しも変わっていないのである。
ALL REVIEWSをフォローする