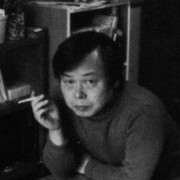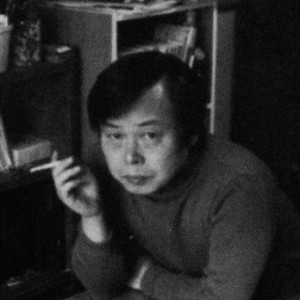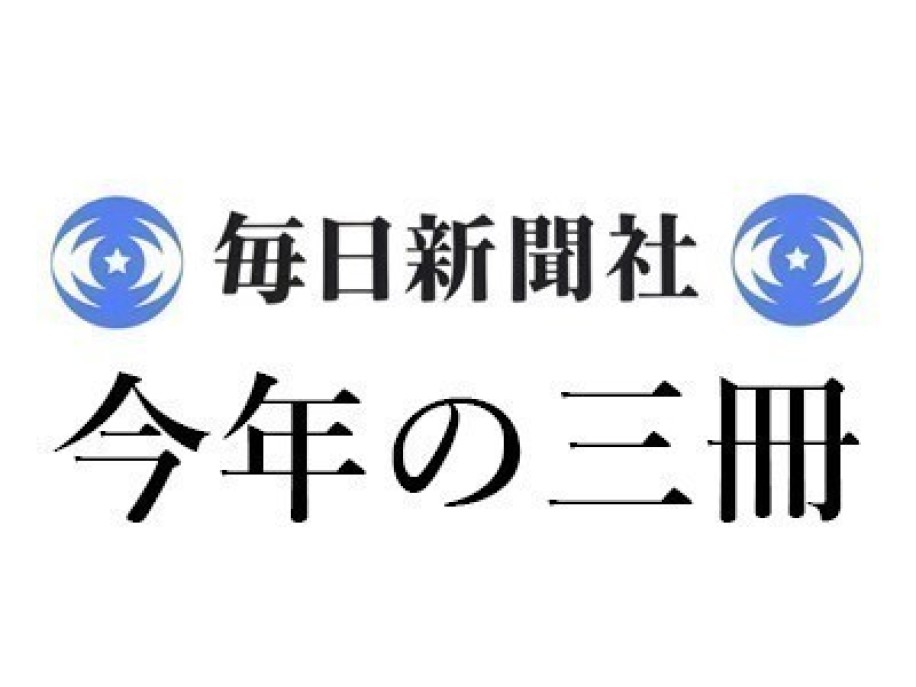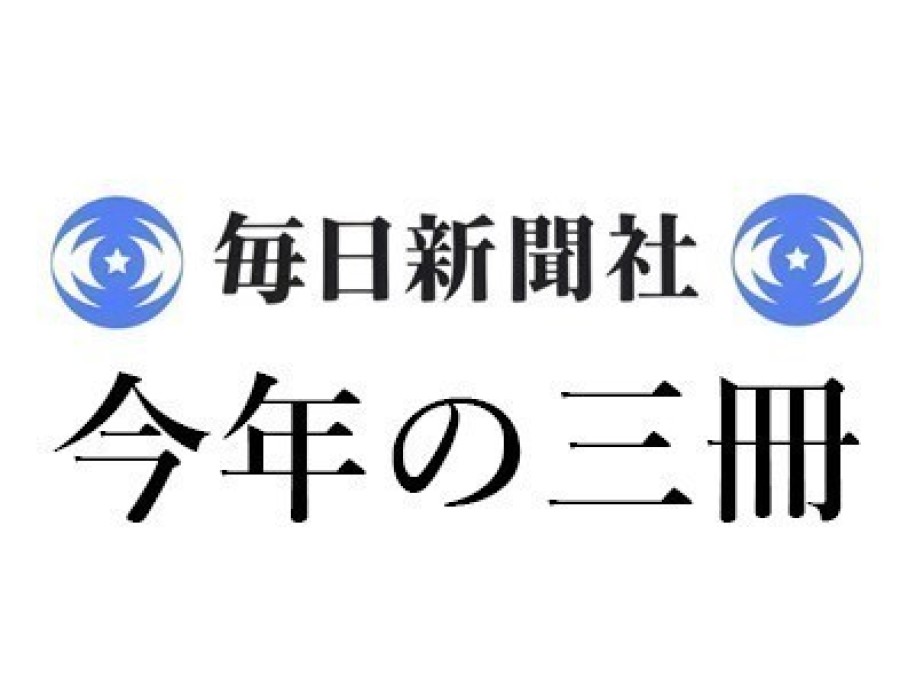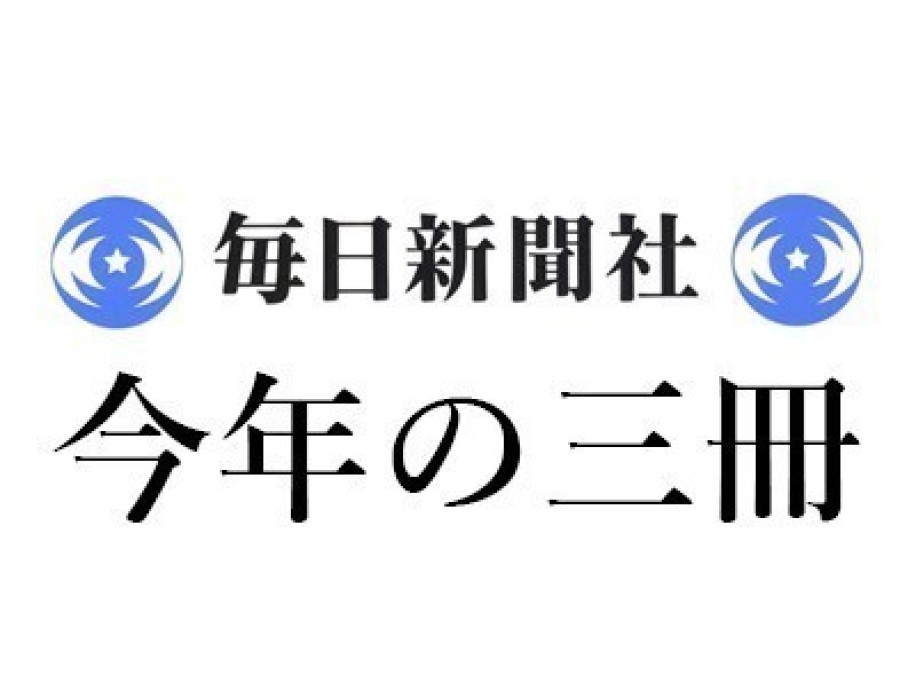書評
『ブダペストの古本屋』(筑摩書房)
物静かに語られる悠々たる学風
一九四一年に最晩年のリヒャルト・シュトラウスとフランツ・レハールのそれぞれ自作を指揮する演奏会を聴いた、と聞けば、ああ幸運にもその世代は間に合ったのだなと溜息をついて忘れてしまいたい。よほどしつこい男でなければ、それから二、三日は眠れないということにはならないだろう。すでに過去に属していた巨匠の晩年の姿にふれたという幸運だからだ。しかし、一九四〇年に亡命直前のバルトークの最後の演奏会を聴いたとなると、話はおのずとちがってくる。現在完了形の出来事であり、それをめぐる歴史的状況の意味はいまもって去ってはいないので、人をなまなましい興奮に誘うのである。どうかするとそうした稀な出来事に立ち合った当事者は、出来事の歴史的意味はもとより、自分がそこに立ち合っていたというめぐり合わせそのものにむやみに陶酔して、たぶん当人以外には誰も面白がりそうにはない感激を、量にすれば二三五頁位の本に一気に書き上げてしまうのではなかろうか。ふつうはそうだ。
徳永康元氏の『ブダペストの古本屋』には、一九四〇年十月八日にハンガリーでのバルトーク最後の演奏会を聴く挿話が出てくる。徳永氏も最後のバルトークを聴いたのである。それなのにこの著者はその出来事を二三五頁の本に書くかわりに、二三五頁の本のなかの数行としてさらりと書いた。では、その出来事とそこに立ち合っていたことの意味に誰が感激するかといえば、もっぱら他人が感激するのである。徳永氏にその晩のことを聞かされた戦後のあるハンガリーの音楽院の学生は、大きく両手をひろげて「ファンタスティック」と奇声を発したのだそうだ。
ことほど左様にここには、口をつければウォトカのように強烈に陶酔するはずの挿話が、水を飲むように淡々と語られている。水を飲む人の文章なのである。一つ一つのエッセイの主題は、古本屋めぐり、映画、相撲、能、留学体験、ハンガリー文学、大正昭和文学、書誌学、言語学と多方面に亘りながら、一貫して細部を正確明快に提示し、他人がそれらの細部からして「ファンタスティック」と奇声を上げることは許しても、みずからはけっして概括的な見取図書きや性急な主張をしない。それでいて、その貴重な細部や書誌学的細目を取り出してくる懐がどこまで深いか底知れないので、しまいには事物そのものをして語らしめる、この物静かなスタイルが空おそろしくなってくる。
たぶん右の消息は著者の知的世界への入り口が大正文化であったことと無関係ではないだろう。映画とマイナー・ポエットの私小説、一例がハンガリーのような小国文化への関心と辺境エキゾチシズムがめばえる土壌がはじめて培われたのは、声高な壮士調が低い声を消した明治でもなければ、けたたましい成長とイデオロギーの時代だった昭和でもなくて、ほかならぬ大正だからだ。徳永氏の専門キャリアからするとオヤと思えるような人名が登場してくるのも、これで納得がゆく。植草甚一、串田孫一、田宮虎彦、上林暁——一九一〇年前後生れの世代には、こまやかな細部への愛を控え目ながら執拗につらぬいてきた共通のアトモスフェアが立ちこめている。パルラ・バッソ。幸いなことに、声高な絶叫にたえずかき消されてきた低声の持主たちは、耳のいい少数の読者にそれとなく囲まれて語り続けることをやめない。
徳永氏のハンガリーとの接点は、大ざっぱに言って三つある。二重帝国の最後の残照が輝いていた四〇年代初頭、それがバベルの塔もさながらに崩壊してゆく四二年のパニック、最後に戦後再分割されたハンガリー再訪である。四二年のパニックを現場から報告する戦前の紀行文の悪夢的な緊迫も、古き良きブダペスト回想も、それぞれに十二分に読みごたえがある。だがそれはそれとして、『舞踏会の手帖』風に綴られた戦後再訪の短文のなかに、進行中の小国の悲劇を一触に書ききった名品があり、とりわけサボー・テレーズという元言語学者の女医や、レヘル君という抽象画家や、イリさんというユダヤ女性の今昔を語った「ブダペスト今昔」という、暗い熱情の底流する小品が全篇の白眉として心に残る。
私事ながら、ヨーロッパ文化の端っこをほじくっている私のような人間にも、ハンガリー文化に接触しなければならない局面がときたまは訪れる。一度は一人の錬金術師の生涯を辿っているときにハンガリー・ルネッサンスの目のくらむような宝庫の一端を垣間見ることがあり、ついで三月革命後のマゾヒスト作家のブダペスト文壇との関わりを調べ、それから今世紀初頭の二重帝国をハンガリーの側から生きた一人のぺてん師の生涯を追うことに関わった。そしていずれの場合にも、ハンガリー文化に関する資料や文献がおいそれとは身近に見つからないことを思い知った。
これからはちがうだろう。事物そのものの細部が語る言葉を聞き取る徳永氏の学風は、ここに語られているのが氷山の一角にすぎないとしても、若い世代を傾倒させて、ハンガリー文化研究に誘うだろう。ハンガリー研究の将来は明るいだろう。
中央公論 1982年10月号
雑誌『中央公論』は、日本で最も歴史のある雑誌です。創刊は1887年(明治20年)。『中央公論』の前身『反省会雑誌』を京都西本願寺普通教校で創刊したのが始まりです。以来、総合誌としてあらゆる分野にわたり優れた記事を提供し、その時代におけるオピニオン・ジャーナリズムを形成する主導的役割を果たしてきました。
ALL REVIEWSをフォローする