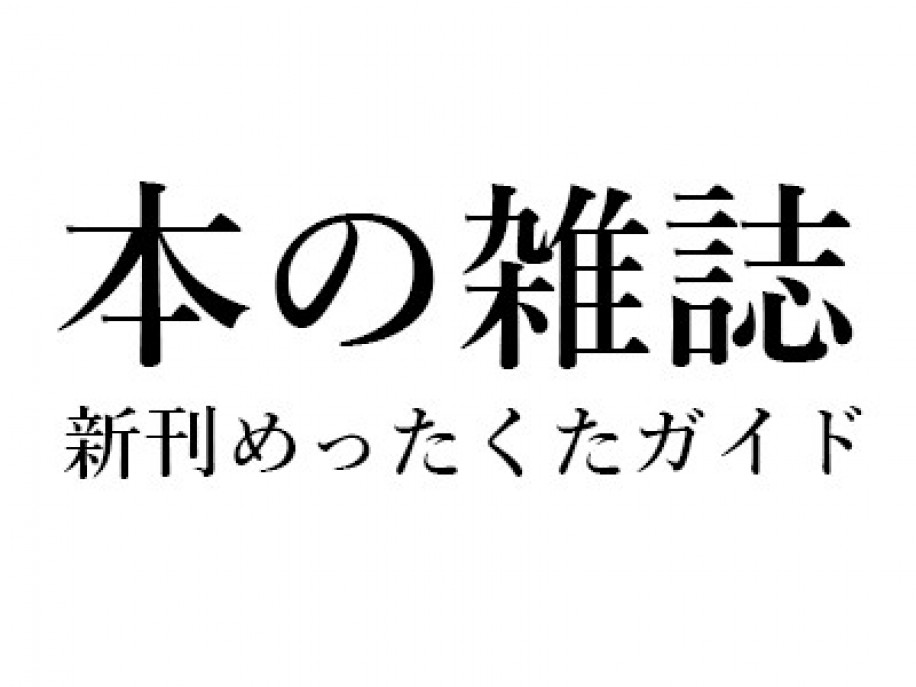書評
『神様のみなしご』(角川春樹事務所)
一人ぽつんと存在する子供たちの物語
海辺に建つ養護施設「愛生園」を舞台に、複数の登場人物が一人称で語りつなぐ物語。語り手は職員や周囲の大人たちではなく、すべて園にいる(あるいはいた)子供たちだ。小学生か中学生。園には「高校生も少しだけいる」のだが、「でも、ふつう、中学卒業したら、園を出て働きたいわね。俺だって、そうするつもり。どっか、住み込みのとこでも見つける。」と登場人物の一人が説明してくれるように、そこは彼らがずっといたい場所でも、ずっといられる場所でもない。たとえ、入園したとき「温かいトースト」や、「おみそしる」に感激したとしても、無料の歯科治療を「好き」だと思ったとしても。この小説に限ったことではないのだが、川島誠の書く一人称にはためらいがない。声とおなじくらい断固とした一人称、とでも言うべき強さがそこにはあって、読み手はその声に導かれ、ほとんど瞬時に物語のなかにひき込まれてしまう。短いセンテンス、絶妙な倒置法、曖昧さを排した記述、感じがわるいほど巧妙な皮肉。
愛生園では何が起るかというと、大きなことは何も(すくなくとも、表立っては)起らない。地区対抗のサッカー大会に出場するとか、お披露目会という、「簡単に言っちゃえば、たぶん、中学校の文化祭みたいなもん」があったり、ホームカミングデイという、卒園生の帰ってくる日があったりするくらいだ。平和といえば平和、平凡といえば平凡。作者はそれを淡々と描き、私はそれを、息をつめて読んだ。すさまじいことは、すでに起きてしまっているのだ。
宮本という双子の兄弟の父親は刑務所にいて、母親はべつの男と逃げてしまった。かつて裕福だった谷本理奈は、父親が事業に失敗し、その後両親が心中してしまう。相川美優は父親に性的な虐待を受けていた。もっともっとある。暴力、貧困、育児放棄、いじめ、殺人事件。
一人ずつの持つ物語には、勿論(もちろん)繊細でふくよかなディテイル――飯場のバイク、やさしくされた記憶、母親の水商売仲間にのませてもらったメロンジュース、水辺のカモメの声、深夜の中華料理、命がけで守ってもらったのだという事実――があるのだが、同時にあまりにも陰惨に陳腐で(そうではないだろうか。男親は酒やギャンブルに溺れ、女親は男に溺れるか逃げるか、そうでなければ不幸な死を迎える)、世のなかが現に陳腐なのだという事実に圧倒されてしまう。
それらの、どれ一つとっても痛々しい長編小説になりそうな事情や事故や犯罪や悲劇に、たった一人でさらされたあとの、サッカーとかお披露目会とかホームカミングデイとかなのだ。
たとえばサッカーの試合において、子供たちは一丸にはならない。一丸になれるはずなどないわけで、でも、そこにはスポーツをする者が避けようのない、心情や思惑や本能や、連帯や喜びのようなものが、ぼんやりと発生する。
描かれるのは、個としての彼らだ。家庭という背景を失い、愛生園という中継地点をべつにすれば、どこにも帰属せず一人ぽつんと存在する、素のままの彼ら。一人ずつを見ると、彼らは決して健気ではないし、たくましくない。でも、健気に思えるし、たくましく思えてしまう。そう感じるよりないという、そのひずみ。
川島誠はほんとうに容赦がない。神父のでてくるくだりや、愛生園をめぐる新聞記事があきらかにするように、この施設もまた、陳腐な世間の一部なのだ。
ALL REVIEWSをフォローする