書評
『ラテンアメリカの新しい伝統―「場の文化」のために』(晶文社)
コミュニケーションの在り方を問うラテンアメリカ演劇の試み
村上春樹の小説は、基本的にはモノローグの世界であり、登場人物たちの間にダイアローグらしきものが成り立つとすれば、共通の過去が話題になるときだけである。だがそのコミュニケーションの回路もたちまち切断されてしまう。高度資本主義社会ののっぺりとした空間は、もはや対話の場とはならない。あるいは中上健次は、生きいきとした対話が成り立つ場としての「路地」を消し去ったのち、大都会の繁華街で仮面を被って生きる人々を描いてみせた。そこでは本来コミュニケーションであったはずの性は、商品に成り下がってしまっている。
本書の真のメッセージは、サブタイトルにこめられているようだ。すなわち上に述べたような状況の中で、対話的創造が可能な場をいかにして再構築するかという問題である。そのためのモデルを求める過程でパウロ・フレイレの識字教育に出会ったことが、ラテンアメリカで現在実践されている対話の場の構築、あるいは再構築をめざす様々な試みの発見へと著者を導いたのだろう。
扱われているのは識字運動のほかに、それと密接な関係を持った民衆演劇運動やブラジルの民衆本「コルデル」などであるが、共通するのは、著者がそれらを対話の場として捉えていることだ。だがそのような「場」は、上から下への一方的伝達をこそ支配の装置として必要とする権力や権力のスポークスマンとして機能するマスメディアにとっては、危険きわまりないものとなる。そこで様々な圧力が加えられ妨害が行われる。
一方、左翼陣営においても、「場」の理解が不十分であれば、そこに成立するコミュニケーションは、権力のそれとなんら変わりない。この問題はアジェンデ政権下のチリで露呈したのだが、政権崩壊とともに未解決のまま残されてしまった。しかし、今日のソ連・東欧の動きを見るとき、コミュニケーションの在り方をめぐる問題は、より重要性を増したといえるだろう。各国共産党の支持率の低下は、官製コミュニケーションに対する不信の結果でもあるからだ。
その意味で、コロンビアやブラジルの演劇集団の試みは、ラジカルであるとともに普遍性を帯びている。それはコミュニケーションの在り方そのものを問題にしているからだ。
たとえばシュールリアリズムがそうであるように、ヨーロッパで生まれた運動や思想が、むしろ辺境で実を結ぶということがある。本書はそうした例のーつとして、ラテンアメリカにおけるブレヒトの受容に焦点を当てている。ブレヒトの演劇を制度としてではなく、生きたものとして捉え、信念を持って脱構築してしまうラテンアメリカの演劇人のバイタリティーが素晴らしい。先年、『三文オペラ/リオ1941』というブラジル映画が日本で公開されたが、音楽を担当したシコ・ブアルキは、まさしくブラジルのブレヒト劇で鍛えられている(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1990年)。この映画を踏まえる形で田原俊彦主演の『マランドロ』が最近上演されたようだが、演出の宮本亜門に是非本書を読ませたかった。本書によると、劇団「かものはし」がニューヨークで『マハゴニイ』を脱構築してみせたところ、一大スキャンダルを巻き起こしたという。その埋め合わせに金を要求されたというエピソードは、いかにも現代を象徴していておかしいが、それに屈しない演劇人の硬派ぶりというのは、今の日本ではほとんどお目に掛かることがない。
だからこそ著者が本書を著したことはいうまでもない。
初出メディア
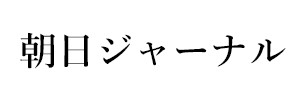
朝日ジャーナル(終刊) 1990年8月31日
ALL REVIEWSをフォローする






































