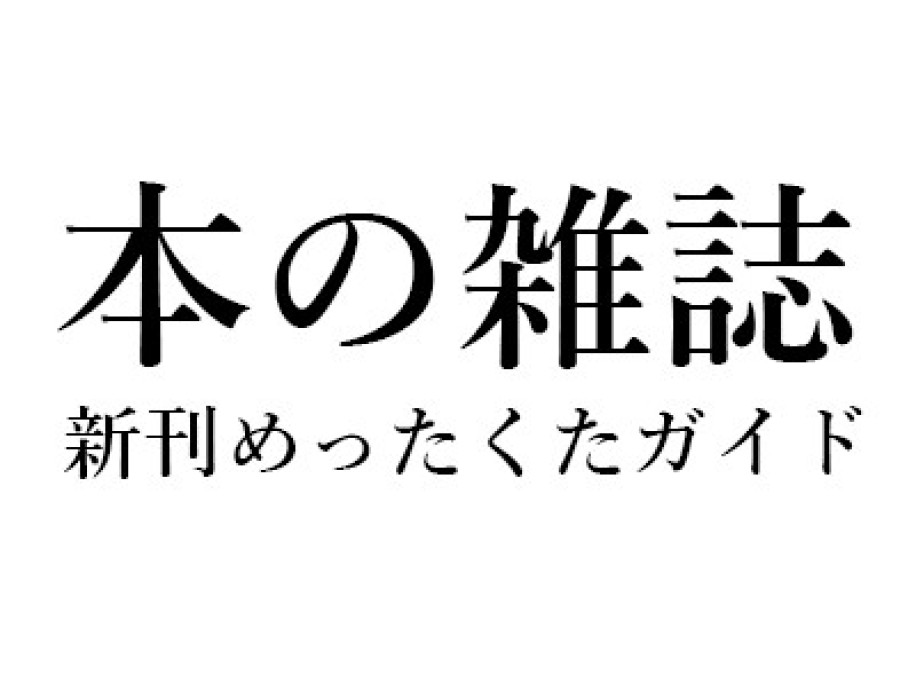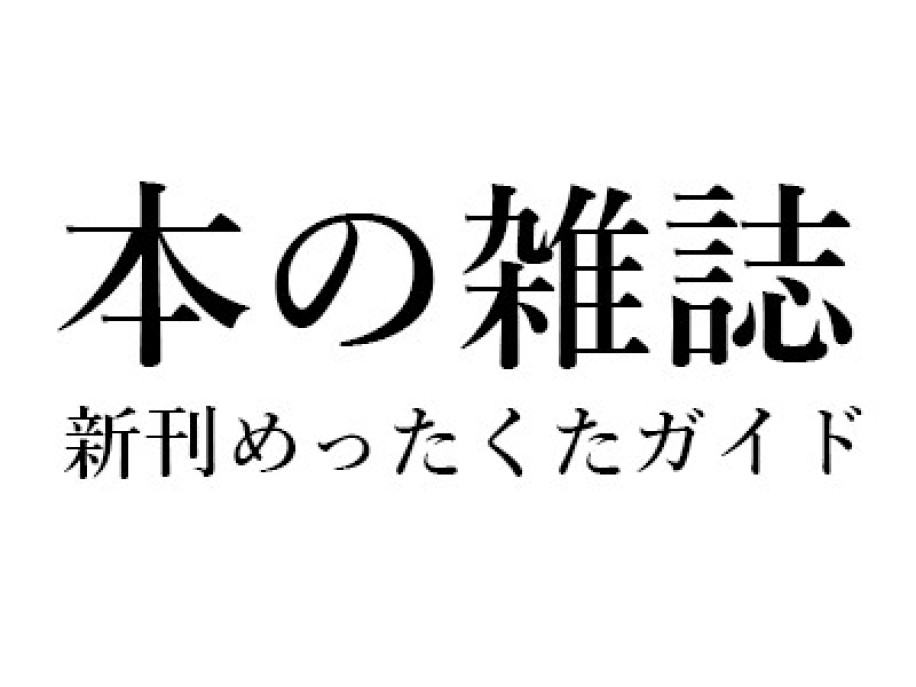解説
『薬菜飯店』(新潮社)
「薬菜飯店」は、この短編集のなかの一編のタイトルであるけれど、次々と現れる作品は、筒井康隆主人が腕をふるう『薬菜飯店』で供される美味珍味のようだ。つまり、目次はメニューである。
今までに味わったことのない世界、夢と現実とをいったりきたりする体験、心と体がスカッとする感じ……という点でも「薬菜飯店」と『薬菜飯店』の料理は似ている。
そして、その『薬菜飯店』の栄えあるデザートとして登場するのが「カラダ記念日」だ。
デザートは、独立しておいしいものであると同時に、それまでの料理と響きあうことが望ましい。「小説新潮」で読んだとき以上に、私にとって『薬菜飯店』の「カラダ記念日」がおもしろかったのは、たぶんその前の一編「偽魔王」と響きあったからだろう。
「カラダ記念日」に登場する君(ダチ)や組長などといった言葉が、「偽魔王」の遠藤や猿田や岸や浜名といったキャラクターと自然に重ねあわされて、世界がいっそう生き生きと感じられた。
さて、その「カラダ記念日」であるが、言うまでもなく私の歌集『サラダ記念日』のパロディである。被パロディ体(?)の側から「解説」を書くというのは、ちょっと照れくさいような気もしたけれど、あえてペンをとった。理由のひとつは、単純に作者として嬉しかったから。そしてふたつ目は、読者としてそのおもしろさの秘密を、書いてみたかったから。
『サラダ記念日』が歌集としては珍しくベストセラーになった当時は、社会現象とまで言われ、短歌のパロディも巷にあふれていた。なかでも頻繁にその対象となったのは、次の三首である。
「嫁さんになれよ」だなんてカンチューハイニ本で言ってしまっていいの
「愛人でいいの」とうたう歌手がいて言ってくれるじゃないのと思う
「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日
「○○○」だなんてナントカカントカで言ってしまっていいの――で、一丁あがりである。
ナントカカントカ……言ってくれるじゃないのと思う――で、二丁あがりである。
「ナントカ」と○○サンが言ったから×月×日はナントカ記念日――で、三丁目もあがり。
五年もたった今では信じられないようなことだが(ALL REVIEWS事務局注:本解説執筆時期は1992年)、たとえば巨人軍の桑田投手が快勝した翌日のスポーツ新聞のトップには「クワタ記念日」の文字が踊っていた。
「作者としては、どういう気持ちです? こういうのって」という質問をよく受けた。あるいはもっとストレートに「やっぱり腹がたつでしょ。おちょくられているみたいで」と言われたことも多い。が、私はべつに腹はたたなかった。パロディが成立するということは、モト歌が親しまれているということだ。そう思えば、むしろ嬉しく感じてしまったくらいである。
ただ、言葉が好きな人間としては、あまりにもお手軽なものが多いのには、ちょっぴり寂しい気がした。右に書いた「一丁あがり」から「三丁あがり」のパターンがほとんどなのである。
そんななかで出会ったのが「カラダ記念日」だった。びっくりした。ここまで真剣に遊んでもらったら、モト歌たちも本望だろう。
まず、数がすごい。半端ではない。しかも、一首一首を恣意的にパロるのではなく、全体を通して、「短歌を作るのが好きな一人の極道」の姿が浮かびあがってくるという仕組み。
そしてタイトルに象徴されるように、できるだけモト歌の言葉に近い音であることが、心がけられている。パロディなんだから、あたりまえじゃん、と思われるかもしれないが、この「音への執着」が「カラダ記念日」全体を、とてもおもしろくしていると思うので強調したい。
大きければいよいよ豊かなる気分東急ハンズの買物袋
大きければいよいよ豊かなる気分盗品入った買物袋
意味的にも「盗品」はうまくつながっている。そのうえで「トウキュウハンズ」と「トゥヒンハイッタ」の音の類似が、楽しい。
「貝殻」→「亡骸」、「東京」→「独房」、「土曜日」→「検挙(ゴヨウ)日」(これは別にケンキョビでも、意味やリズムに支障はないが、音の点からいえば断然ゴヨウビだ)「揺れるコスモス」→「隠れる組長」……などなど、あげればキリがない。
まったく同じ言葉でも、状況が変わると、こんなにも色合いが違ってくるのか、と驚いた例も多かった。
「今日で君と出会ってちょうど500日」男囁くわっと飛びのく
「今日ここで汝(われ)と会うたが百年目」男囁くわっと飛びのく
ひところは「世界で一番強かった」父の磁石がうずくまる棚
ひところは「世界で一番強かった」親分(ボス)の位牌がうずくまる棚
モト歌と同じ状況からスタートして、笑える結末に展開するのもある。
「30で俺は死ぬよ」と言う君とそれなら我もそれまで生きん
「30で俺は死ぬよ」と言う仲間(ダチ)をそれなら30で殺してやろう
街頭のパントマイムに足を止め目と目が合ったようなしばらく
街頭のパントマイムに足を止め目と目が合って因縁をつける
あるいは、こんなのもある。
皮ジャンにバイクの君を騎士として迎えるために夕焼けろ空
皮ジャンにバイクの君(ダチ)を組長(ボス)として迎えるために掃除しろ馬鹿
同じ「迎えるために」だが、夕焼けよりも掃除のほうが、なんだか必然性があっておかしい。
タクシーの河の流れの午前二時眠り続ける横断歩道
タクシーから振り落された午前二時眠り続ける横断歩道
これは、ちょっとした言葉のマジックだ。下の句の見た目はまったく同じだけれど、「眠り続ける」の主語は変わってしまった。
短歌そのもののパロディとも言うべき強烈な一首もあって、忘れがたい。
一二三四五六七八九十十一十二十三十四
私は、五七五七七の定型を「魔法の杖」と呼んでいる。なんてことない言葉が、この定型にぴたっとおさまることによって、急に生き生きと輝きはじめるからだ。
言葉をリズムにのせる喜び。そして言葉のなかからリズムを発見する喜び。かつてこんな歌を作ったことがある。
万智ちゃんを先生と呼ぶ子らがいて神奈川県立橋本高校
自分の勤めている高校の名前が、そのまま下の句になることを発見したときは、とても気持ちがよかった。「一二三四五六七八九十……」を発見したとき、作者はさぞかし気持ちよかっただろうなあ、と思う。
しかし、これは単なる偶然だろうか。数を数えるときは、たいてい口に出して数える。
その場合、リズミカルなほうがいい。数字の読み方が「イチニイサン、シイゴオロクシチ、ハチクウジュウ……」というふうに落ち着いたのは、もしかしたら五七調の好きな日本人の体質が、そうさせたのかもしれない……なんてことまで考えてしまった。
「カラダ記念日」のおもしろさは、まだまだ尽きないけれど、あまり長い講釈は、やぼというもの(え?すでに充分長いですか)。これ以上読者の楽しみを奪わないように、ペンを置こうと思う。
――置こうと思ったが、最後に大切なことをもうひとつ。見てきたように、「カラダ記念日」は「サラダ記念日」と合わせ読むことによって、その真のおもしろさがわかるように作られている。つまり『薬菜飯店』と一緒に『サラダ記念日』も買われることを、あなたに強くおススメいたします。あはは。
【この解説が収録されている書籍】
今までに味わったことのない世界、夢と現実とをいったりきたりする体験、心と体がスカッとする感じ……という点でも「薬菜飯店」と『薬菜飯店』の料理は似ている。
そして、その『薬菜飯店』の栄えあるデザートとして登場するのが「カラダ記念日」だ。
デザートは、独立しておいしいものであると同時に、それまでの料理と響きあうことが望ましい。「小説新潮」で読んだとき以上に、私にとって『薬菜飯店』の「カラダ記念日」がおもしろかったのは、たぶんその前の一編「偽魔王」と響きあったからだろう。
「カラダ記念日」に登場する君(ダチ)や組長などといった言葉が、「偽魔王」の遠藤や猿田や岸や浜名といったキャラクターと自然に重ねあわされて、世界がいっそう生き生きと感じられた。
さて、その「カラダ記念日」であるが、言うまでもなく私の歌集『サラダ記念日』のパロディである。被パロディ体(?)の側から「解説」を書くというのは、ちょっと照れくさいような気もしたけれど、あえてペンをとった。理由のひとつは、単純に作者として嬉しかったから。そしてふたつ目は、読者としてそのおもしろさの秘密を、書いてみたかったから。
『サラダ記念日』が歌集としては珍しくベストセラーになった当時は、社会現象とまで言われ、短歌のパロディも巷にあふれていた。なかでも頻繁にその対象となったのは、次の三首である。
「嫁さんになれよ」だなんてカンチューハイニ本で言ってしまっていいの
「愛人でいいの」とうたう歌手がいて言ってくれるじゃないのと思う
「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日
「○○○」だなんてナントカカントカで言ってしまっていいの――で、一丁あがりである。
ナントカカントカ……言ってくれるじゃないのと思う――で、二丁あがりである。
「ナントカ」と○○サンが言ったから×月×日はナントカ記念日――で、三丁目もあがり。
五年もたった今では信じられないようなことだが(ALL REVIEWS事務局注:本解説執筆時期は1992年)、たとえば巨人軍の桑田投手が快勝した翌日のスポーツ新聞のトップには「クワタ記念日」の文字が踊っていた。
「作者としては、どういう気持ちです? こういうのって」という質問をよく受けた。あるいはもっとストレートに「やっぱり腹がたつでしょ。おちょくられているみたいで」と言われたことも多い。が、私はべつに腹はたたなかった。パロディが成立するということは、モト歌が親しまれているということだ。そう思えば、むしろ嬉しく感じてしまったくらいである。
ただ、言葉が好きな人間としては、あまりにもお手軽なものが多いのには、ちょっぴり寂しい気がした。右に書いた「一丁あがり」から「三丁あがり」のパターンがほとんどなのである。
そんななかで出会ったのが「カラダ記念日」だった。びっくりした。ここまで真剣に遊んでもらったら、モト歌たちも本望だろう。
まず、数がすごい。半端ではない。しかも、一首一首を恣意的にパロるのではなく、全体を通して、「短歌を作るのが好きな一人の極道」の姿が浮かびあがってくるという仕組み。
そしてタイトルに象徴されるように、できるだけモト歌の言葉に近い音であることが、心がけられている。パロディなんだから、あたりまえじゃん、と思われるかもしれないが、この「音への執着」が「カラダ記念日」全体を、とてもおもしろくしていると思うので強調したい。
大きければいよいよ豊かなる気分東急ハンズの買物袋
大きければいよいよ豊かなる気分盗品入った買物袋
意味的にも「盗品」はうまくつながっている。そのうえで「トウキュウハンズ」と「トゥヒンハイッタ」の音の類似が、楽しい。
「貝殻」→「亡骸」、「東京」→「独房」、「土曜日」→「検挙(ゴヨウ)日」(これは別にケンキョビでも、意味やリズムに支障はないが、音の点からいえば断然ゴヨウビだ)「揺れるコスモス」→「隠れる組長」……などなど、あげればキリがない。
まったく同じ言葉でも、状況が変わると、こんなにも色合いが違ってくるのか、と驚いた例も多かった。
「今日で君と出会ってちょうど500日」男囁くわっと飛びのく
「今日ここで汝(われ)と会うたが百年目」男囁くわっと飛びのく
ひところは「世界で一番強かった」父の磁石がうずくまる棚
ひところは「世界で一番強かった」親分(ボス)の位牌がうずくまる棚
モト歌と同じ状況からスタートして、笑える結末に展開するのもある。
「30で俺は死ぬよ」と言う君とそれなら我もそれまで生きん
「30で俺は死ぬよ」と言う仲間(ダチ)をそれなら30で殺してやろう
街頭のパントマイムに足を止め目と目が合ったようなしばらく
街頭のパントマイムに足を止め目と目が合って因縁をつける
あるいは、こんなのもある。
皮ジャンにバイクの君を騎士として迎えるために夕焼けろ空
皮ジャンにバイクの君(ダチ)を組長(ボス)として迎えるために掃除しろ馬鹿
同じ「迎えるために」だが、夕焼けよりも掃除のほうが、なんだか必然性があっておかしい。
タクシーの河の流れの午前二時眠り続ける横断歩道
タクシーから振り落された午前二時眠り続ける横断歩道
これは、ちょっとした言葉のマジックだ。下の句の見た目はまったく同じだけれど、「眠り続ける」の主語は変わってしまった。
短歌そのもののパロディとも言うべき強烈な一首もあって、忘れがたい。
一二三四五六七八九十十一十二十三十四
私は、五七五七七の定型を「魔法の杖」と呼んでいる。なんてことない言葉が、この定型にぴたっとおさまることによって、急に生き生きと輝きはじめるからだ。
言葉をリズムにのせる喜び。そして言葉のなかからリズムを発見する喜び。かつてこんな歌を作ったことがある。
万智ちゃんを先生と呼ぶ子らがいて神奈川県立橋本高校
自分の勤めている高校の名前が、そのまま下の句になることを発見したときは、とても気持ちがよかった。「一二三四五六七八九十……」を発見したとき、作者はさぞかし気持ちよかっただろうなあ、と思う。
しかし、これは単なる偶然だろうか。数を数えるときは、たいてい口に出して数える。
その場合、リズミカルなほうがいい。数字の読み方が「イチニイサン、シイゴオロクシチ、ハチクウジュウ……」というふうに落ち着いたのは、もしかしたら五七調の好きな日本人の体質が、そうさせたのかもしれない……なんてことまで考えてしまった。
「カラダ記念日」のおもしろさは、まだまだ尽きないけれど、あまり長い講釈は、やぼというもの(え?すでに充分長いですか)。これ以上読者の楽しみを奪わないように、ペンを置こうと思う。
――置こうと思ったが、最後に大切なことをもうひとつ。見てきたように、「カラダ記念日」は「サラダ記念日」と合わせ読むことによって、その真のおもしろさがわかるように作られている。つまり『薬菜飯店』と一緒に『サラダ記念日』も買われることを、あなたに強くおススメいたします。あはは。
【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする