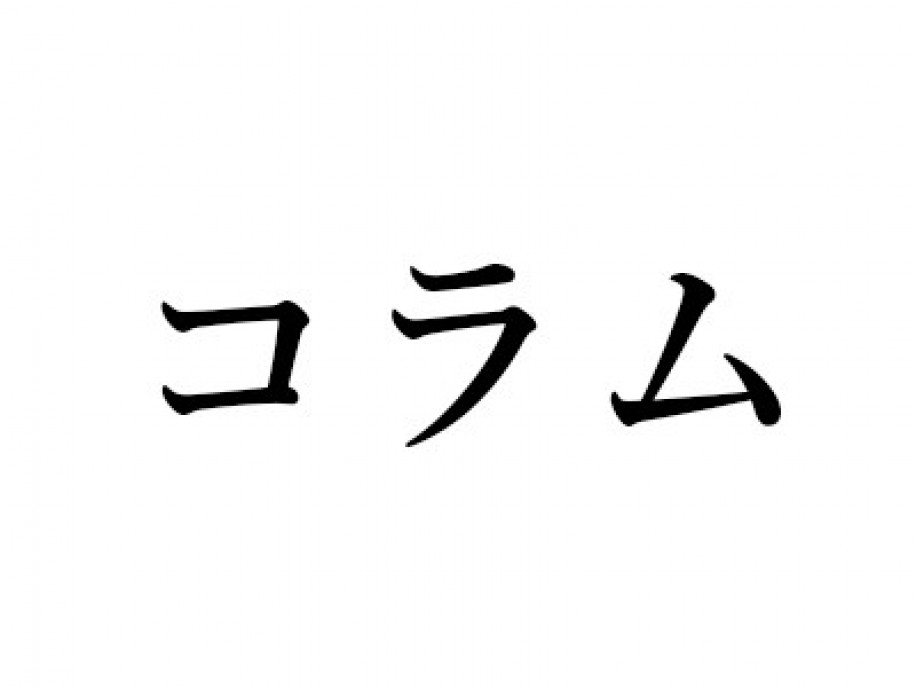書評
『カチカチ山』(新潮社)
『カチカチ山』(『お伽草紙』(新潮社)収録)
「カチカチ山」で、太宰治が鮮やかに描いてみせた「すべての女性の心に住んでいる残忍な兎」と「すべての男性の心の中で溺れかかっている善良な狸」――現代の日本では、この兎と狸は、恋愛の場面に限らず現れているような気がする。兎が狸を嫌悪するところはことごとく、まるで現代のOLたちが、「オジサン」と呼ばれる中年男性に対して、容赦ない言葉を吐いているかのようだ。あるいは、清潔好きの女子中学生が、父親に嫌悪感を抱くのにも似ている。
兎のセリフを挙げてみよう。
「助平の上に、また食い意地がきたないったらありゃしない」
「傍へ寄って来ちゃ駄目だって言ったら。くさいじゃないの」
「あれ、寄って来ちゃ駄目だって言うのに。油断もすきもありゃしない。よだれを拭いたらどう?下顎がべろべろしてるじゃないの」
「ケチンボだから罰が当たったんだわ。ただの薬だから、ためしてみたなんて、よくもまあそんな下品な事を、恥ずかしくもなく言えたものねえ」
ある雑誌に連載されている「部課長必読! おじさん改造講座」を私は思い出してしまった。そこでは毎週さまざまなおじさんが、八百人からなるOL委員会から告発(?)を受けている。たとえば、
「はなをかんだティッシュを他人にみせるのはやめてほしい」
「ごはんの時、くしゃみとともにゴハンつぶを飛ばした」
「酔っぱらい運転で留置場に一晩泊められて『メシがまずい』と言ってもう一晩泊められた」
こんな調子である。「たぬきオヤジ」という言葉があるが、「カチカチ山」の狸も、多分にこの「オヤジ的要素」を感じさせる。
ぐいとその石油缶ぐらいの大きさのお弁当箱に鼻先を突込んで、むしゃむしゃ、がつがつ、ぺっぺっ、という騒々しい音を立てながら、それこそ一心不乱に食べている。
(中略)狸は兎にきょうはひどく寛大に扱われるので、ただもうほくほくして、とうとうやっこさんも、おれのさかんな柴刈姿には惚れ直したかな? おれの、この、男らしさには、まいらぬ女もあるまいて、ああ、食った、眠くなった、どれ一眠り、などと全く気をゆるしてわがままいっぱいに振舞い、ぐうぐう大鼾を搔いて寝てしまった。
一応デートということになっている場面でこうである。兎が残酷なことは私も認めるが、
残酷の炎に油を注ぎ、ムラムラと燃えあがらせるようなところが、狸にはある。
兎が、狸の気持ちの隅々までを理解しているのに比べて、狸はまるで兎の気持ちへの配慮がない。まわりの人がみんな自分と同じ思いや価値観を持っている、と信じている単純さ。それも信じているだけならまだいいが、その信念にもとづいて行動をおこすからタチが悪い。迷惑をかけていることに気づかない最も典型的な場面を抜き出してみよう。
「遊びに来ましたよ。うふふ。」と、てれていやらしく笑う。
「あら!」と兎は言い、ひどく露骨にいやな顔をした。(中略)兎が、あら! と言い、そうして、いやな顔をしても、狸は一向に気がつかない。狸には、その、あら! という叫びも、狸の不意の訪問に驚き、かつは喜悦して、おのずから発せられた処女の無邪気な声のごとくに思われ、ぞくぞく嬉しく、また兎の眉をひそめた表情をも、これは自分の先日のボウボウ山の災難に、心を傷めているのに違い無いと解し、「や、ありがとう。」とお見舞いも何も言われぬくせに、こちらから御礼を述べ、……(後略)
一事が万事こうなのだ。こんな狸に優しくしろと言われても、まだ若い兎には無理というものだろう。
太宰のカチカチ山で強調されている「処女の残酷性」は、その人生経験の少なさゆえに
純粋で歯止めがきかない。
――同じ女として、私は少し兎に味方しすぎだろうか?ただ、最後の最後になって狸もいいことを言う。
「惚れたが悪いか。」
これは、なかなかの名言だ。たしかに、惚れたことに罪はない。惚れたことは悪くない。
そして狸のすべての行動は、この悪くないことから出発しているのだ。
先ほど、兎は狸の気持ちの隅々まで理解していると書いたけれど「この狸は私に惚れている」という点を、もう少しくみとってやっても、よかったかもしれないなあ、とは思う。
言い方をかえれば、狸は兎に、惚れさせられていたのだから。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
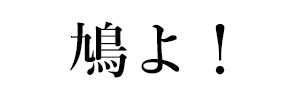
鳩よ!(終刊) 1991年7月号
ALL REVIEWSをフォローする