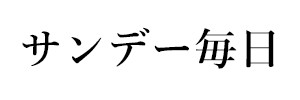書評
『メイドの手帖 最低賃金でトイレを掃除し「書くこと」で自らを救ったシングルマザーの物語』(双葉社)
底辺を生きる“透明人間”が自らの力で光をつかむまで
最低賃金で請け負うのは、依頼主の家を掃除する「メイド」。床磨き、荷物の整理、バスルームやトイレの掃除……ハウスクリーニングなら何でも引き受けるのが、二十代のシングルマザー、ステファニーの仕事だ。『メイドの手帖』は、著者ステファニー・ランドの回想録であり、手記であり、同時代を生きるシングルマザーの物語である。彼女をつねに脅かす貧困、飢え、ホームレス生活、DV、生活保護、病気、福祉の不備……ひとつひとつが社会の軋みを露わにする。アメリカでも日本でも、生活の格差あるいは分断が広がり、さらにコロナ禍は「格差社会」の様相を浮き彫りにした。しかし、そこには隣人ひとりずつの生の現実があるのだから、目を逸らすわけにはいかない。
「私の娘はホームレスシェルターで歩くことを覚えた」という一文によって始まる苦闘の物語。ミアの父親ジェイミーとの関係を修復することが「最悪」から抜け出す有効手段だと思い、努力を試みるのだが、うまくはいかない。両親は遠方に住み、とりわけ母親との複雑な関係は心の傷であり続けている。頼りはピーナツバターとインスタントラーメン、マクドナルドのハンバーガーは贅沢品。週二十五時間働き詰めても、つねに生活費は足りない。孤立無援のなか、すがるようにして得たのが清掃会社が派遣するプロの清掃員の職だった。
驚くべき観察眼で綴られるメイドとしての日々。住人の不在を通じて生活の気配を匂わせ、人物像の陰影が語られる展開はスリリングでさえある。ベッドの様子やナイトスタンドに残されたティッシュ。家庭内別居中らしい夫婦のベッドルームに置かれたポルノ雑誌や恋愛小説。あるいは、トイレのあちこちに落ちている陰毛、ごみ袋に詰まったタンポンやコンドーム、鼻をかんだティッシュ、髪の毛のかたまり、バスルームのカビ……おぞましい細部が、メイドという過酷な仕事、人間の行い、両方を浮かび上がらせる。ステファニー自身も、裕福な「シェフの家」で鎮痛薬の大きなボトルを見つけ、思わずポケットに入れたい衝動に駆られたり(彼女は膝と肘の痛みを抱えている)、カシミアのカーディガンをうっとり羽織ってみたり。
メイドは、どこの家でも透明人間であることを要求されるが、そのじつ目撃者でもある。ステファニーは、書き綴ることによって自身を極限の窮地から救い出したが、と同時に、他者との生々しい遭遇によって持ち前の洞察や描写力に磨きをかけ、他者と自分との距離をあらたに設定し直してゆく。崖っぷちを歩く体験を綴る本書がどこか鮮烈でいきいきとしているのは、作家誕生という希望に読者が立ち合っているからだと思うのだ。
ミアに注ぐひたすらな愛情は、終始変わらない。「愛してる、私はあなたのためにここにいる」。何度となく唱える言葉の真実が伝わってくるから、壁にびっしり黒カビが生える部屋に住むことで娘の体調を悪化させる母ステファニーを責められないし、私たちは自分たちの物語として共有するのだ。
羞恥、戸惑い、後ろめたさ、恐怖、誇り。人間が生きてゆくときの困難と希望がみっしり詰まっている。ひとが前を向いて生きてゆくためのカンテラとして、右手に持ちたい一冊だ。
ALL REVIEWSをフォローする