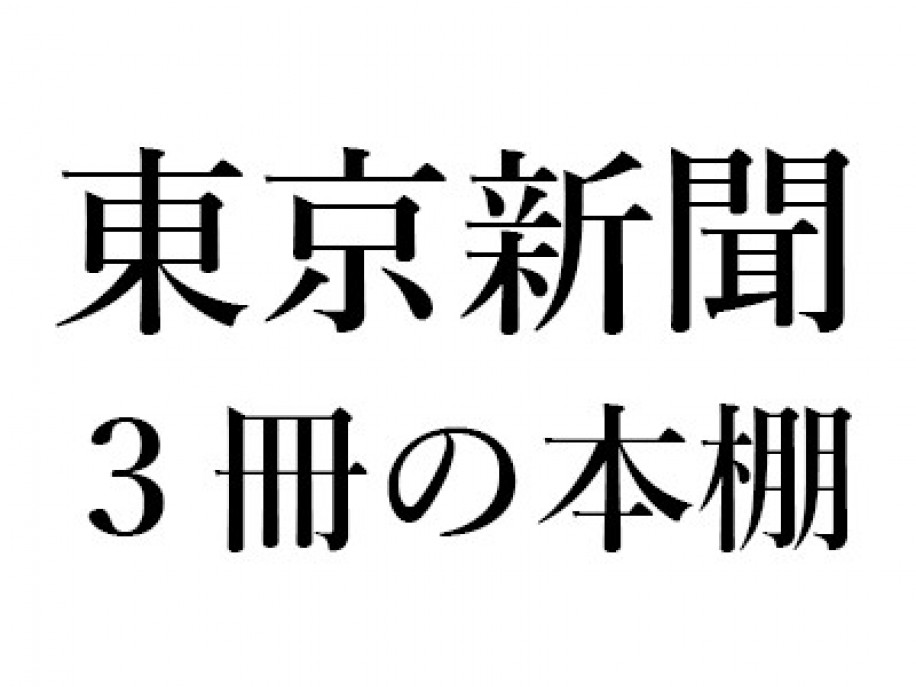書評
『日没』(岩波書店)
市民を味方につけて行う言論統制
主人公の女性作家マッツ夢井は、市民が国民と呼ばれるようになり、ネットニュースが「時の政権に阿(おもね)る書きっぷりに」なった時代に生きている。また作家の不可解な自殺や病死が増えている。そんなある日、総務省文化局・文化文芸倫理向上委員会から召喚状が届く。マッツの小説は犯罪を肯定するように書かれていると判断され、海辺の断崖にたつ療養所へ連行される。携帯電話もWi-Fiも通じない世間から隔離された収容所だ。
そこでは名前ではなく番号で呼ばれ、自作の問題点を直す指導を受ける。問題視されるのは「猥褻、不倫、暴力、差別、中傷、体制批判」と「反原発」らしい。
小説は、必ずしも正しいことばかり考えている訳ではない人間の愚かしさ、差別意識や狡さも含めて作家が責任を持って描く表現だが、そうした反論は通じない。抵抗したとされ、収容期間が延長される。知り合いの書き手に会っても、作家同士で話をすると「共謀罪が適用」され、会話はできない。
食事は量が少なく貧しいが、矯正された文章を書けば待遇が良くなるため、マッツは心身の飢餓から、所長の気に入る作文を書くようになる(この作中作も面白い)。ところが彼女は枕の中から遺書を見つける。かつて収容された作家が自殺前に遺した文書には、おぞましい事実が記されていた。
マッツは絶望と憤りから恭順したふりは止め、決然と立ち向かうが、ベッドに拘束されて身体の自由を奪われ、睡眠薬の点滴で眠らされ、さらに精神科医が脳の研究のために……。
本作は狭い収容所内での職員による理不尽な支配を描くが、背後あるのは国家による言論統制だ。ただし桐野作品らしいひねりがある。
「正しくない作家」は、国が選ぶのではない。読者が、総務省のホームページに、この文筆家は問題ありと告発するのだ。また収容所内では、転向した作家が職員となり、抑圧する側にまわる。版元も、読者が正しいことを書く作家を支持するため、書き手を選ぶようになっている。つまり国による弾圧という古典的な構図ではなく、市民を味方につけた言論統制という巧妙な仕掛けを著者は創り出している。
思えば近頃、人々が分断している。ネトウヨだパヨクだ、嫌韓だ反日だ、性差別だフェミだ、ヘイトだポリコレだ……。双方とも自説のみが正しいと信じ、相手を非難する。そんな不毛な対立を避けるために、日常会話やネットの言葉を曖昧にぼかす人がいる。こうした言葉の萎縮と市民の分断がある現実を生きている私は、架空の小説とは思えない恐怖と不安を覚えた。
本作は優れたディストピア文学にして戦慄のホラー小説、作家たちの謎めいた死の真相を明かすミステリー小説であり、そこにブラックユーモアと、この著者の魅力である不気味な夢や暗示的な幻想が渾然一体となっている。桐野文学の新たな傑作の誕生だ。
初出メディア
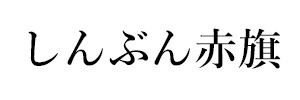
しんぶん赤旗 2020年11月16日
ALL REVIEWSをフォローする