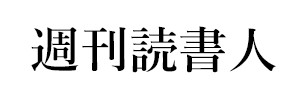自著解説
『建物が語る日本の歴史』(吉川弘文館)
建物の生きざまのその先に
洋の東西を問わず、建造物は権力を視覚化し、権力者の威光を示す装置でもあった。ことに前近代には建物の建設には労働力を挑発する権力、軍事的な安定性、財政基盤が求められたがゆえに、建物は富や権力の象徴として、その意味は大きかった。そのため歴史のなかで為政者によってさまざまな名建築が生み出されてきた。聖武天皇の東大寺大仏殿、藤原道長・頼道親子の法成寺・平等院鳳凰堂、足利義満の鹿苑寺金閣や相国寺七重塔。そして織田信長の安土城に豊臣秀吉の聚楽第・伏見城…。枚挙にいとまがない。同時に権力者に建物が政治的に利用されることも少なくなかった。中世の東大寺大仏殿を例にとると、平重衡により焼失した大仏殿は後白河法皇や源頼朝の援助で再興されたが、畿内に基盤のない頼朝にとって、大仏殿の再興は畿内で自身の権威を示す格好の場であったのである。
いっぽうで建物の破壊により、その権威性を打ち砕くこともあった。代表は織田信長の比叡山焼き討ち。もちろん軍事拠点としての延暦寺の破壊という意味もあったが、精神的な威圧・制圧の意味を含んでいた。建物が権威性を帯びていたからこそ、その破壊はメンツをつぶす行為で大きな意味を持ったのである。
もちろん建物は為政者だけのものではない。江戸時代に民衆が経済的に力を持ち始めると、芝居小屋・遊郭など、彼ら好みの建築も成熟した。また各地の観音巡礼は伊勢参りなどの参詣が民衆の娯楽として盛隆すると、寺社の建物も向拝(こうはい)を中心に彫刻や彩色を凝らして華やかにし、彼らの目を惹く装いになっていく。特に観音信仰の高まりから、西国三十三箇所・坂東三十三箇所・秩父三十四箇所を合わせた百観音巡礼が流行した。巡礼には費用も時間も多くかかるため、百観音を一つの建物に集め、巡礼のご利益が得られるお堂まで登場した。三匝堂(さざえ堂)の誕生である。この三匝堂はらせん階段で三層に登るという特殊な体験も加わって人気を博したのであるが、さしずめテーマパークの人気アトラクションであろうか。
さて拙著で触れた建物と社会のつながりのほんの一部をご紹介したが、建物の建設の背景にはさまざまな想いや葛藤があり、建物を通して見ると、新たな歴史が見えてくるのである。拙著をきっかけに各地の古い建物を訪れた際に、その背後にある歴史・社会・人に思いを巡らせてもらえたら幸いである。
[書き手] 海野 聡(うんの さとし・東京大学大学院工学系研究科建築学専攻准教授)
ALL REVIEWSをフォローする