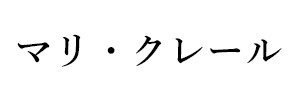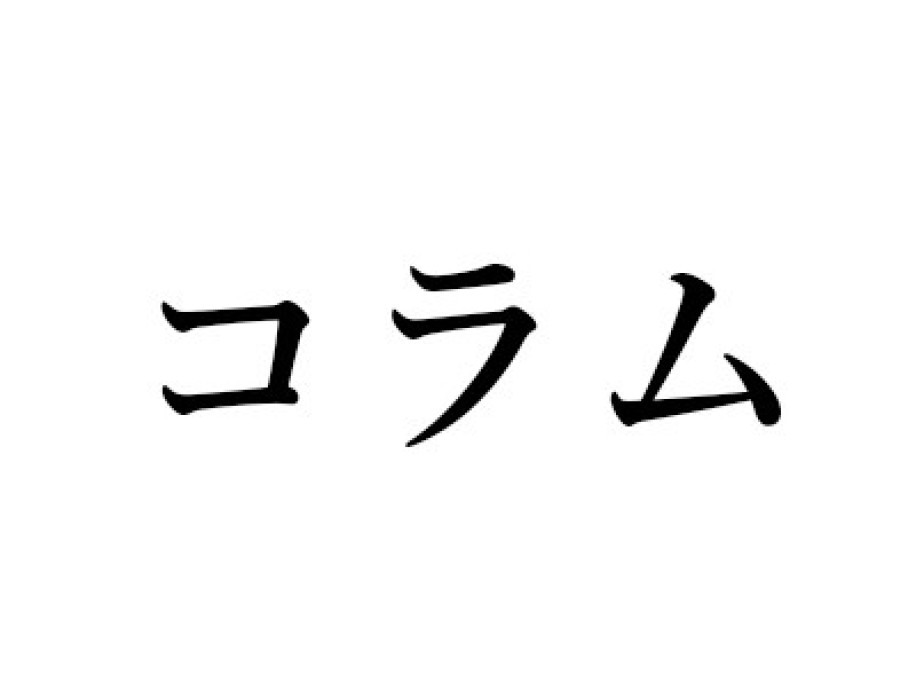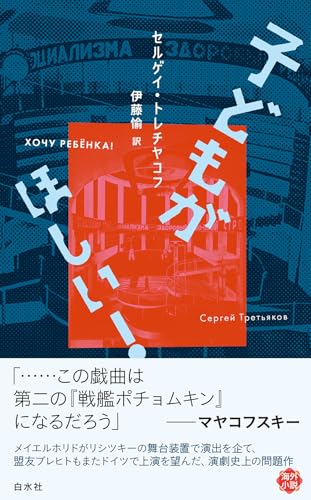書評
『フロイト〈シナリオ〉』(人文書院)
「情緒論粗描」(一九三九年)以来のサルトルの絶えざる精神分析批判を知る者なら、その彼がフロイトを主人公とする映画シナリオを書いていたという事実には誰しも心を奪われざるをえまい。一九五八年にジョン・ヒューストンの求めに応じて書かれたこのシナリオは、二十九歳の一講師フロイトがいったんは催眠療法に惹かれながら、結局それから離れ、開業医として独自の精神分析学を創造してゆく苦しみの時代をまことに鮮やかに描き出している。サルトルはヒューストンの書き直しの要求に対して、求められたように短かくするどころかさらに加筆したらしいが、今回訳出されたのは手直し前の第一稿である。見事な日本語に移し替えた訳者の労を、まず多としたいと思う。
序文でJ ― B・ポンタリスも指摘しているとおり、ここに扱われた伝記的事実は、確かにおおむねアーネスト・ジョーンズの『フロイトの生涯』(紀伊國屋書店)に依拠しているといえるだろう。師マイネルトとの確執と訣別、シャルコの催眠術実験への関心とその超克、ブロイアーや、とりわけフリースとの特異な友情、父ヤーコプ、妻マルタ、さらには幾人かの女性ヒステリー患者との関係がドラマとして巧みに織りなされているが、そのかぎりではそこには何ら新しい事実は付加されていない。しかしこのシナリオのおもしろさはむしろ別のところにあるので、たとえば、フロイト自身が一人の神経症患者たることを暗示するかのように、こんなト書きが挿入されるのだ。
戯曲家としてのサルトルの才能にあらためて感心せざるをえないが、実際、これはなんと生彩に富んだフロイト論たりえていることだろう。
サルトルは『存在と無』の末尾近くで精神分析と対比的にみずからの「実存的精神分析」の企図について語りながら、いみじくもこう書いている。「この実存的精神分析の分野においては、いまだフロイトに当る人がいない」と。『ボードレール』に始まり『聖ジュネ』を経てフローベール論『家の馬鹿息子』へといたる仕事で、まさしくみずから一個のフロイトたることを示しえたサルトルにしてみれば、フロイトに対する実存的精神分析ほど心を唆るものはあるいはなかったにちがいない。実存的精神分析を行なう者は、「自分の考察する個別的な場合に即応して、そのつど、一つの象徴解釈を再発明しなければならない」とすれば、これは個々の人間へのいわば全面的共感にもとづく「根源的選択」をそのつど生き直すことにほかならないだろう。その意味でこのシナリオは、サルトルの実存的精神分析の系列のいわば番外篇として位置づけられるといえるかもしれない。
本書を読めば、人はフロイトを多少とも好きにならざるをえまい。いや、それにも増して、私などはやはりどうしてもサルトルを嫌いになれないのである。
【この書評が収録されている書籍】
序文でJ ― B・ポンタリスも指摘しているとおり、ここに扱われた伝記的事実は、確かにおおむねアーネスト・ジョーンズの『フロイトの生涯』(紀伊國屋書店)に依拠しているといえるだろう。師マイネルトとの確執と訣別、シャルコの催眠術実験への関心とその超克、ブロイアーや、とりわけフリースとの特異な友情、父ヤーコプ、妻マルタ、さらには幾人かの女性ヒステリー患者との関係がドラマとして巧みに織りなされているが、そのかぎりではそこには何ら新しい事実は付加されていない。しかしこのシナリオのおもしろさはむしろ別のところにあるので、たとえば、フロイト自身が一人の神経症患者たることを暗示するかのように、こんなト書きが挿入されるのだ。
フロイトは熱心に耳を傾け、自分の鼻に人差指を突っ込むことさえ忘れている。
フロイトは驚いたようにしかめ面をする。そしてあわてて鼻孔から人差指を抜く。
戯曲家としてのサルトルの才能にあらためて感心せざるをえないが、実際、これはなんと生彩に富んだフロイト論たりえていることだろう。
サルトルは『存在と無』の末尾近くで精神分析と対比的にみずからの「実存的精神分析」の企図について語りながら、いみじくもこう書いている。「この実存的精神分析の分野においては、いまだフロイトに当る人がいない」と。『ボードレール』に始まり『聖ジュネ』を経てフローベール論『家の馬鹿息子』へといたる仕事で、まさしくみずから一個のフロイトたることを示しえたサルトルにしてみれば、フロイトに対する実存的精神分析ほど心を唆るものはあるいはなかったにちがいない。実存的精神分析を行なう者は、「自分の考察する個別的な場合に即応して、そのつど、一つの象徴解釈を再発明しなければならない」とすれば、これは個々の人間へのいわば全面的共感にもとづく「根源的選択」をそのつど生き直すことにほかならないだろう。その意味でこのシナリオは、サルトルの実存的精神分析の系列のいわば番外篇として位置づけられるといえるかもしれない。
本書を読めば、人はフロイトを多少とも好きにならざるをえまい。いや、それにも増して、私などはやはりどうしてもサルトルを嫌いになれないのである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする