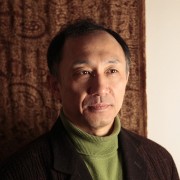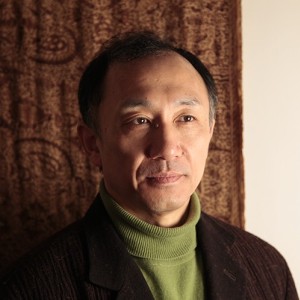書評
『水都 東京 ――地形と歴史で読みとく下町・山の手・郊外』(筑摩書房)
水循環都市をとらえ直す
チェーン店の看板がケバケバしく、地域に潤いをもたらす屋敷森が突如マンションになり、プレハブ住宅が続く。評者は街並みの特徴を失ったそんな東京の景観を嘆いてきたが、1985年に出版された陣内秀信『東京の空間人類学』(筑摩書房)には虚を突かれた。陣内氏は建築史家であるというのに、また地元で名団地が跡形もなく取り壊されるについては議会で断固反対の論陣を張ったのに、眼前にある建築物を評するトーンはむしろ抑えている。古地図を片手に「場所の特徴」を書き出すに当たり、建物よりも植生、湧水とつながる聖域や水路・道のネットワーク、敷地割りをたどり、地形から東京の「都市を読み解く」のだ。なるほど古い建物が織りなす景観が失われても、地形という「基層」は消えない。
しかもその東京像がふるっている。昭和になって鉄道や自動車が生み出した銀座や新宿、郊外のニュータウンといった「陸」には焦点を当てない。山手線の内側であっても江戸城ないし皇居の海側や下町は、河川や掘割が網目をなし舟が行き交う、ヴェネツィアに似た「水の都市」だというのだ。
言われてみれば神戸にせよ開港から大正時代まで、大型船は沖合に停泊、荷は艀(はしけ)が受け取って陸揚げした。海底を深掘りした港がなかったからだ。東京湾ではさらに、佃島沖で荷を受け取った艀は近くの岸でなく、河川や人工の掘割に入り込んでいく。日本橋川周辺に倉がずらりと並んでいたのはそこが物流拠点だったからだし、飯田橋のように川沿いに鉄道駅が設置されたのも、艀から荷を貨車に移したからだ。鮮やかな分析に、『東京の空間人類学』は都市論の基本書に指定されるのみならず、街歩きの手引きともみなされた。
それから35年。この続編の刊行に長い時間がかかったのには訳がある。高度成長期に舟運が役割を終え、東部の倉庫群は取り残された。宅地開発は西の郊外へと向かった。80年代後半に出現した「水の都市」論は、沸き立つウォーターフロント開発で不動産広告に引用されるほど注目を浴びた。ところがバブル崩壊とともに東京ベイエリアの開発熱は冷え切った。
その後、潮流は逆転した。都心回帰が始まり、閑散としていた清澄白河辺りの倉庫はお洒落なカフェやギャラリーにリノベーションされている。地形への関心は、タモリのテレビ番組「ブラタモリ」や中沢新一の『アースダイバー』(講談社、2005年)で再点火した。世論が追いついた今であれば、「過去の経験を掘り起こし、価値ある歴史の層を尊重しながら新たな開発を重ね」よという真意は正確に伝わるはずだ。
本書の前半は前著の増補版。そこに山手線外を考察する後半が加わる。西の武蔵野台地では崖線(がいせん)や谷頭(こくとう)からの湧水が井の頭池、神田川や玉川上水の水源となり、山手線内に流れ込むとして、東京を壮大な「水循環都市」として三次元的に描き出す。
19世紀初頭に鍬形蕙斎(くわがたけいさい)が隅田川東の高台から富士山を望んだ江戸鳥瞰(ちょうかん)図のアングルが、東京スカイツリーからのそれと同じという指摘には興奮した。まとまりある街並みは、上空からの鳥瞰図が共有されてこそ成り立つ。熟成の時を経て戻ってきた名著である。
ALL REVIEWSをフォローする