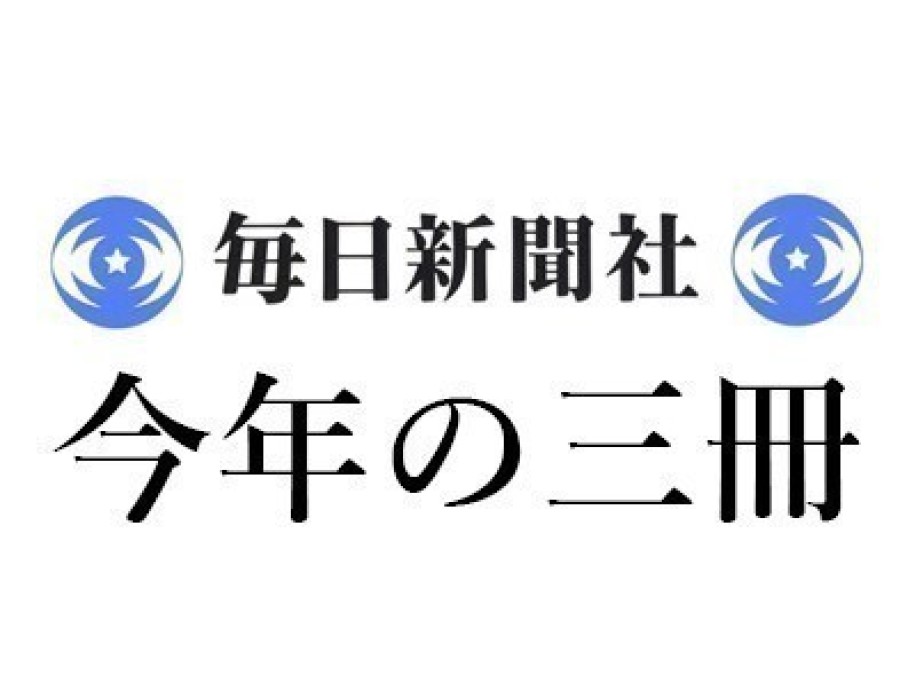書評
『雉猫心中』(新潮社)
隠された毒、つねに蠢いている何か
男の名前は晩鳥陸朗といい、女の名前は大貫知子という。男には妻と娘が、女には夫がいる。東京のはずれの、畑やら雑木林やらがたっぷり残った「のどかでのんびりした」町で、二人は出会う。というより物語そのものが、ほとんどこの町のなかでだけ進行する。二人が住んでいるのも、大胆かつ淫靡(いんび)に互いを貪(むさぼ)るのもその町だし、男の妻の仕事場も、娘の通う学校も、女の夫の勤め先もその町にある。家庭のある者同士の恋愛――あるいは性愛――を描いた小説はたくさんある。たくさんあるが、こんなにこわいものは滅多にない。こんなにふしぎなあかるさをたたえたものも。これは官能的な小説というよりも、官能そのものが描かれためずらしい小説だ。
この小説を読んで、ああ、私もこんな恋愛がしてみたい、と思う人は、おそらく一人もいないだろう。それだけで、これがやわな小説ではないことがわかろうというものだけれど、なにしろこれは、「しかたがない」と思ってしまう女と、「どうでもいい」と思っている男の物語なのであり、恋愛に伴う歓喜――世界が突然色つきになるような――の描写は一切ないし、惹(ひ)かれ合う者同士の愚かしくも喜ばしい献身や、そのためにいや増す陶酔、幸福感、といった甘やかな描写も一切ない。飢餓感は、ある。寂寥(せきりょう)感も。そしてひそかな、名づけようのない共鳴のようなものも。
二人はひたすら身体を重ねる。男の家で、女の家で、さらにびっくりするような場所でも。男も女も、それを愛とか恋とかいうふうには呼んでいない。でも、それでは単純に肉体だけのことかといえば、無論そんな芸当は、人間にできるはずもないのだ。そこにあるのは――そして著者が細心の注意を払い、生々しく浮き彫りにするのは――感情である。感情というのが、たぶん唯一この小説を歪(ゆが)めない、というか汚さない、言葉だろうと私は思う。人体における血液みたいに、この小説には感情が流れている。どの頁(ページ)にもそれが脈打ち、蠢(うごめ)き、切れば溢(あふ)れてそこらじゅうを濡(ぬ)らす。
二部構成になっていて、第一部の語り手が女、第二部の語り手が男であるために、ただでさえ複雑な感情の脈動は、より複雑に、重層的になる。というのも、そこには二人以外の登場人物たちの感情も、際限なくと思われるほど緊密に、はりめぐらされているからだ。おなじ出来事が男女両側から語られ、だから読者はおなじ出来事に二度立ち合い、愕然(がくぜん)とする。その温度差に、見える景色の違いに。
それにしてもこわい小説だ。いたるところに毒が隠されている。たとえば物語の最初の方で、女は、自分がこっそり餌づけした猫が、庭にやってきてガラス戸にその影が映るのを心待ちにする。実際に猫が来ても気づかない夫を見て、「猫の影は、猫を待っている人間にしか、そのかたちに見えないのだろう」と思ったりする。こわく、ないだろうか。そのしばらくあとに今度は夫が、「いいんだよ、餌をやったって。家に入れなければ」と言ったりするのだから、ホラーそこのけだ。
ホラーといえば、小副川さんという人物がでてくる。「ハンサムな老人だ。若者が着るようなカーキ色のフリースのパーカに、スラックスという恰好(かっこう)だったが、着物を着せたら、歌舞伎役者のように見えるだろう」と描写される町内会長で、言葉つきも人当りもやわらかい。凡庸な作家なら好々爺(こうこうや)、不穏な不倫劇における一服の清涼剤、的な役をわりふりそうな人物だけれど、この人のこわさは尋常じゃなく、私はずっと、この人がもうでてこないことを祈りながら読んだ(でもでてくる)。
この町の中学生たちもこわい。不良たちだけじゃなく、「ブルーグレイのブレザー」を着て、「ブルーグレイの不吉な靄(もや)」みたいに見える、ただ歩いているだけの子たちも。女の隣に住む「大西夫人」も、今度この町に住もうかと考えている、と話しかけてくる女もこわい。わき役のわき役(たとえばドーナツ屋の店員)までこわくなったときにはもうあとの祭で、すっかり井上荒野の術中にはまっていた。つまり、誰もじっとしていないのだ。穏やかな表面とはうらはらに、つねに何かが蠢いている。
この人の小説の強みの一つに、説明が徹底的に排除されているために、まるで映画を観(み)たあとのようにくっきりと、場面場面がそのまま残るということがある。感銘を受けたとか受けないとかではなく、ただ見てしまったものとして、それは読者の記憶に残る。選べないのだ。
さっき私は、ここには恋愛の歓喜の描写がないと書いた。それなのに(と言うべきか、だからこそ、と言うべきかは迷うところだけれど)、物語の終盤、男性の語りによる数十頁が美しい。歓喜とか献身とか陶酔とか幸福感とか、彼らがひたらなかった甘やかなあれこれを、全部合わせたより美しい。これから読む人の興をそぐのでくわしくは言えないが、私は茫然(ぼうぜん)とした。
ALL REVIEWSをフォローする