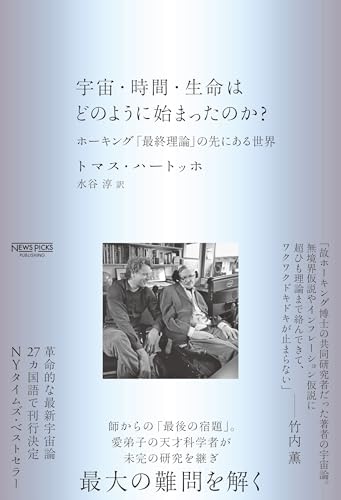書評
『Life Changing:ヒトが生命進化を加速する』(化学同人)
家畜を通して生きる選択肢検証
猛暑と豪雨の中で、新型コロナウイルスの感染拡大が続き、自然との向き合い方の再考が必要と思わざるを得ない。人間は、生物でありながら、生態系の枠をはずれた生き方をしている唯一の種である。それが人間の特徴ではあるが、その生き方にはさまざまな選択があるはずだ。本書は、家畜を通しての生き方検討の試みである。家畜化などで動物を人為的に変化させてきた歴史と現状の具体例が豊富に示される。始まりは、3・5万年前のオオカミからイヌへの移行だ。ヒトがオオカミを選んだのか、その反対なのかは分からないが、イヌが今も人間の友だちであり、家畜誕生のきっかけになったことは確かだ。
家畜の人懐っこさは身体・行動の発達の不完全さと連動しており、構造決定に関わる神経堤細胞の移動の不足など脳機能関連遺伝子の変化によるとわかるなど家畜化にも科学が入り込んでいる。
近年、経済効果の大きい性質をもつ個体の精子を用いた人工授精は日常化している。最近ホルスタインでの特定品種で流産が多いのはDNAの一塩基変異によることがわかった。家畜としての選択が遺伝子の欠陥を拡散させていたのだ。「短期的な生産性を優先し、品種の長期的な健康と持続可能性をないがしろにしてきた」という指摘は、家畜を生きものとして見る必要性を示している。
「世界に700億頭いる家畜の3分の2は工業的畜産によって飼育されており」その典型はニワトリだ。体重は60年前の4~5倍、成長速度は5倍であり筋肉が増えた分心臓や肺は縮小した。遺伝子操作で形質転換した結果成長が速く大型化するサケは、米国ではFDA(食品医薬品局)が安全性を保証し市場に出ている。このような例は今後急速に増えるだろう。
ゲノム編集やクローン作成も日常化している。ポロ競技の選手がウマのクローン作製会社を立ち上げ、フィールドをクローンが駆け回っているという。バーブラ・ストライサンドが愛犬のクローンを作ったことを本書で知った。企業がすでに100頭以上のクローンイヌを誕生させている。ただし、誕生の成功率は4%以下であり背後に多くの死があること、健康上の問題も少なくないこと、クローンはまったく同じ性質をもつとは限らないことなどから、これには著者も疑問を呈している。この流れは、ヒトのクローンづくりにつながる可能性もあり、ここでの抑止は重要である。
一方、異常気象によって、北米のヒグマ(グリズリー)がホッキョクグマと出会い交雑種の誕生がみられた。家畜ではないし、この結果の先行きは不明だが、間接的に人間の生き方が関わる変化として心にとどめておきたい。
今後を考えるにあたり、英国のサセックスで赤字危機を救うために「農場をゆっくりと自然に明け渡す手続きを開始した」例を見よう。20年間でトウモロコシの単一耕作農場は野生生物が自由に行き交い、丈夫な品種のブタやウシが草を食(は)む場になった。土壌からの駆除剤の除去から始めたのだが、今は自然の作用が回り始めている。手つかずの自然などないが、ヒトは自然界から切り離された存在ではないことも確かなのだ。
ALL REVIEWSをフォローする