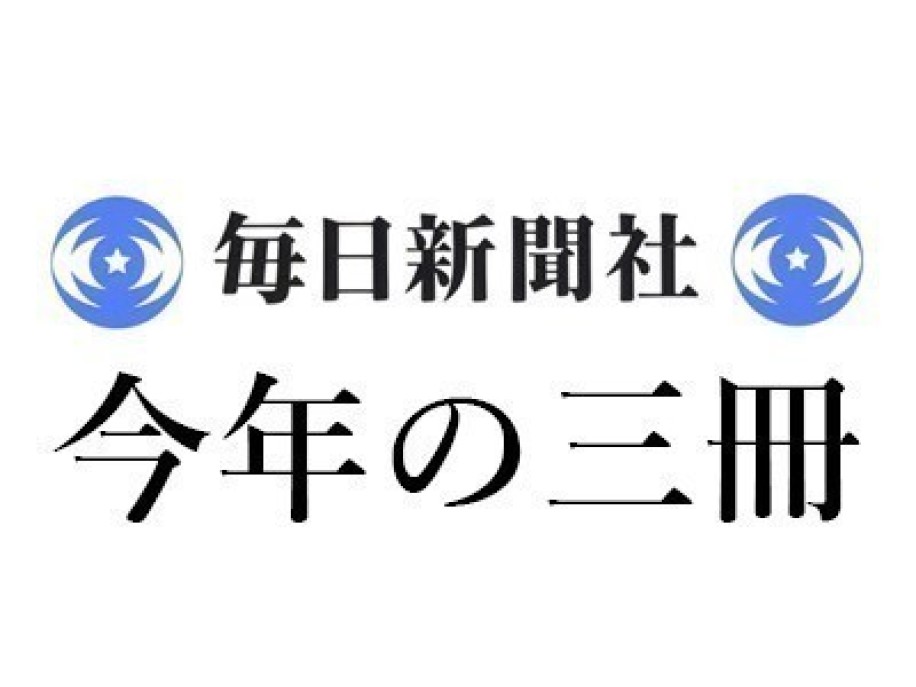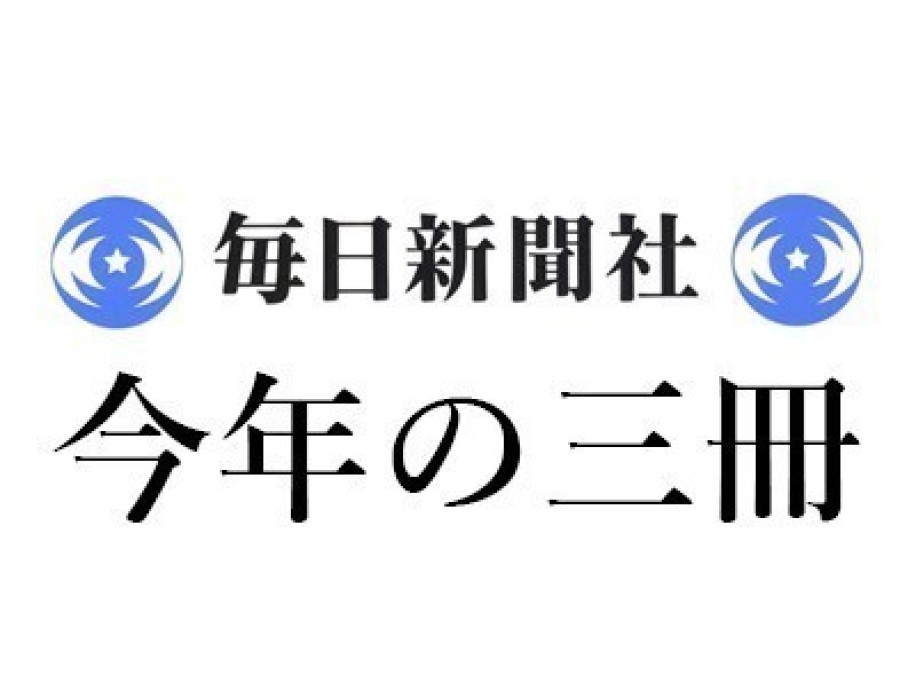書評
『日本の食文化史――旧石器時代から現代まで』(岩波書店)
食材も作法も、驚きの変化たどる
日本列島では旧石器時代から現代まで、何がどのように食べられてきたか。いまでは海外でも人気の高い日本食。本書はその変遷を辿(たど)り、見渡す通史。一般的に歴史学で採用される時代区分とは異なる、著者独自の巨視的な区分方法によって描き出される。「王朝や政府の制度が変わったからといって、民衆の食事の慣習がすぐに変化するわけではない」からだ。狩猟採集の時代から稲作社会の成立へ。古代から中世の終わりに近い時期までを、本書では「日本的食文化の形成期」とする。肉食のタブーと仏教・神道の関係、牛乳を飲まないことなど、多様な視点から食文化の特徴が説かれる。中世には鍋・釜が普及して温かい料理が増えたことや、一日二食だった食事が一七世紀末までに全国的に三食化したことなど、驚くような変化への言及が随所に織りこまれていて興味は尽きない。
発酵食品のナレズシがかたちを変えて江戸時代には握りズシとなる。保存食品から出発してファストフードに変化したのだ。「それでも、スシ飯には酢を加えて、かならず酸味をつけることに、古代からの伝統がかろうじて残存している」。二〇世紀の日本人の食事の変化については「外来の要素をうけいれて日本的に変形することによって、伝統的な食事を再編成していった」と指摘される。
歴史を辿る第一部に続く第二部では、食卓・食事作法・台所用品などが取り上げられる。たとえば、二〇世紀初頭に普及しはじめたチャブ台だが、一九七〇年代ごろにはイスとテーブルの方が優勢となったことなどは、社会の変化を映し出す例だ。
いまの人々は「かつては祭のときにしか食べられなかったような、さまざまな料理を日常的に食べている」。私たちは摂取するもので出来ている。当然だが、不可思議でもある事実。親しみやすい記述による、食文化の入門書だ。
朝日新聞 2016年1月24日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする