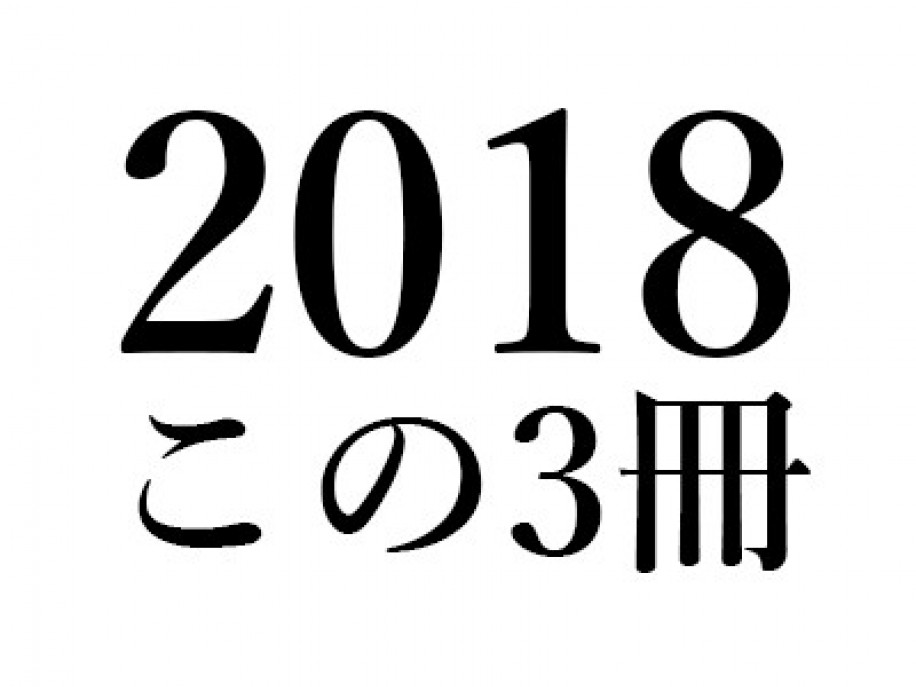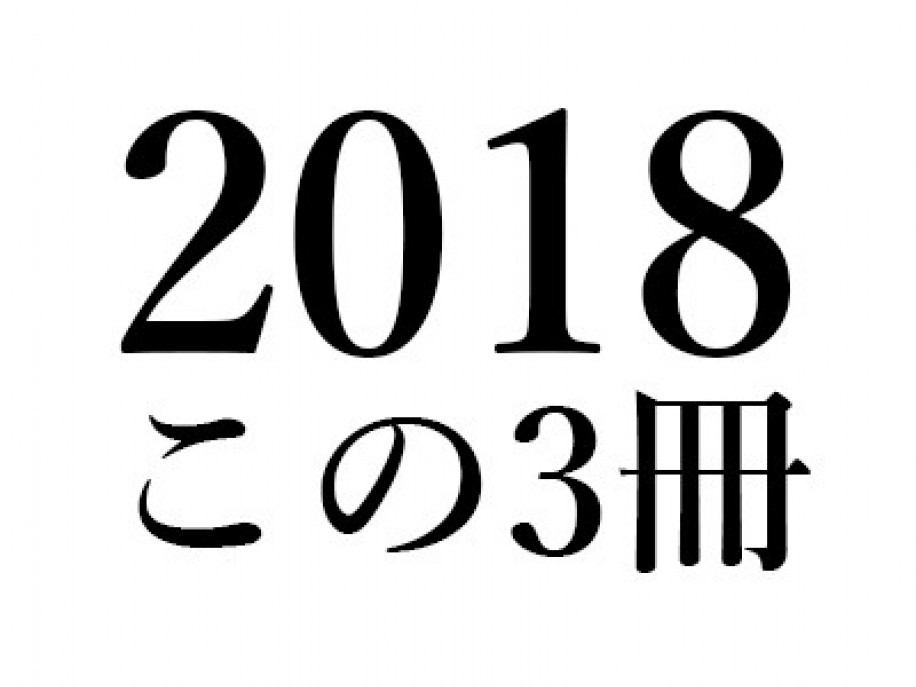書評
『出生の秘密』(講談社)
分析と統合の力業で日本近代文学を解読
出生の秘密。一見使い古された言葉である。だが、三浦雅士がこの言葉にあたえた射程は恐ろしく遠大だ。これは日本近代文学の解読から人間誕生の瞬間にまでさかのぼる、気が遠くなるような分析と統合の力業なのである。幼年期は人間形成に決定的な力をもつ。このことはもはや常識だ。しかし、人間は生まれて数年の最も重要な時期の記憶を喪失している。いちばん大事なことは本人の目には隠されているのだ。エディプスの神話が古来あれほど人を魅了してきたのは、彼の出生の秘密が隠されていたからなのである。
ここから三浦氏は、出生の秘密に憑かれた作家と作品を次々に尋問の場に召喚する。
まずは丸谷才一の『樹影譚』。樹の影に異様な愛着を抱く小説家が、ある老婆に招かれ、そこで自分の出生の秘密を聞かされるという短篇だ。その結末で、主人公は「七十何歳の小説家から二歳半の子供に」、さらには「未生以前へ、激しくさかのぼつてゆく」ように感じる。どうして出生の秘密にそんな奇跡のような力があるのか? これが本書の根本的な問いとなる。
次いで国木田独歩の『運命論者』。この小説で実の妹と結婚する男の悲劇を描いた独歩は、最初の妻の妊娠も娘の誕生も知らなかった。彼の娘は、妻の母の娘として入籍されていたのだ。『運命論者』の裏に隠れた出生の秘密である。
また志賀直哉の『暗夜行路』。周知のとおり、作者自身が投影された主人公・謙作は父の子ではなく、祖父が母と通じて作った子供だった。
さらに中島敦の『北方行』。母を知らぬ伝吉という主人公を造形した作者もまた、生みの母を知らなかった。そして、自分が自分であることに必然性などないと気づき、世界がばらばらになって意味を失うという病的な自己意識に苛(さいな)まれる小説を書いた。出生の秘密を抱えた人間は自己意識が過敏になる。いや、鋭敏すぎる自己意識が出生の秘密を引きよせるのだ、と三浦氏はいう。出生の秘密とは、自己意識の発生を映しだす鏡なのだ。ヘーゲル流にいえば、自己意識の誕生とは人間の誕生にほかならない。ここが本書の眼目となる。
そして、発狂した実母のほか養母と伯母と義母、計四人の母をもった芥川龍之介と、生後まもなく里子に出され、実家に戻ったのも束の間、ふたたび養子に出された夏目漱石。この二人の小説と生涯の分析は本書のまさに白眉であり、今後、近代日本文学の研究者は『出生の秘密』の論点を避けて通ることはできないだろう。
かくして、出生の秘密という自己意識のドラマを経めぐったのち、著者は、自己意識と他者の葛藤を人間精神の起源においたヘーゲルへと到達する。そして、ラカンの精神分析も、パースの記号論も、ルソーの孤独も、この自己意識のドラマとして解読するのである。それだけではない。ここから、食と性の儀式、共同体、国家、宗教の起源まで明らかにしてしまう。冒頭で「気が遠くなるような分析と統合の力業」だといった理由がお分かりいただけるだろう。
朝日新聞 2005年10月2日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする