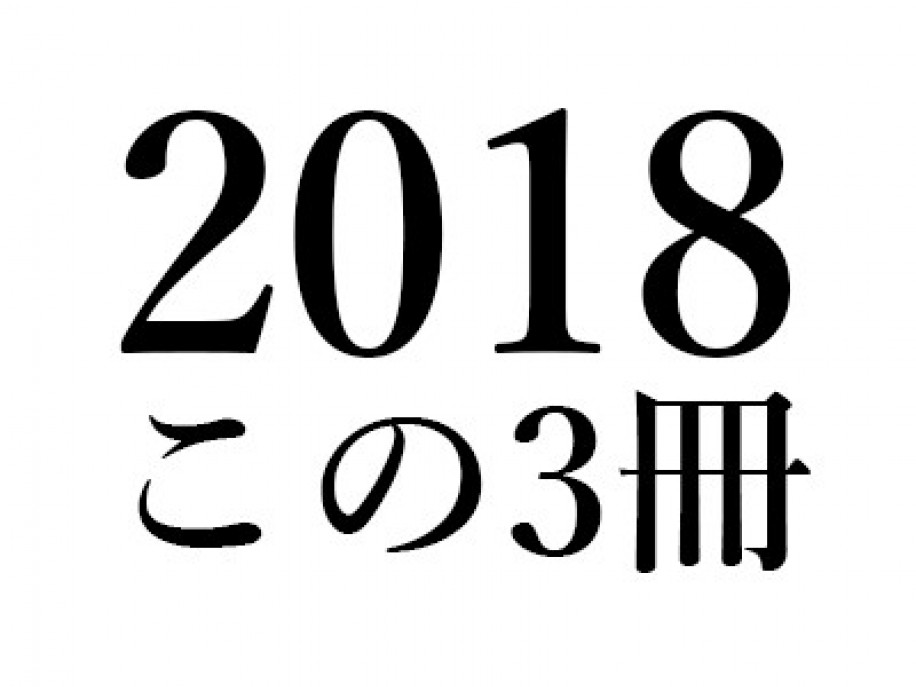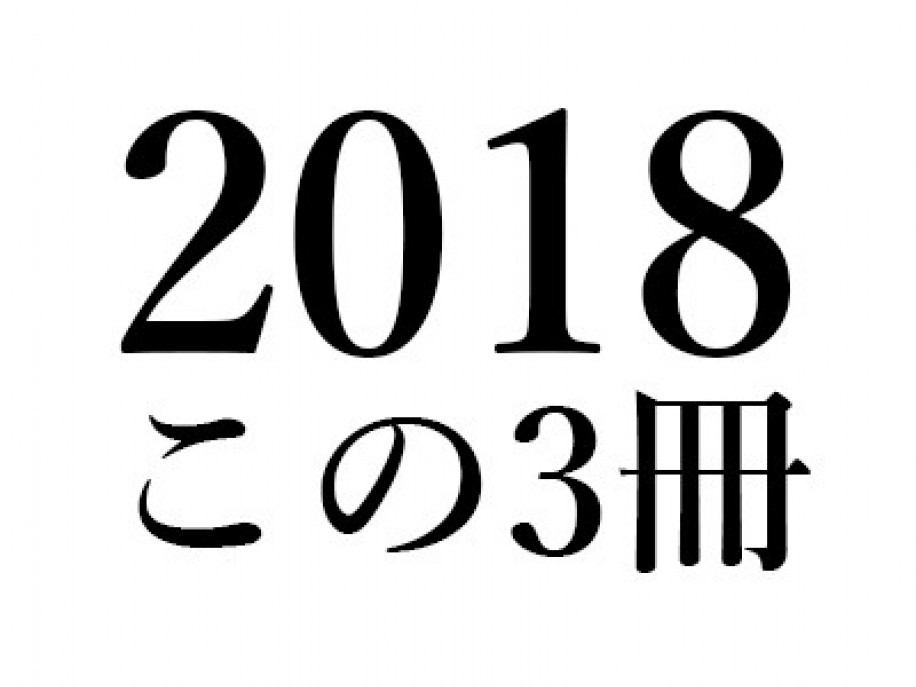書評
『石坂洋次郎の逆襲』(講談社)
郷土愛の響きあい 情熱的な作家論
石坂洋次郎は存命中に流行作家と見なされ、いまはすっかり過去の人となった。しかし、著者の見解はまったく違う。石坂は作家としてもその作品も不当に低く評価され、いまだからこそ、その魅力を見直すべきだと言う。なぜなら、石坂は東北日本の深層に潜む母系制の神話を鮮やかに捉えており、時代を超えた独特の個性を描き出しているからだ。石坂洋次郎の小説に出てくる女性はほとんど例外なく経済的に独立し、恋愛においても婚姻においても家庭において主導権を握っている。このような人物造形は戦前戦後を問わず一貫しており、父系制の神話と真っ向から相対している。女性支配の世界は無意識ながら、戦前においては軍部と対決するものになり、戦後においては近代工業社会に対する批判になっている。石坂の小説が戦前においても戦後においても大人気を博したのはそのためである。
石坂の文学と民俗学とのあいだに決定的な呼応関係があるという仮説は、作家論の展開において中心的な柱になっている。石坂は折口信夫の影響を受けたが、折口が表向きに隠していたことをあからさまにしただけでなく、それを血肉化することに成功した。宮本常一の民俗学も網野善彦の歴史学も石坂の影響を受けたもので、二人が登場しうる場を切り拓いたのも石坂だと指摘する。津軽の風土の中で育ち、母系制のなごりを日常として生きる経験を持つ者でないと、気付かない発見であろう。
むろん、石坂文学の真の価値は情念の煌(きら)めきを巧みに捉える表現力と、社会的共振を引き起こす発信力にある。そのことは同時代作家との比較を通して炙り出されている。
同じ戦前の流行作家でも、吉川英治と山本周五郎は父系制に少しの疑いも持っていない。二人とも男性原理の大義に殉ずる女性を描いたが、石坂は大義そのものを疑い、女性の視点に立って大義の欺瞞を暴き出してしまった。
戦後の作家として対比されたのは獅子文六である。二人とも、五十、六十年代において、小説が映画化され、主題歌や作中人物のセリフが流行した。文学に止まらず、同時代の社会現象にもなっていた。しかし、獅子には伝統的価値観に対する配慮があるのに対し、石坂の場合、社会制度を根底から突き崩しかねない革新性がある。女性を主人公に据えても、獅子の場合、物語の結末はつねに父権制の勝利として訪れるが、石坂は女性の主体的な意志だけを重視し、父権制の論理は初めから蹴飛ばされている。同時代の作家との比較を通して、石坂文学の音域の広さが示されているだけでなく、近代文学史を捉え直す手がかりも示唆されている。
今日の社会問題を考えるとき、石坂の再評価は特別な意味がある。家族の空洞化、家庭内暴力などに象徴されるように、現代社会は家族崩壊という大問題を抱えている。家族形態の激変に直面している現在、石坂の文学にはエマニュエル・トッドの家族論を推し進める力があり、その作品が示唆したのは未来においてありうる家族のあり方なのかもしれない。三浦の解読は文学的想像力の垣根の外にもこぼれだして面白い。
石坂も三浦も弘前の出身で、二人のあいだに強烈な郷土愛と、東北の地に生まれ育った人しか持ちえない原体験と感性の響きあいがあった。ただ、文学的な直観は決して初期値に止まることはない。石坂の読み直しは、輪郭の明晰な語り、解像度の高い分析と、燦爛(さんらん)たる詞藻によって情熱的な作家論になっているだけでなく、著者の熱い思いがこめられた郷土賛歌にもなっている。
ALL REVIEWSをフォローする