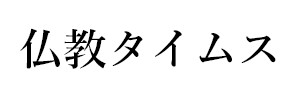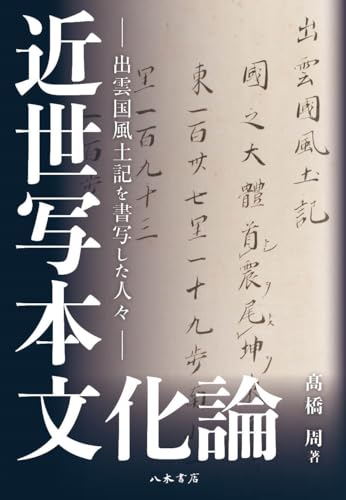書評
『文覚』(吉川弘文館)
怪僧「文覚」 その等身大の姿に迫る
数々の荒行を完遂し獲得した、飛ぶ鳥をも祈り落とす験力。空海ゆかりの名刹・神護寺の復興を発願し、後白河院(ごしらかわいん)に荘園の寄進を強訴する胆力。伊豆の流人だった源頼朝(よりとも)に平家打倒を持ちかけ、挙兵にいたらせた実行力――。『平家物語』が語る魁偉な文覚(もんがく)像は、中世という新時代の扉を開いた怪僧の活躍を伝えて余すところがない。一方で、『平家物語』の鮮やかな文飾を離れ、それ以外の歴史史料から立ち上ってくる人間・文覚の実像はどうか。著者はそこに「熱烈な大師信仰に由来する真摯な真言の行人」の姿を見、鎮護国家の理想を実現しようとした、飽くなき宗教的使命感を看取する。
その生涯は、常に波乱に富んでいる。鳥羽院皇女・上西門院(じょうさいもんいん)に仕える武士から、「文覚」を自称し修験の道に進んだ前半生。後白河院と将軍・頼朝を外護者とし、思うがままに仏法興隆を成し遂げていった絶頂期。そして一転、後鳥羽院(ごとばいん)との対立から流罪に処せられ、非業の最期を迎える最晩年・・・。「盛」と「衰」の強烈なコントラストから、文覚が生きた鎌倉時代初期の実相が浮かび上がる。
最終章では、文覚が34歳年下の弟子・明恵(みょうえ)に示した敬愛の態度から、「純真な修行僧を畏敬する敬虔な宗教人」像を抽出する。併せて、明恵の眼から見た文覚像にも言及し、この師弟間に終生存した葛藤に肉薄する。
平家の滅亡から鎌倉幕府の草創に深く関わった傑僧・文覚。希代の荒法師の一生を彩った栄華とその儚さも、「諸行無常」が紡ぎ出す中世ロマンに満ちている。
[書き手] 山崎一昭(新聞記者)
ALL REVIEWSをフォローする