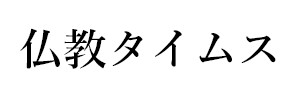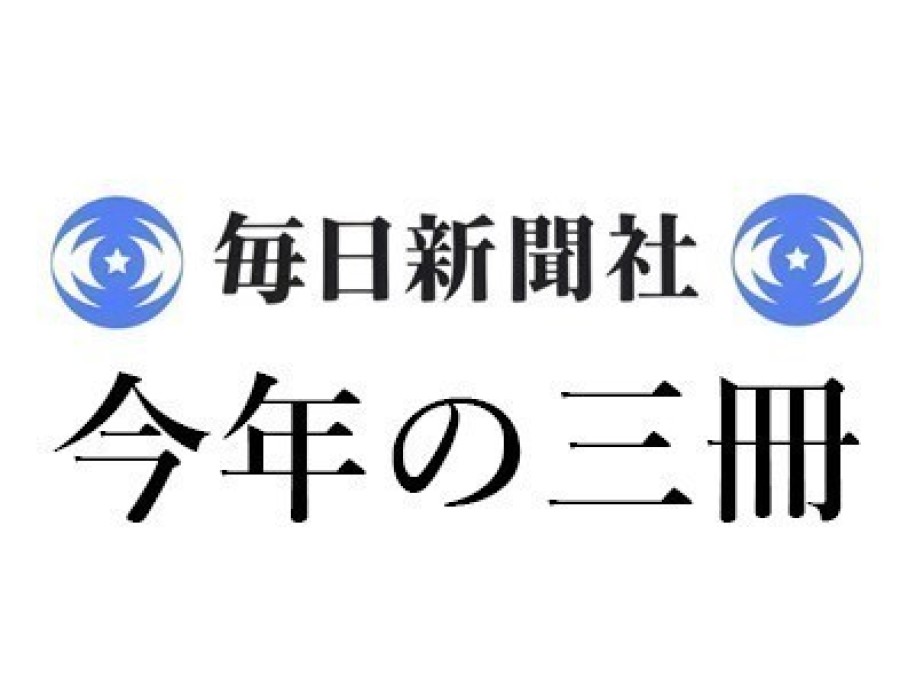書評
『熊谷直実: 中世武士の生き方』(吉川弘文館)
中世武士のリアリティ
源平合戦を描いた『平家物語』に雄々しく登場し、歌舞伎など伝統芸能の世界でも独特の存在感を放つ東国武士・熊谷直実。一の谷の合戦で若き平家の公達を討ち取ったことから無常を感じ、法然門下の僧となった直実の激動の生涯は、中世から現代に至るまで人々の心をとらえて離さない。しかし直実の強烈な個性とは裏腹に、平安末から鎌倉初期という時代の転換期を生きた中世武士の実像は中々見えてこない。本書は一人の新興武士を通して、中世武士のリアリティを明らかにしようとするものである。
本領である武蔵国大里郡熊谷郷の支配もままならなかった小武士・直実が、源頼朝から本領を安堵され、「御家人」という新たな武士身分を与えられる。だが鎌倉殿(頼朝)の前では平等という「傍輩の論理」の陰で、成り上がった小武士を弾き出そうとする豪族武士出身の有力御家人の思惑を感じ取ってしまう―。
弱小勢力に過ぎず、そこから這い上がろうと奮闘する直実の葛藤は、多くの現代人が共感できるに違いない。中世と現代の世相は通底しているのかもしれない。
直実はなぜ僧になったのか。自分の息子と同年齢の平敦盛を討ったことが出家の理由なのか。直実自身が書いた文書数通には、「自身の発心の経緯にかかわる述懐もみられるが、実は敦盛という特定個人の供養に繋がるような表現はまったくみられない」という。「むしろ武士として犯してきた数々の殺生が、彼のような勇猛な戦士の心をも苛んできたと考えた方がよいだろう」
中世武士の罪業感と宗教観を垣間見る思いがする。
[書き手] 山崎一昭(新聞記者)
ALL REVIEWSをフォローする