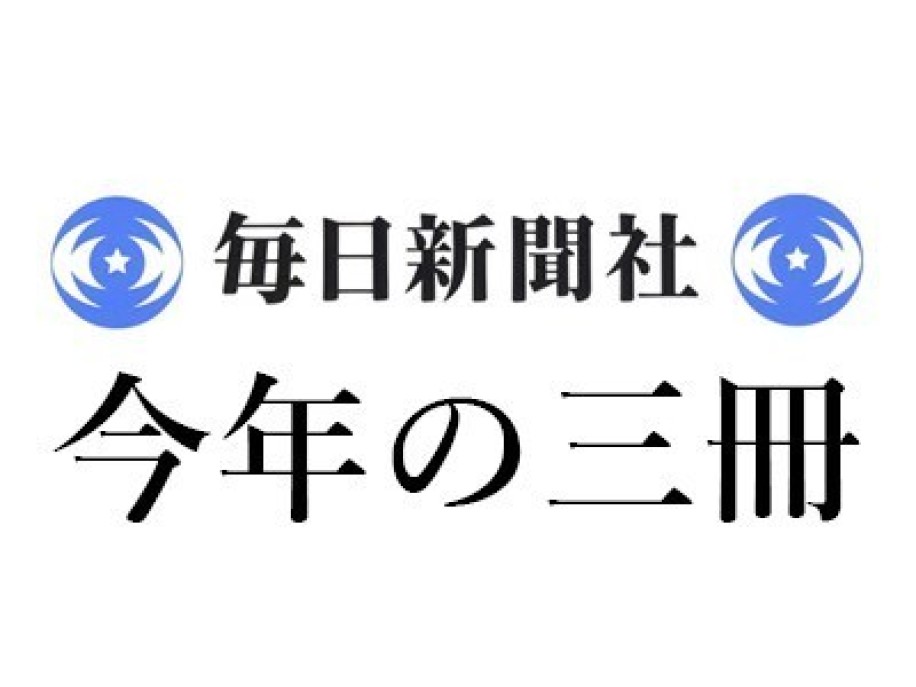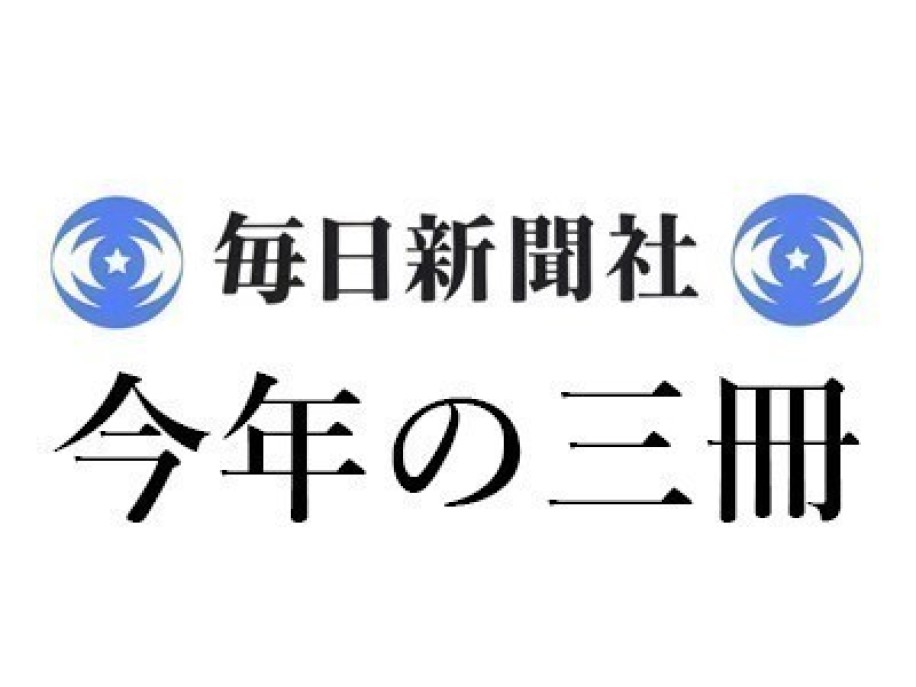前書き
『[図説]食材と調理からたどる中世ヨーロッパの食生活:王侯貴族から庶民にいたる食の世界、再現レシピを添えて』(原書房)
中世に生きる人たちは何を食べていたのだろうか。中世ヨーロッパの食文化を当時の写本から徹底的に読み解くと、意外なほど豊かな中世が見えてくる。当時の食事を再現した60あまりのレシピも収録した書籍『[図説]食材と調理からたどる中世ヨーロッパの食生活』より序文を公開します。
さらに、中世の怠惰な貴族階級は、その城内で赤肉(哺乳動物の肉)をこれでもかというほど貪り食い、アルコール度数が高くスパイスを効かせたワインを来る日も来る日もがぶ飲みし、アルコール中毒になり痛風で身動きが不自由になっていた。そして上流階級の食卓にのぼる肉も腐敗している場合が多かったが、その悪臭を隠そうと、高価なスパイスを大量に使っていた――現代ではこうしたステレオタイプな見方がはびこっているのだ。
質が劣っていて風味に乏しい、あるいは過度に味付けされていること以外にも、中世の食べ物の多くはとても辛く、どろどろであったり胸が悪くなったりするような代物だった。調理法は、異常とは言わないまでもお粗末なものだ。当時の人々のテーブルマナーは不愉快きわまりなく、その結果、中世末期の道徳家たちはエチケットの手引きやコンダクト・ブック[道徳、礼儀作法書]をまとめたもののお手上げ状態となり、正餐の場では野蛮な行動や無作法が野放しになっていた。今に伝わっているのはこうした内容のものだ。
本書を書く目的は、当時主流だった習慣や態度、食にまつわるイデオロギーについて語り、前述のような誤解を正して、今日の読者に中世の台所を知ってもらうことにある。本書でおもに扱うのは中世後期(1300頃~1550年)であり、この時期は、同じ中世でもそれ以前の時代よりも食文化に関する一次資料や情報が豊富だ。地理的にはヨーロッパ全土を取り上げている。
本書は、中世末期の資料や現代における調査・研究を根拠として、レシピや中世の食文化の特徴を紹介、解説している。中世の食物史の主要な資料となるのは写本だ。それには料理書やレシピ集、請求書、税金の記録、帳簿、遺書や遺言書、日記や年代記、諸々の手引き書、百科事典や物語など多様なものがある。中世の下層階級の食習慣に関する情報を調べるにあたっては、考古学の知識も重要だ。貧しい人々のレシピは、通常は記録されなかったからだ。壁画、板絵、細密画、木版画、タペストリーやステンドグラスも役に立つ情報源だ。さまざまな資料で情報を補完し、利用できるあらゆる資料に情報を求めることが重要だ。書き記されたものから得る情報によって、考古学上の発見物をもとにしたものとはまったく異なる結論に導かれることもあるからだ。
中世の料理書やレシピは現代の読者が読むには難しい。原本から句読点が消失している場合が多く、単語や節がだらだらと続くからだ。レシピはレシピと言えるような代物ではないこともあり、指示は短くごく簡潔であったり、あいまいであったりする。また、調理手順がすべて書かれているわけではない―パンを焼く手順や生地作りは書かれていない場合が多い。材料の分量や調理時間、温度が書かれていないことも珍しくはない―多くの場合、「好きなだけ」、「少々」、「適宜」や「好みで」といった言葉が書かれているだけだ。概して、材料はしっかりと、あるいはその直前まで火を通す。このように正確さを欠くのは、中世が口頭伝達の時代だったことがその大きな理由だ。
このため現代の食物史家は、中世のレシピをもとに実際に作ってみて、必要な食材の分量や調理時間や温度を導き出さなければならない。本書のレシピ紹介の章では、今日の一般家庭のキッチンで用意できるものを考慮しつつ、自分の知識をフルに使って中世の調理手順を解説することに努めた。中世の料理人がチョウザメの浮袋を使い[浮袋からゼラチンを抽出した]、すり鉢とすりこぎや、ザルや漉し器を使い何度も裏漉しするような調理法を用いている場合は、私は迷わず、調理にゼラチンリーフや電動ブレンダーを使うことを提案している。同じ資料をもとにしたレシピでも、実際に作ってみて、仲間の研究者たちが提案しているのとは少々異なる分量や調理方法をお勧めすることにした箇所もいくつかある。読者のみなさんにはこれまでの調理経験や常識を生かし、とくにスパイスの分量に関しては自分の味の好みに従っていただきたい。本書のレシピは五感を喜ばせるためのものなのだから!
[書き手]ハンネレ・クレメッティラー(中世研究家)
誤解だらけの中世の食事
近年、中世料理が人気だ。ヨーロッパでは、イギリスなど各国で中世の饗宴の再現が企画され、中世料理をテーマとした新しい書や研究が次々と世に出ている。そうではあるが、中世の食文化については次のような誤解があって、それは払拭されないままで驚くほどだ。曰く、中世で日々食べられていたのは、まずくて体によくない、種類も少なく味付けが単調な食べ物だった。下層階級はぱさぱさのパンと水のような野菜スープを日々の食事とし、そのスープには運がよければなにか具が浮いているが、具が入っているのは景気がよいときだけ。当時の人々は食料不足による空腹のためやせ細っていた。祝祭日のごちそうでは、人々は腹がパンクするほどたらふく食べた。しかし彼らが食べる肉は、腐っているか、塩の味しかしないような代物だった――。これが世間一般の見方だろう。さらに、中世の怠惰な貴族階級は、その城内で赤肉(哺乳動物の肉)をこれでもかというほど貪り食い、アルコール度数が高くスパイスを効かせたワインを来る日も来る日もがぶ飲みし、アルコール中毒になり痛風で身動きが不自由になっていた。そして上流階級の食卓にのぼる肉も腐敗している場合が多かったが、その悪臭を隠そうと、高価なスパイスを大量に使っていた――現代ではこうしたステレオタイプな見方がはびこっているのだ。
質が劣っていて風味に乏しい、あるいは過度に味付けされていること以外にも、中世の食べ物の多くはとても辛く、どろどろであったり胸が悪くなったりするような代物だった。調理法は、異常とは言わないまでもお粗末なものだ。当時の人々のテーブルマナーは不愉快きわまりなく、その結果、中世末期の道徳家たちはエチケットの手引きやコンダクト・ブック[道徳、礼儀作法書]をまとめたもののお手上げ状態となり、正餐の場では野蛮な行動や無作法が野放しになっていた。今に伝わっているのはこうした内容のものだ。
本書を書く目的は、当時主流だった習慣や態度、食にまつわるイデオロギーについて語り、前述のような誤解を正して、今日の読者に中世の台所を知ってもらうことにある。本書でおもに扱うのは中世後期(1300頃~1550年)であり、この時期は、同じ中世でもそれ以前の時代よりも食文化に関する一次資料や情報が豊富だ。地理的にはヨーロッパ全土を取り上げている。
本書は、中世末期の資料や現代における調査・研究を根拠として、レシピや中世の食文化の特徴を紹介、解説している。中世の食物史の主要な資料となるのは写本だ。それには料理書やレシピ集、請求書、税金の記録、帳簿、遺書や遺言書、日記や年代記、諸々の手引き書、百科事典や物語など多様なものがある。中世の下層階級の食習慣に関する情報を調べるにあたっては、考古学の知識も重要だ。貧しい人々のレシピは、通常は記録されなかったからだ。壁画、板絵、細密画、木版画、タペストリーやステンドグラスも役に立つ情報源だ。さまざまな資料で情報を補完し、利用できるあらゆる資料に情報を求めることが重要だ。書き記されたものから得る情報によって、考古学上の発見物をもとにしたものとはまったく異なる結論に導かれることもあるからだ。
中世の料理書やレシピは現代の読者が読むには難しい。原本から句読点が消失している場合が多く、単語や節がだらだらと続くからだ。レシピはレシピと言えるような代物ではないこともあり、指示は短くごく簡潔であったり、あいまいであったりする。また、調理手順がすべて書かれているわけではない―パンを焼く手順や生地作りは書かれていない場合が多い。材料の分量や調理時間、温度が書かれていないことも珍しくはない―多くの場合、「好きなだけ」、「少々」、「適宜」や「好みで」といった言葉が書かれているだけだ。概して、材料はしっかりと、あるいはその直前まで火を通す。このように正確さを欠くのは、中世が口頭伝達の時代だったことがその大きな理由だ。
このため現代の食物史家は、中世のレシピをもとに実際に作ってみて、必要な食材の分量や調理時間や温度を導き出さなければならない。本書のレシピ紹介の章では、今日の一般家庭のキッチンで用意できるものを考慮しつつ、自分の知識をフルに使って中世の調理手順を解説することに努めた。中世の料理人がチョウザメの浮袋を使い[浮袋からゼラチンを抽出した]、すり鉢とすりこぎや、ザルや漉し器を使い何度も裏漉しするような調理法を用いている場合は、私は迷わず、調理にゼラチンリーフや電動ブレンダーを使うことを提案している。同じ資料をもとにしたレシピでも、実際に作ってみて、仲間の研究者たちが提案しているのとは少々異なる分量や調理方法をお勧めすることにした箇所もいくつかある。読者のみなさんにはこれまでの調理経験や常識を生かし、とくにスパイスの分量に関しては自分の味の好みに従っていただきたい。本書のレシピは五感を喜ばせるためのものなのだから!
[書き手]ハンネレ・クレメッティラー(中世研究家)
ALL REVIEWSをフォローする

![[図説]食材と調理からたどる中世ヨーロッパの食生活:王侯貴族から庶民にいたる食の世界、再現レシピを添えて / ハンネレ・クレメッティラー](https://m.media-amazon.com/images/I/51OApTm9mvL._SL500_.jpg)