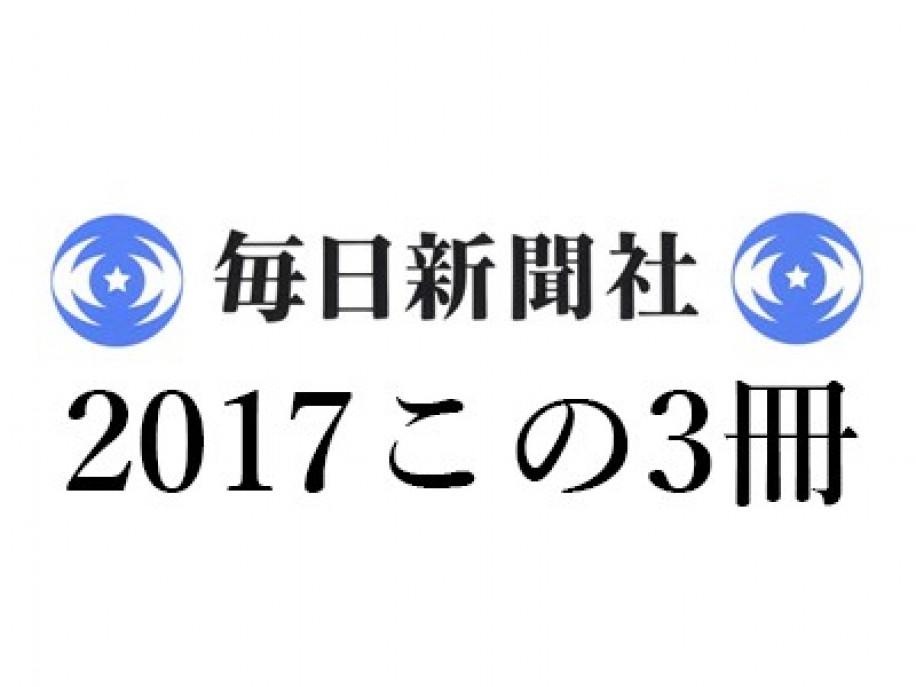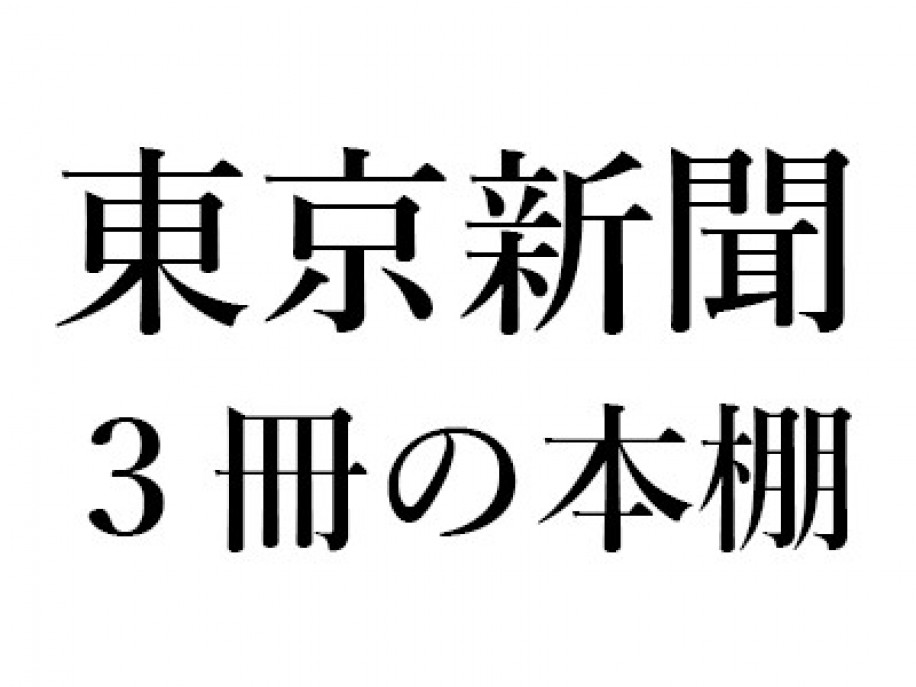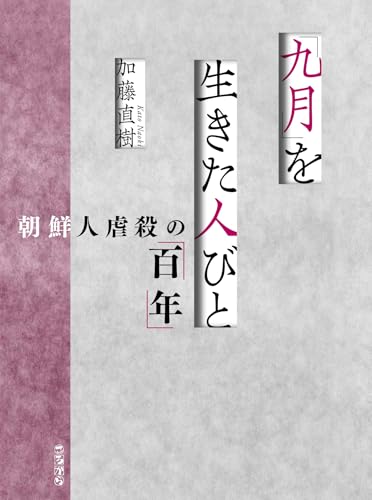書評
『ルポ 筋肉と脂肪 アスリートに訊け』(新潮社)
勝つための極限の先に食べる喜び
「筋肉と脂肪」とはまた、食文化を見つめてきた著者がたどり着いた究極の地点か、とも思う。自らの身体そのものを表現手段にして、日々それを磨き上げて競技に挑むアスリートたちにとって、「食べること」はそれ自体、仕事であり、鍛錬であり、技術である。栄養を考え抜いた献立と、効率よく吸収するタイミング、トレーニングとの関係、睡眠との関係、プロテインの威力など、「食べる」とはかくも科学的な営為かと、舌を巻く例が積み上げられる。
登場するアスリートたちも多彩で、相撲取り、プロレスラー、陸上選手、車いすバスケットボール選手、野球選手、サッカー選手、マラソンランナーなど。彼らの「食」に関わるスポーツ栄養士や、プロテインの開発者、体脂肪計の開発に関わった人物、学者、はたまた学生の胃袋を預かる寮母も取材の対象になる。そして彼らがまた、驚くほどの金言を、体と食に関して紡ぎ出す。
「マッスルメモリー」(押尾川親方)
「アスリートにとって、和食の存在はアドバンテージ」(あるラグビー部監督)
「チケット代の半分は、おまえたちの筋肉」(山本小鉄)
「筋肉は、いちばん身近な宇宙」(桑原弘樹)
「アスリートは芸術作品」(鈴木志保子)
押尾川親方の「マッスルメモリー」は、筋肉じたいに記憶力がある、という意味。衰えても、一度鍛えた筋肉は蘇らせることができる。「筋肉は裏切らない」とも通じるところのある、経験則からくる筋肉への強い信頼がある。
筋肉とは、興味深いものらしい。「筋肉は、いちばん身近な宇宙」は、筋肉増量に働きかけるサプリメント、クレアチンを開発した人物の言葉。無限の可能性を秘めた場所、というほどの意味か。筋トレはセロトニンを生み、筋肉の目に見える変化は自己肯定感につながるという。「キン肉マン」という人気漫画さえ生んだ「筋肉」の魅力。「筋肉には、感情を物語ったり取り込んだりする力がある」「筋肉への欲望」が「情緒的なメッセージの伝達を強く受け取る」と著者は指摘する。
「アスリートは芸術作品」という言葉には、「オリンピックでメダルをもたらす」公認スポーツ栄養士の鈴木志保子の、選手一人ひとりへの敬意が込められる。選手よりも「勝ち」にこだわる鈴木から、著者は「指導者や栄養士が、自分の思想を押しつけちゃだめ」「食べることが当たり前になるように、楽しくなるように。その思いが私のなかにはずっとあります」という言葉を引き出す。
極限まで体重を落とし「無月経」を招くことすら奨励された女子マラソン界で、生理があるのは強み、速く走るには強い体=健康な体が必要と公言する新谷(にいや)仁美選手のインタビューも迫力がある。
しなやかな筋肉を作り、エネルギーを生み出す脂肪を競技に必要なだけまとうために、アスリートたちは考えて、考え抜いて、食べる。そのプロフェッショナルな姿勢の陰に、しかし、もう少し機微の細やかな、「食」への思いがある。「食」は、やはり根源的な喜びであり、コミュニケーションであり、健やかな心と体を支えるものであると、あきらかにされていく過程が鮮やかで心に残った。
ALL REVIEWSをフォローする