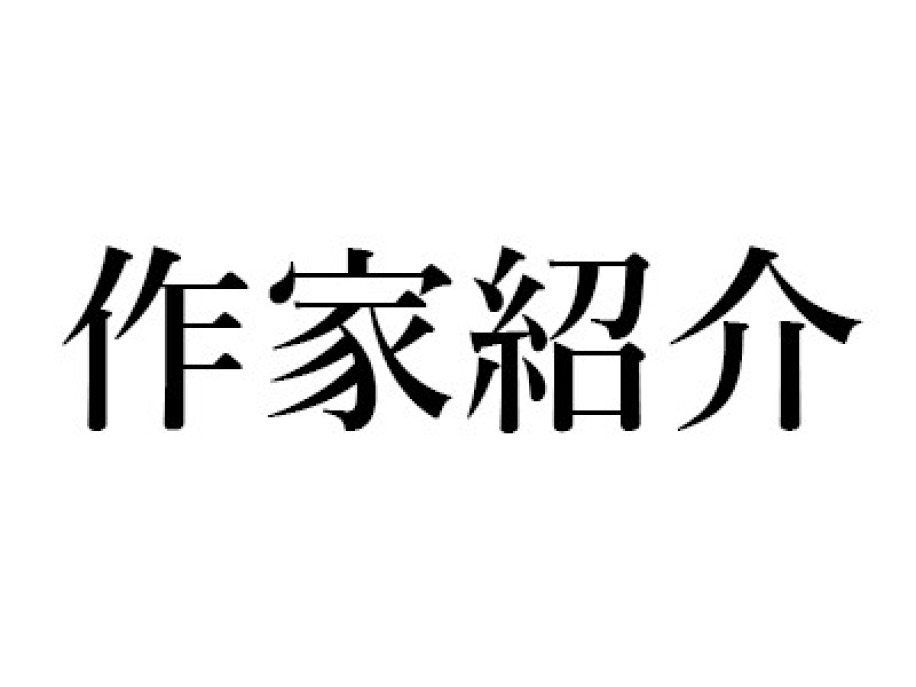書評
『新訳 老人と海』(左右社)
「the boy=成人男性」の新解釈
ヘミングウェイの代表作『老人と海』の新訳が上梓された。同作家の研究の第一人者今村楯夫による翻訳であり、巻末には手厚い解説も収録している。ノーベル文学賞の発表が近いが、同賞は特定の作品に与えられるものではない。しかしヘミングウェイはその授賞対象を名指された数少ない一人だ。同時代作家の文体に与えた影響と、「最近作『老人と海』に示された卓越した語りの技術に対して」と選評にある。
語彙や構文の点ではおおむね、難解、複雑なところは少ないヘミングウェイ作品だが、翻訳の難度では最上位に入る作家だと思う。『老人と海』は特にある点が長らく議論の的になってきた。老漁師サンティアゴに寄り添うthe boyは何歳なのか? 「十歳説」と「二十二歳」説があるという。
多数ある日本語既訳では、このマノリンという人物は十歳から十代前半の「少年」に想定されていた。映画でも十代前半の子役が演じている。今回の新訳は二十二歳説をとり、初めてthe boyを成人した「若者」として訳出した。
成人男性と判断した理由は、訳者解説で丁寧に説かれている。一つには、八十四日間も不漁がつづいているサンティアゴに対するマノリンの心づくしの言動。たとえば、マノリンに「ビールを一杯、テラス亭でおごらせてくれないかな」と持ちかけられる場面で、老人は快諾し、between the fishermenと付け添える。今村訳は「漁師仲間だしな」だ。
ほかにもマノリンは店でツケがきくとか、重い漁具などを運べるとか、“猥談”にうまい返しをしている箇所などが挙げられ、一番の争点である野球選手に関する記述の細密な読解に入る。
マノリンが若い成人男性となると、作品の印象はだいぶ変わってくるだろう。自分もすでに経験を積んだ漁師でありながら、老漁師に全幅の尊敬と信頼をおく若者の謙虚さや親愛の情がより強く感じられるようになる。
また、朝早く漁に出る前に、老人のほうが青年を起こしにいってやる場面からも――子どもが相手なら自然だが――サンティアゴが彼をまだ保護の必要な息子のように可愛がっているのが伝わってきた。実際、老人がIf you were my boy([おまえが]わしの息子だったら)という仮定法で語りかけるくだりもある。
沈みかけた月の明かりが、部屋で眠るマノリンの姿を照らしだし、老人は「若者の脚にそっと手を添え、目を覚ますまでそのままでいた」というくだりには、そこはかとなく大人の男性同士の愛情関係すら感じられた。独り漁に出た老人はしきりと「あの若者がいてくれたら」と思うのだ。
今村訳は、カジキマグロとの激闘以外の細やかなシーンにも留意し、新たな視点を呼びこむ。サンティアゴは「殺される側」の魚に「兄弟」として畏敬の念を抱く。獲物を鮫(さめ)に貪られ、帰り着いた浜で丘にへたりこむ老漁師のずっと先を横切る猫の眼差し、通りすがりの旅行者たちの目……。若い漁師に継承される生と、消えゆく生。それらの重みを知らない目に映じられることで、物語の感傷が洗われる。翻訳により世界が刷新される。多彩な既訳も併読されたい。それぞれに彫琢された訳文と解説を楽しめるのは、翻訳書読者ならではの贅沢なのだから。
ALL REVIEWSをフォローする