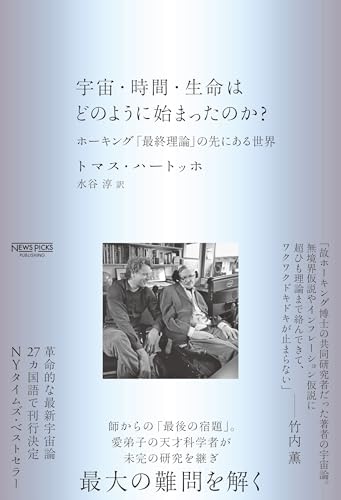書評
『やまと言葉の人間学』(ぺりかん社)
「潑剌たる生の内容」にふれる瞬間
「たしなみ」は「ニュアンスに微妙な幅のある、すこし不思議なやまと言葉である」と著者は言う。「お酒をたしなむ」は「好んで親しむ」の意だが、「武道をたしなむ」になると、それに「一定の心得、覚えがある」という意が加わる。「我が身をたしなむ」となると「つつしみ、用心する」の意であり、「身だしなみ」とも使う。そこから「忠告する」意味の「たしなめる」という言葉も派生する。そこには「欲求と節制のほどよい加減」があるのだ。「お酒は召し上がりますか」と尋ねられた時に「たしなむ程度には」と答えるのは、飲む量はともかく、節制の大切さは心得ていますと伝えたいのだろう。「もてなし」「つつしみ」「ほほえみ」「きれいさ」「かたじけなさ」「いたわり」「やさしさ」「なつかしさ」「あわれ」などのやまと言葉と、「ゆめ」「いかり」「おに」「いのり」「かぜ」など、日本文化の中で重要な役割を果たしている言葉が検討される。
著者は倫理学、日本思想史をやまと言葉で考え続けてきた。きっかけは、和辻哲郎の「日本人は何ゆえに彼らの活きた言葉をもって考えようとしないのであろうか。平俗な言葉を使うのが学者の威厳をそこなうがゆえであろうか。あるいは潑剌たる生の内容を担った言葉をコナシ切れず、すでに哲学語として使い古された言葉の翻訳を必要とするのであろうか」という呼びかけだった。
漢語、翻訳語、カタカナ語を排除するつもりはなく、ましてやその先に純粋なかたちの日本精神なるものを取り出そうなどという気はさらさらない。やまと言葉のもつ「他者や事物への、より具体的、より直接的な結びつきや関わりのあり方を、それ自体として確かめ」、「活きた」「潑剌たる生の内容」を取り戻そうとするだけだ。科学の世界にいる評者も、人間について考える時、やまと言葉が本質を見せると感じる場合がよくある。概念性、抽象性を活かしながら、それを日常につなげられるのだ。
花鳥風月の中でも風は、見えないがゆえに聞く、触れる、嗅ぐなど、複合的に気配を感じさせる。それが風雅、風情、風味などなど、細やかな感覚を表現する言葉につながるのだ。芭蕉は「片雲の風に誘はれて、漂泊の思ひやまず」と旅に発つ。宮沢賢治の作品は「きれいにすきとおった風をたべ」るところから始まっているし、宮崎駿は自然の中で生きようとするナウシカを風の谷に置いた。しかし今や都会では、空調機からの空気の流れの中で過ごし、外へ出るとビル風に飛ばされそうになる日常を送っており、風情とはほど遠い。
著者は、日本人が自然から学びとったのは、すべては「おのずから」と「みずから」の「あわい(間、出会うところ)」にあるという生き方だと言う。「しあわせ」は、本来「みずから」の努力で「うまく合うようにする」という意味であったが、やがて運という「おのずから」の働きを含意するようになったのだ。やまと言葉を用いれば正しい生き方が見えてくるというわけではない。言葉は動いていくものであり、新しい言葉の取り入れは大事だ。とはいえ、なんでも「ヤバッ」ですませてしまっては、思考も暮らしも豊かにはならない。今起きている異常気象や格差などの課題を解くには、「欲求と節制のほどよい加減」を探るしかないのではなかろうか。
ALL REVIEWSをフォローする