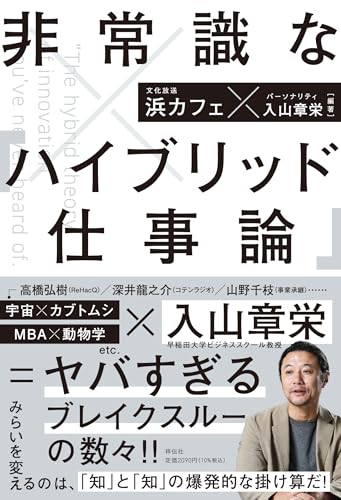内容紹介
『歌う言葉 考える音ーー世界で一番かわいい哲学的音楽論』(祥伝社)
近年、SNSなどでも大バズリ中のアイドルグループFRUITS ZIPPER。その代表曲とも言える『わたしの一番かわいいところ』『NEW KAWAII』の作詞・作曲を手掛けたのが、音楽クリエイターのヤマモトショウさんです。
ヤマモトさんは、超難関の東京大学理科Ⅰ類に入学し、数学科に進んだあと哲学科に転籍し、卒業後にはバンドふぇのたすのギターとして活躍した異色の経歴をもつ音楽クリエイター。近年では地元静岡のアイドルグループをプロデュースし、地元企業や自治体を巻き込んだローカルビジネスにも注力するなど、活動の幅はますます広がっています。
作詞という行為についてヤマモトさんは、「何か天啓を受けてひらめきまくっているわけではなく、言葉を言い換えたり整えたりしていることがほとんど」と言います。
しかし、そのアカデミックな知識に裏付けられた言葉の選び方とアイデアの生み出し方は、音楽ファンのみならず、企画職の方や言語化に悩む方々にとっても大いに参考になるものです。
今回、ヤマモトさんが自身のキャリアを振り返りながら、作詞論、音楽論について考察した『歌う言葉 考える音――世界で一番かわいい哲学的音楽論』より、一部を抜粋して紹介します。
「好き」の解像度を上げていくにはどのような方法があるでしょう。もちろん、人とは違う突飛なことをしなさい、というように言ってしまうのは簡単です。私が読んだ「作詞の方法について書かれた」本では、「自分なりの経験が歌詞になる」というようなことが書いてあることがほとんどでした。たしかに「結果的」にはそうでしょう。
しかし、実際それほど独自の経験をしている人はいません。
なぜならここまで書いてきたことから逆説的にわかることなのですが、それほど解像度の高くない「好み」というのは、実際にこれまで世の中に提出されてきた「こういうの好きでしょ?」によってつくられているからです。
たとえば、「好きな色は何?」と聞かれたら、多くの人が「赤」とか「青」と答えるでしょう。それは一つには、子供の頃に与えられた色のバリエーションがクレヨンとか、絵の具とかの種類でイメージづけられているからであり、また一般的に(有名人などの)このような質問への回答がやはりそのようなイメージづけをもとになされているからです。
もしも幼い頃からの学習によって色がカラーコードで見えている人がいたら、その人のこの質問への回答は非常に独特のものになるでしょう。しかし、それは「好きな色は何?」という質問で「通常」想定されている回答ではないように思います。
つまり、「好きな◯◯」といった話題には、そもそもそれが一般的に前提にしているような答えの範囲があらかじめ内包されていることが多いのです。
「嫌い」から生まれるアイデア
そこで、私はむしろ好きではなくて「嫌い」のほうから創作をスタートすることを薦めています。非常に有名な言葉ですが、「好きの反対は嫌いではなく無関心」という表現があります。これは非常に含蓄のあるフレーズだと思います。
実際「嫌い」というのは創作のモチベーションたりえますが、「無関心」では難しいでしょう。まったく関心のないものについて書くことはできませんが、嫌いなものについては思考を巡らすことが可能です。
むしろ、人は大半の場合「嫌いなもの」「嫌なもの」にどう対処するか、そしてどうやってそれをなるべく良いものにするか、といったことに取り組んでいるようにも思われます。
一例を挙げると、私は小さい頃からハチが苦手なのですが、ハチを避けて生きるた
めにハチの生態については、少なくとも他の昆虫よりも詳しいように思います。
さらにいえば、「好き」よりも「嫌い」のほうがより個人的でありながらも、共有
される可能性を持っているもののように思われます。
「私はこういうことが嫌だと思ったので、それをこういうふうに変えていきたい」といったような内容は、もちろん個人的な快不快といった体験を出発点にしているものではありますが、と同時に他者にとっても「たしかに言われてみれば自分もそう思っていた」といったような感情を呼び起こします。
また、好きなものについて語るときであっても、同時にその分野における「嫌いな
もの」についても考えることで、より「好き」の表現の幅を広げることができます。
ここでは、前述の「色」について考えてみましょう。
私は赤い色が好きで、どうしてもそれについて書きたいと思ったとします(楽曲テーマの設定としては弱いとは思いますが)。赤は好きな色なので、色々と好みの対象が思い浮かぶでしょう。
一方、赤いものとして「血」を挙げることもできます。それは、怪我や痛みを連想するので、どちらかといえば好ましくないと思う人が多いでしょう。テストの赤点(実際に赤で書かれるのかは置いておいて)も基本的にみんな嫌いなものだと思います。
しかし、むしろそういったキーワードにこそ、赤という色から「個性的な」歌詞をつくるヒントがあるように思います。それはつまり、「嫌い」を考えることで「好き」の解像度が上がるからなのです。
「好き」ということの中身をすべて説明しようと思ったらなかなか難しいものです。嫌いを掘り下げることで結果的には「好き」の表現に幅が生まれ、「個性的に」好きなことを書くことができるようになるわけです。
本稿は『歌う言葉 考える音――世界で一番かわいい哲学的音楽論』(祥伝社)より抜粋のうえ作成
[書き手]ヤマモトショウ
ヤマモトさんは、超難関の東京大学理科Ⅰ類に入学し、数学科に進んだあと哲学科に転籍し、卒業後にはバンドふぇのたすのギターとして活躍した異色の経歴をもつ音楽クリエイター。近年では地元静岡のアイドルグループをプロデュースし、地元企業や自治体を巻き込んだローカルビジネスにも注力するなど、活動の幅はますます広がっています。
作詞という行為についてヤマモトさんは、「何か天啓を受けてひらめきまくっているわけではなく、言葉を言い換えたり整えたりしていることがほとんど」と言います。
しかし、そのアカデミックな知識に裏付けられた言葉の選び方とアイデアの生み出し方は、音楽ファンのみならず、企画職の方や言語化に悩む方々にとっても大いに参考になるものです。
今回、ヤマモトさんが自身のキャリアを振り返りながら、作詞論、音楽論について考察した『歌う言葉 考える音――世界で一番かわいい哲学的音楽論』より、一部を抜粋して紹介します。
「好き」の解像度を上げる
「好き」の解像度を上げていくにはどのような方法があるでしょう。もちろん、人とは違う突飛なことをしなさい、というように言ってしまうのは簡単です。私が読んだ「作詞の方法について書かれた」本では、「自分なりの経験が歌詞になる」というようなことが書いてあることがほとんどでした。たしかに「結果的」にはそうでしょう。しかし、実際それほど独自の経験をしている人はいません。
なぜならここまで書いてきたことから逆説的にわかることなのですが、それほど解像度の高くない「好み」というのは、実際にこれまで世の中に提出されてきた「こういうの好きでしょ?」によってつくられているからです。
たとえば、「好きな色は何?」と聞かれたら、多くの人が「赤」とか「青」と答えるでしょう。それは一つには、子供の頃に与えられた色のバリエーションがクレヨンとか、絵の具とかの種類でイメージづけられているからであり、また一般的に(有名人などの)このような質問への回答がやはりそのようなイメージづけをもとになされているからです。
もしも幼い頃からの学習によって色がカラーコードで見えている人がいたら、その人のこの質問への回答は非常に独特のものになるでしょう。しかし、それは「好きな色は何?」という質問で「通常」想定されている回答ではないように思います。
つまり、「好きな◯◯」といった話題には、そもそもそれが一般的に前提にしているような答えの範囲があらかじめ内包されていることが多いのです。
「嫌い」から生まれるアイデア
そこで、私はむしろ好きではなくて「嫌い」のほうから創作をスタートすることを薦めています。非常に有名な言葉ですが、「好きの反対は嫌いではなく無関心」という表現があります。これは非常に含蓄のあるフレーズだと思います。実際「嫌い」というのは創作のモチベーションたりえますが、「無関心」では難しいでしょう。まったく関心のないものについて書くことはできませんが、嫌いなものについては思考を巡らすことが可能です。
むしろ、人は大半の場合「嫌いなもの」「嫌なもの」にどう対処するか、そしてどうやってそれをなるべく良いものにするか、といったことに取り組んでいるようにも思われます。
一例を挙げると、私は小さい頃からハチが苦手なのですが、ハチを避けて生きるた
めにハチの生態については、少なくとも他の昆虫よりも詳しいように思います。
さらにいえば、「好き」よりも「嫌い」のほうがより個人的でありながらも、共有
される可能性を持っているもののように思われます。
「私はこういうことが嫌だと思ったので、それをこういうふうに変えていきたい」といったような内容は、もちろん個人的な快不快といった体験を出発点にしているものではありますが、と同時に他者にとっても「たしかに言われてみれば自分もそう思っていた」といったような感情を呼び起こします。
また、好きなものについて語るときであっても、同時にその分野における「嫌いな
もの」についても考えることで、より「好き」の表現の幅を広げることができます。
ここでは、前述の「色」について考えてみましょう。
私は赤い色が好きで、どうしてもそれについて書きたいと思ったとします(楽曲テーマの設定としては弱いとは思いますが)。赤は好きな色なので、色々と好みの対象が思い浮かぶでしょう。
一方、赤いものとして「血」を挙げることもできます。それは、怪我や痛みを連想するので、どちらかといえば好ましくないと思う人が多いでしょう。テストの赤点(実際に赤で書かれるのかは置いておいて)も基本的にみんな嫌いなものだと思います。
しかし、むしろそういったキーワードにこそ、赤という色から「個性的な」歌詞をつくるヒントがあるように思います。それはつまり、「嫌い」を考えることで「好き」の解像度が上がるからなのです。
「好き」ということの中身をすべて説明しようと思ったらなかなか難しいものです。嫌いを掘り下げることで結果的には「好き」の表現に幅が生まれ、「個性的に」好きなことを書くことができるようになるわけです。
本稿は『歌う言葉 考える音――世界で一番かわいい哲学的音楽論』(祥伝社)より抜粋のうえ作成
[書き手]ヤマモトショウ
ALL REVIEWSをフォローする