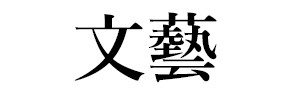書評
『マイルス・デイヴィスの真実』(講談社)
物書きにとって、自分が心の底から敬愛する人物について何かを書くというのは楽しい作業である筈だが、その人物の魅力が余りに圧倒的で、しかも著者が彼とじかに接したことがあるような場合には、なかなか容易ではないのかもしれない。昨年日本で翻訳が出たクインシー・トループの『マイルス・アンド・ミー』を読んだ時、私は改めてそんなことを考えた。読み物としてはそこそこに面白かったが、『マイルス・デイビス自叙伝』の無類の感動を思えば、あれを纏め上げた功労者の作としては何とも物足りなかったし、何よりも方々に散見される「憧れの人」への屈折した心理と自尊心の喘ぎとが、分かるとはいえ、私には鼻について仕方がなかった。
そもそも、タイトルからして悪い冗談のようである。
『マイルス・デイヴィスの真実』を読む前に、私はついそうしたことを心配していたが、一読してそれが杞憂に過ぎなかったことを知り、あとは心から楽しんで読んだ。著者である小川氏のマイルスへの愛情には、読者を安心させるような率直さがあり、それがこの労作を、単なる資料的な仕事以上の愛すべきものとしている。
この本の読み方は、色々あると思う。マイルス・デイヴィスという二〇世紀後半の最もクリエイティヴな音楽家についての、これはいわば格好の入門書であろうし、また、彼の音楽のみを知り、生涯についてはあまり知らないという人には、その人間的な魅力に目を開かせる伝記としての意味も持っているだろう。
私はやはり、この本を、前述の『自叙伝』と併読することをお奨めしたい。『自叙伝』には、マイルスの極めて正直な心情が語られていて、そのリアリティは強く読者の胸を打つが、中には彼独特の遊び心というべきか誇張や虚構もあるようで、この本を読むと、その何処がどう事実と違っているのかということが明らかになる。例えば、七〇年代後半の彼の沈黙についても、『自叙伝』では、「オレは、一九七五年から一九八〇年の初めまで、一度も、ただの一度もだ、トランペットを持たなかった。」とあるが、この本を読むと、それもどうも大袈裟なようだということが分かる。
ただ、肝心なのは、だから彼が、『自叙伝』の中ではホラを吹いているというのではなくて、あの五年間が、彼にとってそう語られざるを得ない期間として回想されているというそのことの意味を考えてみることである。それは、彼の一生に対する理解を一層深めてくれるのではあるまいか?
また、『自叙伝』との関連では、この本がそれ以後をフォローしているという点も重要である。
色々と面白い逸話もあるが、私が殊に心惹かれたのは、著者がマイルスの自宅からサンドイッチを買いに行き、雨に降られて店先で難渋していたところに、傘を差し、彼の分の傘まで携えてマイルス本人が迎えに来たという話である。私は勿論、生前のマイルスに会ったことはないが、その時の彼の姿は意外な逸話であるにも拘わらず不思議とはっきり想像することが出来る。それは彼を愛する者皆が何処かで予感していた彼の繊細さと孤独とを、これ以上ないほどに象徴している光景だからではあるまいか?
【この書評が収録されている書籍】
そもそも、タイトルからして悪い冗談のようである。
『マイルス・デイヴィスの真実』を読む前に、私はついそうしたことを心配していたが、一読してそれが杞憂に過ぎなかったことを知り、あとは心から楽しんで読んだ。著者である小川氏のマイルスへの愛情には、読者を安心させるような率直さがあり、それがこの労作を、単なる資料的な仕事以上の愛すべきものとしている。
この本の読み方は、色々あると思う。マイルス・デイヴィスという二〇世紀後半の最もクリエイティヴな音楽家についての、これはいわば格好の入門書であろうし、また、彼の音楽のみを知り、生涯についてはあまり知らないという人には、その人間的な魅力に目を開かせる伝記としての意味も持っているだろう。
私はやはり、この本を、前述の『自叙伝』と併読することをお奨めしたい。『自叙伝』には、マイルスの極めて正直な心情が語られていて、そのリアリティは強く読者の胸を打つが、中には彼独特の遊び心というべきか誇張や虚構もあるようで、この本を読むと、その何処がどう事実と違っているのかということが明らかになる。例えば、七〇年代後半の彼の沈黙についても、『自叙伝』では、「オレは、一九七五年から一九八〇年の初めまで、一度も、ただの一度もだ、トランペットを持たなかった。」とあるが、この本を読むと、それもどうも大袈裟なようだということが分かる。
ただ、肝心なのは、だから彼が、『自叙伝』の中ではホラを吹いているというのではなくて、あの五年間が、彼にとってそう語られざるを得ない期間として回想されているというそのことの意味を考えてみることである。それは、彼の一生に対する理解を一層深めてくれるのではあるまいか?
また、『自叙伝』との関連では、この本がそれ以後をフォローしているという点も重要である。
色々と面白い逸話もあるが、私が殊に心惹かれたのは、著者がマイルスの自宅からサンドイッチを買いに行き、雨に降られて店先で難渋していたところに、傘を差し、彼の分の傘まで携えてマイルス本人が迎えに来たという話である。私は勿論、生前のマイルスに会ったことはないが、その時の彼の姿は意外な逸話であるにも拘わらず不思議とはっきり想像することが出来る。それは彼を愛する者皆が何処かで予感していた彼の繊細さと孤独とを、これ以上ないほどに象徴している光景だからではあるまいか?
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする