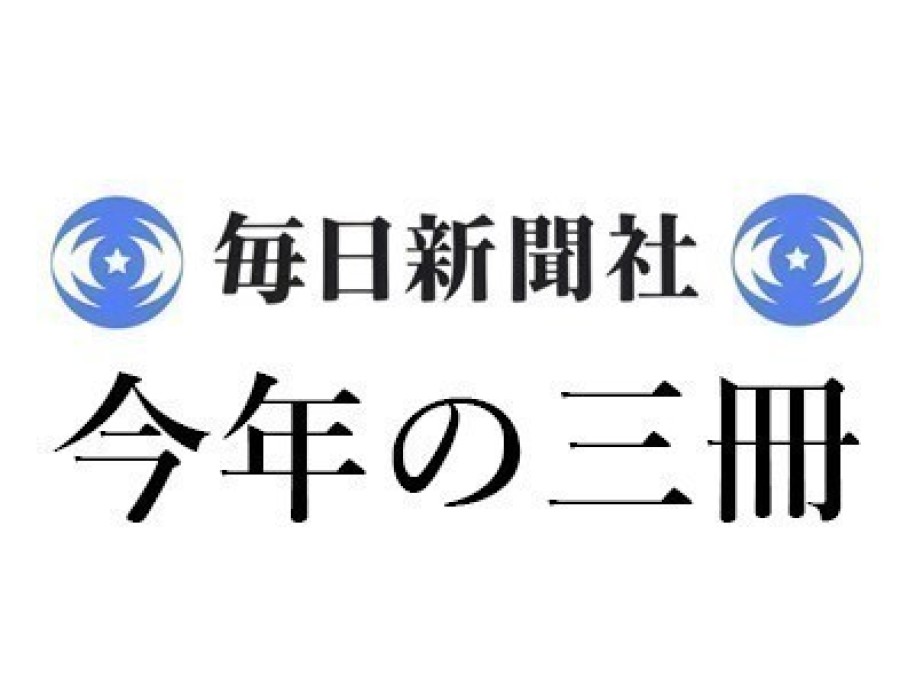書評
『このとき、夜のはずれで、サイレンが鳴った』(岩波書店)
文化人類学者だった原の「遺言」
昔、原広司は、私にとって、建築家というより、文化人類学者だった。何となくタイトルに似せた表現になりましたが、本当のところなのです(もっとも、書物のタイトルとしては、なにがしか異様な感を与える本書のタイトルは、原が永年愛したカミュの『異邦人』の中で、主人公ムルソーが処刑を迎える最後に近い件(くだり)から採られています)。世界の集落を訪ね歩き、人間が集まったときに何が起こるか、を実体験しながら、原は、稀有(けう)な論説「均質空間論」(『空間<機能から様相へ>』岩波現代文庫所収)を仕上げたのでした。そして本書は、建築の実作家としての原の作品を背景に、時代と社会への鋭い洞察者としての原の面目が鮮やかに看取できる一冊となりました。その原に初めて親しく話をするようになったのは、CULCONという日米の識者が集まる会議に出席する機上でした。お互いのパスポートを、ひょんなことで見せ合うことになって、二人の生年月日が全く同じであることを発見したのです。人間性とは一切無関係な、言わば物理的な暗号に過ぎないには違いないのですが、不思議な絆が生まれました。そして今年彼は鬼籍に入ったのです。ただ物理的な暗号は、タイトルの「夜」では重なっています。幼時、夜間の空襲の記憶は、今も(と言ってももう彼はいないのですが)夜寝るとき明かりを消さない、という共通の習慣と結びついてもいます。
本書は、原に最も近かった都市論の大家である吉見との間に交わされた、普通には得られない、貴重な対話の再現です。話柄(わへい)は、吉見は、数学だけは除いてほしい、と最初に注文を付けますが、風発する二つの精神の赴くところ、漱石の『それから』から、アインシュタインの反量子力学の言説まで、カミュ、ベケット、サルトルからティム・インゴルドまで、留(とど)まるところがありません。
この種の書物は、要約して紹介することの、最も困難な性格のものです。ひたすら、「読む」こと自体に、楽しみを、時には魂への衝撃を、そして豊かな満足を、求めるべき類の書物です。特に、この企画は、原の提案で始まったものらしく、原は、様々な形で対話に絡む話題やエピソード、ヒントなどを、肉筆のメモや、描図などとして、驚くべき周到さで準備して対話に臨んだようです。それらは有難いことに、すべて本書で、生のまま再現されているのです。建築家というのは、自分のアイディアや着想を、紙の上に描いて見せることが、職業的習慣になっていますが、本書を見ると、対話における原の肉声だけでなく、手書きの文字、スケッチなどに豊富に触れられるのです。それは本書の特色の一つです。再現に力を尽くされた、編集業務に立った人々のご苦労も偲(しの)ばれるところです。そういう意味では、私は原の遺言を、本書を読むことで、まざまざと感じとることができ、引き出し役の吉見にも、深い感謝を捧げたい思いです。
どこか個人的な、書評とも言えない文章になってしまいました。その点は読者にお詫びをいたします。ただ、本書が放つ何とも言えない香気のようなものは、直接手に取って読むことでしか感得できないものであることを、読者にお伝えして、書評子としての役割を果たすことにします。
ALL REVIEWSをフォローする