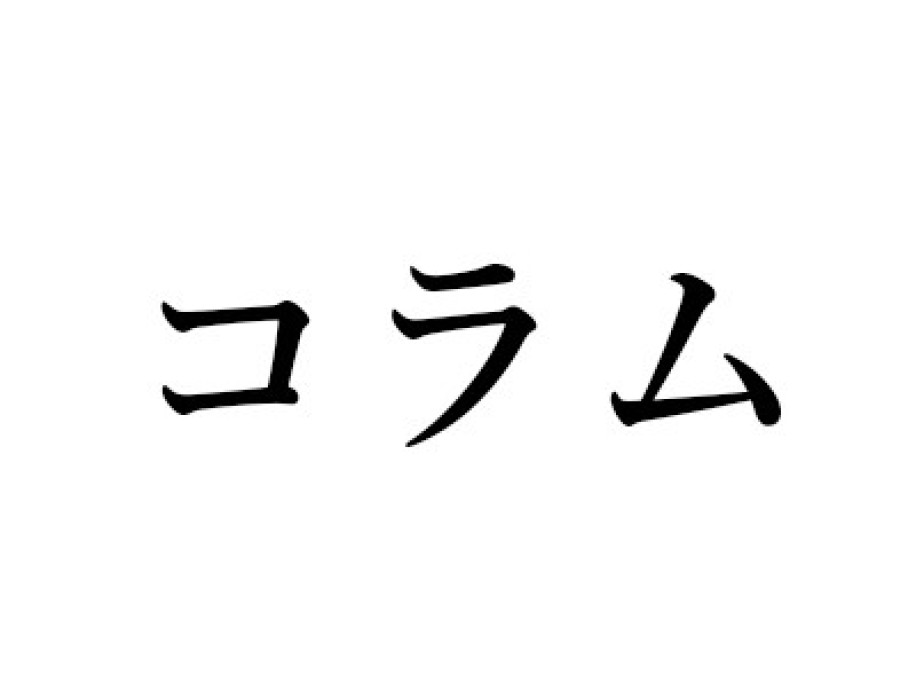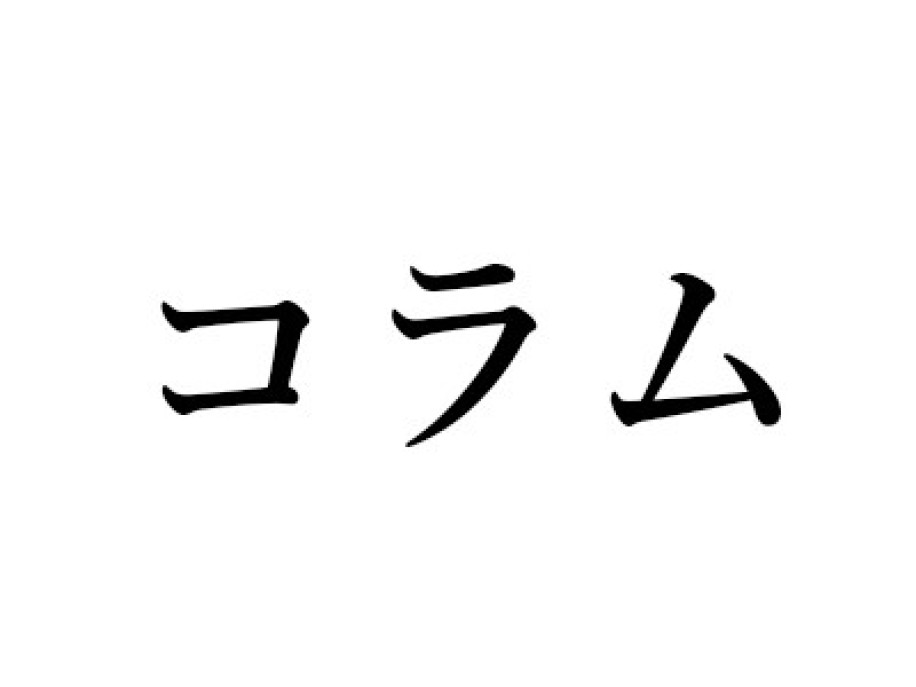解説
『青い雨傘』(文藝春秋)
丸谷流エッセイのおもしろさ
素朴な疑問から始めたい。丸谷才一のエッセイはどうしてこうもおもしろいのだろう。というよりも、どこをどう工夫すると、こうしたおもしろいエッセイが書けるようになるのだろうか。エッセイを頼まれるたびに四苦八苦している私としては、本書の解説を引き受けたのを機会に、ひとつこの丸谷流エッセイのおもしろさの構造という問題を解いてみたいと思う。よく、『エッセイの書き方』などの本を読むと、エッセイの命は書き出しにある、あるいはテーマへの枕の振り方が問題だなどと書いてある。これはこれで、その通りだと思う。事実、本書収録のエッセイを見ると、いずれも、なるほどこうやると大勢の読者の興味をいっぺんに引きつけることができるのか、と感心するものばかりである。
しかし、丸谷才一のエッセイを何回読みかえしても飽きないものにしているのは、むしろ、本題に入るとき、テーマを「問い」の形で立てることが多いからではないだろうか。もちろん、普通に読んでいたのではそうとは気づかない類いの偽装した「問い」である場合もあるのだが、とにかく、「問い」であることに変わりはない。この点が重要なのである。
なぜか。
「問い」という形でテーマを立てることで、エッセイは推理小説と同じ構造をもつようになるからだ。つまり、謎の探求となるのだ。おかげで、読者はどれほど話が横道にそれていっても、かならずそれが必要な脱線であると意識することができる。いいかえれば、横道や脱線は、推理小説における犯人当ての手掛かりのばらまきのようなもので、話がそれればそれるほどかえって本筋へと舞い戻るさいの落差の大きさに期待が高まるから、それ自体が楽しみにさえなる。この点が、いったん横道にそれると本当に「とりとめのない話」になってしまう凡百のエッセイと違うところである。「問い」のないエッセイだと、少しでも話が専門的になったり、議論が煩瑣(はんさ)になると、読者はそのとたんに読むことをやめてしまう。
しかし、ではテーマを「問い」によって切り出せば、だれでもよいエッセイを書けるのかといえば、そんなことはない。問題は、どのような種類の「問い」を立てるかということである。本書に例を取って具体的に見てみよう。
「硬と軟」軟球のギザギザは日本の偉大な発明ではないのか?
「ラの研究」「森繁ら参列」の「ら」は日本人の深層心理とどんな関係があるのか?
「西郷隆盛」西郷隆盛と武藏丸の類似に潜む意外な問題とは?
「水着の女」思春期に水着姿の女の写真に興奮しなかったのはなぜなのか?
「醍醐味」乳製品の話となると王様や天皇が出てくるのはどうしたわけか?
「カポネ会見記」欧米のインタビューアーは第一問をどう切りだすか?
「椅子について」なぜ日本人は椅子を取り入れなかったのか?
「日本ラーメン史の大問題」水戸光圀が食べたのが日本最古のラーメンか?
「牛乳とわたし」牛乳の大好きな私は日本人の例外なのか?
「三栄町遺跡」日本人は本当に明治以前は肉を食わなかったのだろうか?
これらのエッセイに共通しているのは、なんでまたそんな問いを発するのかと、普通の人ならいぶかしく思うようなところにあえて問いを立てているということである。ようするに、一見すると、どうでもいいような填末な疑問にしか見えないような問いである。それは、ばかばかしい問題をわざと大仰に論じて見せるスーパー・エッセイの手法と似ているように見えるかもしれない。ところが、これが大違いなのである。
というのも、丸谷流の問いの立て方というのは、刑事コロンボがつまらない差異にこだわることで真犯人を突き止めるのに似て、くだらない問いのように見せながら、最終的には真犯人、つまり日本や西洋の文化の本質に迫るような問いを用意するところに特徴がある。それは、樵(きこり)名人がデタラメに斧を当てているように見えて、そのじつ、一撃で木を倒せるようなスポットを選んでいるのに似ている。ここが丸谷流エッセイのポイントなのだ。寝転がって雑誌を読んでいる読者でも思わず興味をそそられるような問いで誘って、最後には、文化の核心に触れるような結論へともっていき、寝転んでいた読者に居住まいを正させる、これこそが丸谷流エッセイの極意なのである。
ところで、こうした話の運び方というもの、じつは丸谷才一の発明になるものではなく、かのアリストテレス先生に始まる弁論術(レトリック)の定法を踏まえたものなのである。
すなわち、話し手は、なによりも聞き手を不意打ちしなくてはならないというのがレトリックの基本である。つまり、聞き手の予想だにしていなかったような意外なところで問題提起を行う必要がある。これが話し手の興味を引きつけるレトリックの第一歩だ。先に例をあげた本書のエッセイの「問い」はすべてこのレトリックに則っている。
しかし、その反面、話し手は聞き手を安心させる努力も怠ってはならず、また最大公約数的な読者にたいして窓口を広げることが必要だ。できるだけ多くの聴衆に聞いてもらわなければ、弁論の効果はないからだ。
したがって、予想外の問題提起に先立って、枕の振り方に注意し、だれでもが知っているような話題から入ってゆくのがいい。枕は親しみやすく、問いは意外にするというのがレトリックの定石だ。丸谷流エッセイの書き出しはどれをとっても、このレトリックに忠実である。
話の運び方についても同じことがいえる。あまりに理詰めに議論を進めたのでは、論文や特殊研究ではないのだから、読者が窒息してしまう。適度の脱線・横道は、読者に息抜きを与えて、親しみを増す。それどころか、人から聞いた話とか本で読んだ話といった形で、この脱線・横道をうまく処理すれば、話に何重もの厚みをつけることができる。
げんに、丸谷流のエッセイの醍醐味はこの脱線・横道の部分にあるという人もいる。私もその一人で、脱線・横道を読むのが大好きだ。エッセイの巧拙は、脱線・横道をどれほどの余裕をもって行えるかにかかっている。
しかし、難しいのは、むしろ、脱線・横道からボートを回収してふたたび本船に戻るところだろう。これがへたな人は、話の運びがいかにもとってつけたようになるが、丸谷エッセイはこのタイミングが絶妙なのである。あるいは、こうした脱線・回収のうまさは、丸谷才一が、師匠であるジョイスのそのまた師匠であるホメロスあたりから受け継いだものなのかもしれない。
さらに、もうひとつ見逃せないのは、レトリックでいうテーゼ・アンチテーゼの対立をそれと気づかせないようなディスカッションに仕立てて、話の駆動力としてつかっている部分だろう。
ある人から非常におもしろい話を聞いた、あるいは目から鱗が落ちるような内容の本を読んだ、と、その議論を紹介することから始めて、次には、予想しうる疑問・反論をしっかりと用意しておく。これは、アンチテーゼが強力なものであり、なおかつテーゼがそれを打破できるほどの論拠をそなえていれば、論証はより強力になるという修辞学の論法をきっちりと踏まえたものである。もちろん、丸谷エッセイは、その論法が透いて見えるようなヤボは犯さないから、読者はただ文を先へ先へと読み進んでいくだけで否応なく説得されることとなる。
そして、気づいたときには、アッと驚くような結論にたどりついている。その一番いい例が「西郷隆盛」である。西郷隆盛と武藏丸の類似から始まった話が、最後には、幕末における西郷の呪術的カリスマ性が彼の「力士性」にあったという驚嘆すべき説に行き着き、こう結論が下される、
小説家が、東洋の哲人西郷隆盛ではなく、ドスンドスンと四股を踏んで大地を祝福する巨漢西郷隆盛(その前歯が一本欠けてゐる)を心に思ひ描いて書いてゆけば、明治維新といふ革命の叙事詩はもつと明確なものとして読者に迫るかもしれないのであります。
エッセイというのはレトリックだけでは書けないが、レトリックなしでは絶対に成立しないという、ヨーロッパでは当たり前の事実を教えてくれるのが、一見融通無碍に見える丸谷流エッセイなのである。
私は常々、国語教育では、「作者は何を考えているのですか」などという馬鹿げた問題ではなく、「この著者はどのようなレトリックで議論を進めているのですか」という問いかけをすべきだと思っているが、実情では、日本のエッセイにはこの種の問いに耐える構造を具えたものがほとんどない。丸谷才一のエッセイはその数少ない例外のひとつといっていい。
【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする