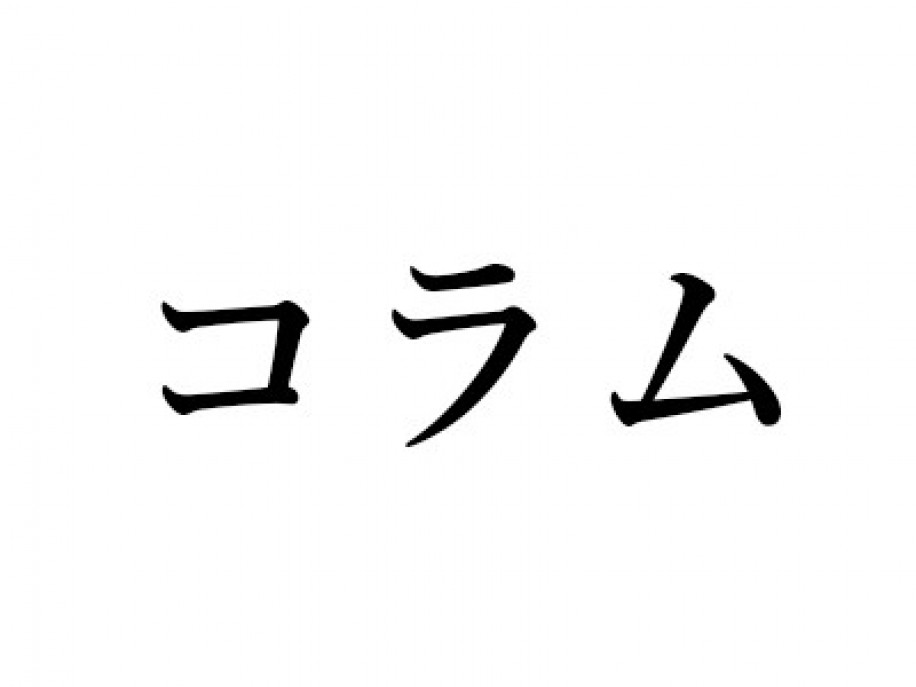書評
チャールズ・ブコウスキー『パルプ』クロード・シモン『アカシア』
ブコウスキーとシモンと「悪文」
ブコウスキーが流行っている。「流行っている」といったって『ソフィーの世界』みたいにメチャ売れしているわけじゃないが、「文学業界」としては異例のヒットということになるんじゃないだろうか。この盛り上がり方はどうも「幸田文」ブームに似ている。おばあさんの次は(不良の)おじいさんが旬だったのか(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1995年頃)。去年の暮に出版された遺作長編『パルプ』(柴田元幸訳、学研、筑摩書房)は、ブコウスキーらしさがもっとも出た傑作だが、冒頭におかれた「悪文にささぐ」というフレーズにはまいった。ブコウスキー全作品の秘密をたった一行で、それも自分で説明してしまったからだ。
ブコウスキーは「悪文」だ。しかし、この場合の「悪文」とは何だろう。
俺には才能があった。いまだってある。ときどき、自分の両手を見て、すごいピアニストか何かになれたのに、と思うことがある。なのに、いままで、この手でなにをしてきた? 金玉をぼりぼり掻いて、小切手を書いて、靴ヒモを結んで、トイレのレバーを押して、エトセトラ。俺は自分の手をムダに使ってきたのだ。それと頭も。
俺は雨もりに囲まれて座っていた。
電話が鳴った。期限の過ぎた納税通知書で受話器を拭いてから、手に取った。
「悪文」というからには、その対極に「名文」があるはずである。しかし、ブコウスキーが「悪文にささぐ」と、わざわざいっているからには、「名文」より「悪文」の方がいいと主張しているに違いない。では、「名文」とは何なのか。
『パルプ』とほとんど同じ頃、クロード・シモンの最新長編『アカシア』(平岡篤頼訳、白水社)が出版された。似ていないといって、ブツ切れで無味乾燥で下品そのもののブコウスキーの文章と、長く複雑にからみあって官能的なシモンの文章ぐらい似ていないものもない。
それは夏が尻ごみし、ぐらりと傾き、いわばみずからの重みで、自分に飽いたずしんとして有無をいわさぬ重苦しさでへたりこみはじめる時期で、日ましに一日が短くなるにつれ、夕べの訪れのたびにノスタルジーをともなった光の喪失感がやってきて、暑さが段階的にしずまり、背後にいままでそれ(夏)が膨張するもととなっていたあの怪物じみたなにかを置きざりにしたのだったが……
とまあ、これでもまだ一つの文章は終わっていないのだから、当然どこがブコウスキーかといわれそうだ。
訳者はあとがきの中で、こんなシモンの回心の言葉を伝えている。
「自分からいっさいの芸術という観念を追放した。……。あらゆるイデオロギーは失格となった。ヒューマニズムも終わりだ」
実は、この告白はブコウスキーがふだんいっていることとまったく同じなのである。芸術はダメ。ヒューマニズムなんかクソクラエ。芸術+ヒューマニズムの行き着くところこそ「名文」ではないか。ブコウスキーは無愛想すぎ、シモンは丁寧すぎる。どちらにしても極端なのだ。
極端では「名文」になれないのである。
しかし、こんな大問題を17字×86行で書けるわけないよな。詳しくはまた(といつも書いてるけど)。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする