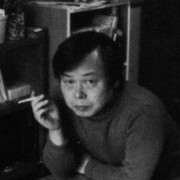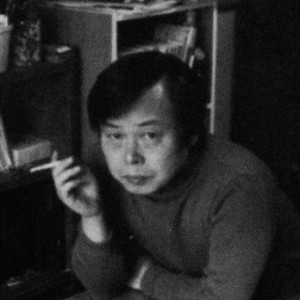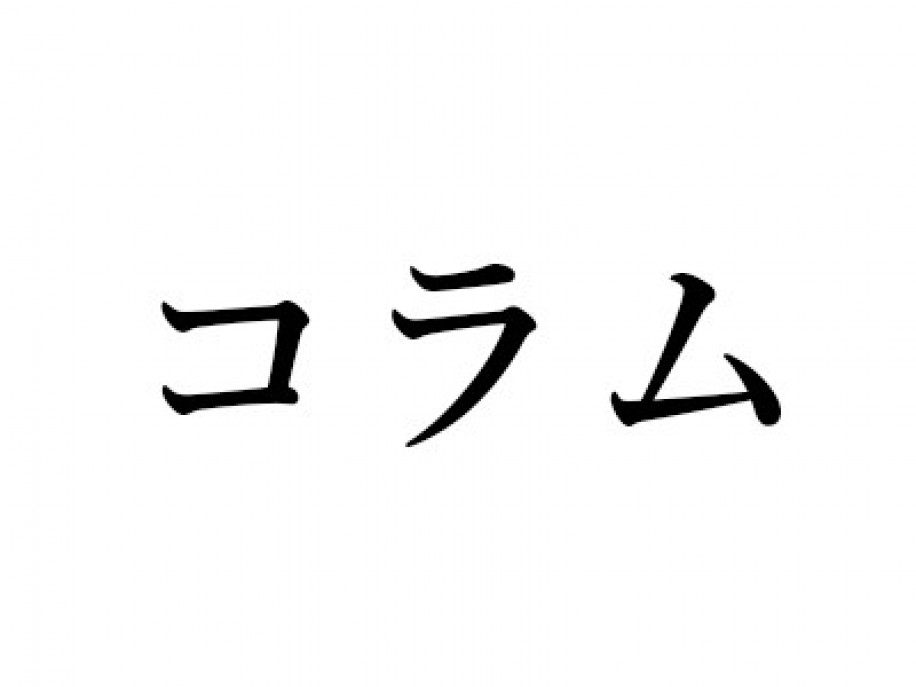書評
出口裕弘『ペンギンが喧嘩した日』(筑摩書房)、『ろまねすく』(福武書店)
捨て難い東京の片隅
いい大人が上野の動物園にふらりと入って、たまたまペンギンの喧嘩(けんか)を目撃する。ペンギンのくせにいやになまぐさい喧嘩沙汰(ざた)で、野生動物であるからには野性もエロティシズムもみどころとしてセットされているのに、管理飼育のせいでどこか人間みたいに卑小に衰弱している。といったほどの意味の表題作を含む、主に東京論がテーマのエッセイ集である。東京町あるきだから、寅さんの柴又にも銀座にも足をのばす。しかし柴又なら柴又で足がとまって、そこに入り浸りはしない。その足でまた田園調布にでかける。ことほど左様にたえず焦点が2つできてしまう都市論で、一例が「浜松町駅でポルトガルの掏摸を思い出した」。逆に「パリで東京を思い出」す文章もあれば、南イタリアのバーリやリスボンの裏町で少年期の失われた東京にめぐりあう話もある。時間の焦点が過去と現在の2つに割れたりもする。といって比較都市論ではない。2つの焦点のズレのなかに、つかの間、しかし永遠のひろがりにおいて姿をあらわす虚無、あるいは死の官能性ともいうべき瞬間を、卑俗な都市風物のなかに手さぐり足さぐりに、それこそなまぐさく探ってゆく。
3つの幻想短篇を組曲風に編んだ短篇小説集『ろまねすく』のほうは、同じ都市風景を抽象化して、野生が管理に地続きになってどこまでいっても堂々めぐりの迷路を、原因不明の有罪感を背負った男が逃走する物語。それが近未来社会の出来事のように薄気味わるいが、小説としては、日付も地名も消した空間のリアリティーを表現主義的な情念の連発で埋めてかえって遠近感が乏しくなる、この種の作の通弊がないではない。
『ペンギンが喧嘩した日』の、亡友渋沢龍彦にちなんだ冒頭の2作が圧巻である。友人の死に気落ちして、せめてもの供養に彼の少年時の遊び場を訪ねると、そこに「兎穴」がみつかる。中里のトンネルである。その向こう側にもこちら側にも死者と共有した戦前と戦後の同世代的記憶があり、トンネル内部には共有をこばむ暗黒がある。それを足と推論によって探索する、元少年の冒険。これに集中の2篇の蕪村論をあわせ読むと、管理社会へのことさらなクリティシズムよりは、恍(ほう)けたような無心やポエジーによる超越のほうが歩幅が長いことの道理が、ごく自然に納得されて、あらためて東京の片隅もすてたものではないと悟らされるのである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする