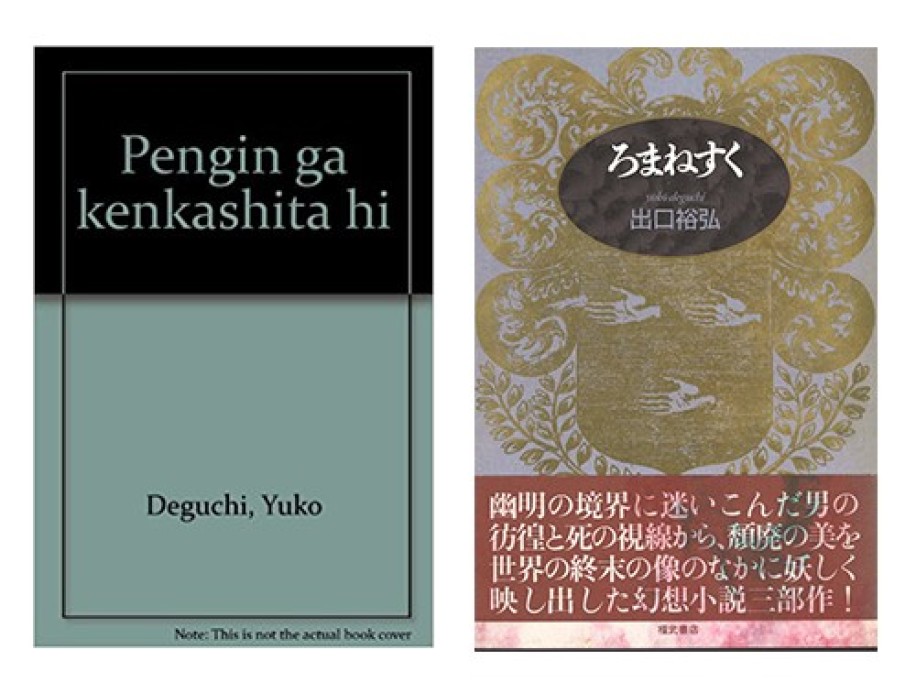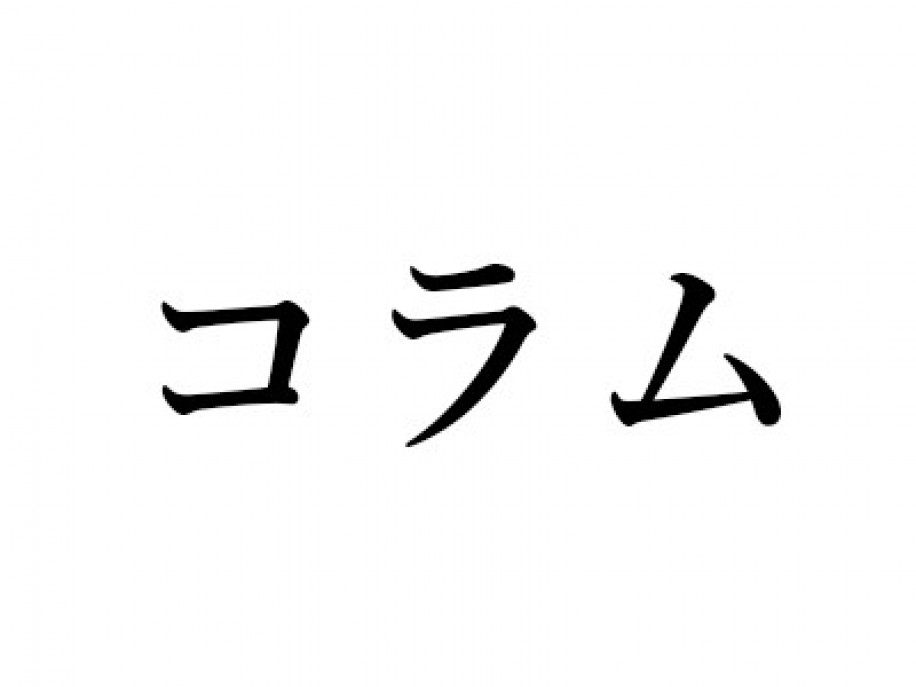書評
『辰野隆 日仏の円形広場』(中央公論新社)
フランスの意味を問う
明治以来百三十年、日本にとってフランスとはなんだったのか。ワインを筆頭とする食材はもとより、文学、美術、映画、思想にオートクチュールまで、わが国における「憧憬」の大半を占拠しているフランスの力は、時の首相からウサギ小屋住まいと揶揄されても、太平洋のかなたで核実験が強行されても、いっこうに衰える気配がない。本書は、この不思議な国に魅了されつづけている日本の近代を、ひとりの明治男を通してたどり直そうとする卓抜な文化史であり、興味あふれる評伝である。
男の名は、辰野隆(ゆたか)。東京駅を設計した辰野金吾の息子にして東京大学フランス文学科の創設者である。一高の同級生に谷崎潤一郎を、教え子に小林秀雄と太宰治を持ち、驚くべき包容力で幾多の後進を育てた人物だ。
大正十(一九二一)年にフランスへ留学すると、為替相場の恩恵にあずかって、美食に芝居に音楽にと、彼はなに不自由ない暮らしを堪能する。苦労話は、ひとり自分の胸にしまって、周囲を喜ばせる前向きの言葉しか口にしない、すべてにおいてプラス思考の人間でもあった。
辰野には、だから、「専門分野」など必要なかった。強烈な好奇心をもってあらゆる時代の文学に親しむ懐の深さが、研究者だけでなく、詩人や批評家や小説家を教え子に引き入れる土台となって、一時期の東大仏文の、独特の雰囲気をつくりあげたのである。著者自身、辰野が残したそのにおいに引かれて仏文を志したのだった。
大人(たいじん)への敬愛とその不在の意味を、実体験もまじえて縦横に語る本書の構成は、話題の道路が放射状に延びていく円形広場そのものだ。すべてが矮小化した今日、もはや辰野隆のような人物は出てこないだろう。しかし嘆くばかりでいいのかどうか。軽やかな文章と裏腹に、その問いはずいぶんと重い。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
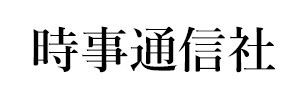
時事通信社 1999年10月
ALL REVIEWSをフォローする