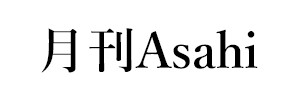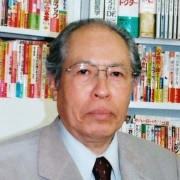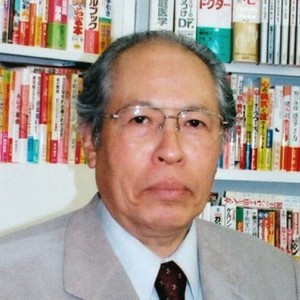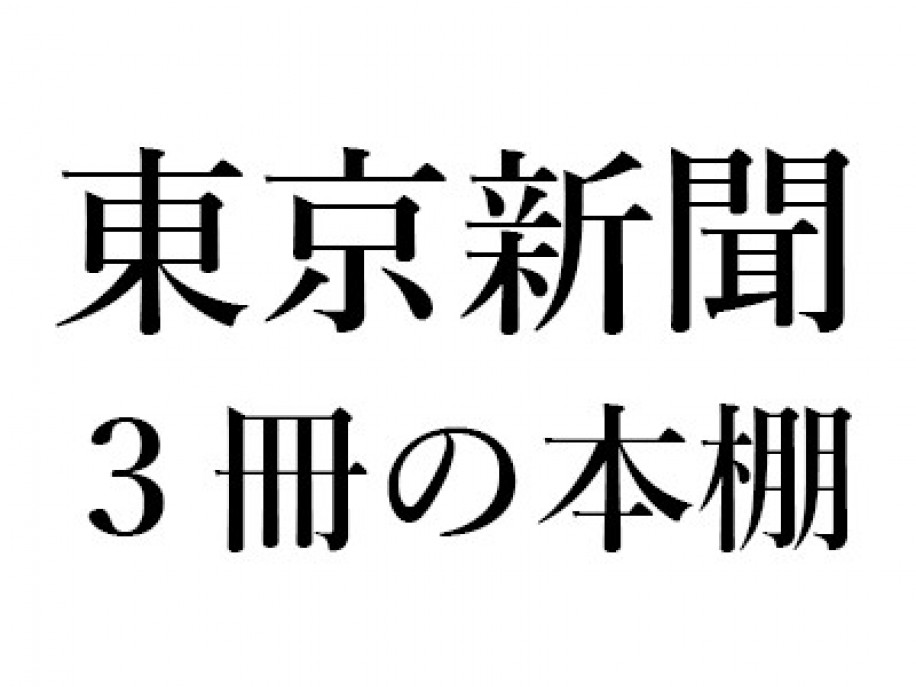コラム
谷崎潤一郎『文章読本』(中央公論新社)、川端康成『新文章読本』(新潮社)、三島由紀夫『文章読本』(中央公論新社)、丸谷才一『文章読本』(中央公論新社)ほか
新入社員・学生のための文章読本
新入社員の文章が全然なっていないという批判を耳にする。「メディア環境の多様化と文章力は反比例する」といいたくなるほど、最近の学生や新入社員の文章表現力には落胆させられることが多いようだ。このようなときに、文庫の書棚で文章入門書の類が版を重ねているのは、一見奇異に似て、むしろ当然の現象といえよう。明治から昭和初期までの文章論、文章指南書では虚子、武島羽衣、菊池寛らのものが知られているが、昭和九年(一九三四)に出現した谷崎潤一郎『文章読本』(中公文庫)は、当時における急速な口語文の乱れ、外来語の氾濫を背景に書かれたもの。「語彙が貧弱で、構造が不完全な」日本語の弱点を逆手にとり「陰翳」と「含蓄」に富んだ表現力を引き出すという発想が今日なお新鮮である上、伝統的な日本語と欧文脈との結合に現代日本語の課題を見出そうとする意図が、後の諸家の文章読本に及ぼした影響は少なくない。
戦後はまず泉鏡花や佐藤春夫など同時代作家の文体を比較検証した川端康成『新文章読本』(新潮文庫)が現れたが、どちらかといえば鑑賞に終始。ついで小説中心に多彩な文章技巧を解明した三島由紀夫『文章読本』(中公文庫)は「小説を深く味わう読者」のために、自己の小説作法を開陳したという性格をもつ。
鷗外、漱石から井上ひさしまで、近代百年の文章の変遷を跡づけた中村眞一郎の『文章読本』(新潮文庫)についで、昭和五十二年に出現した丸谷才一『文章読本』(中公文庫)は、以上の諸家の例を踏まえながら、一層幅広い視点から日本語の特質を解明、文章上達の秘訣を説いた、このジャンルでの決定版。「現代日本で文章を書くのがむづかしいのは文明の性格ないし状況にかかはる」という認識も、谷崎以来の問題意識を正確に継承したものといえよう。
文学中心の文章観を解体した井上ひさし『自家製文章読本』(新潮文庫)は、「話すように書くな」「オノマトペ(擬音語、擬態語)を避けることはない」など常識破りの提言により、価値意識の混乱した現代における文章を考える。なお、作家による文章読本のエッセンスを集めたものとして吉行淳之介選『文章読本』(福武文庫)がある。
文学史はともかく、これから小説や随筆を書きたいという人には、まず鶴見俊輔『文章心得帖』(潮文庫)、多田道太郎『文章術』(同)がある。いずれも文章塾での講義だけに受講者の具体例を引用しつつ、問題点を指摘している。
白井健策『文章トレーニング』(ちくま文庫)は、現実を新しい眼で観察し、そこから得た主題を平明達意の「自然体」で綴る方法を説いたもので、肩の力を抜いた軽快さがある。同じように平明な文体で知られる外山滋比古の『文章を書く心』(福武書店)は、「段落と段落の間の論理は、少し飛躍していたほうがよさそう」とか「題をつける練習をしていると、言いたい筋をとらえながら書くことができる」「推敲のさいには声を出すようにする」といったコツが、エッセイの中にちりばめられている。
国語学者の平井昌夫による『新版文章を書く技術』(現代教養文庫)は、書く前の用意から主題の出し方、どう述べるか、よい段落の条件、表現を強める条件、書き終わりの余韻、符号の使い方にいたるまで、作文の技術を網羅した教科書で、初版刊行いらい二十八年間に三十二刷を重ねている。さすがに用例は多少古さが感じられるようになったが、学生には好個のテキストといえよう。
このほか野間宏の『文章読本』も働く者の文章を例にしているという点で特徴のあるものだが、文庫では絶版となり、現在は新書判の「レグルス文庫」に編入されている。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする
初出メディア