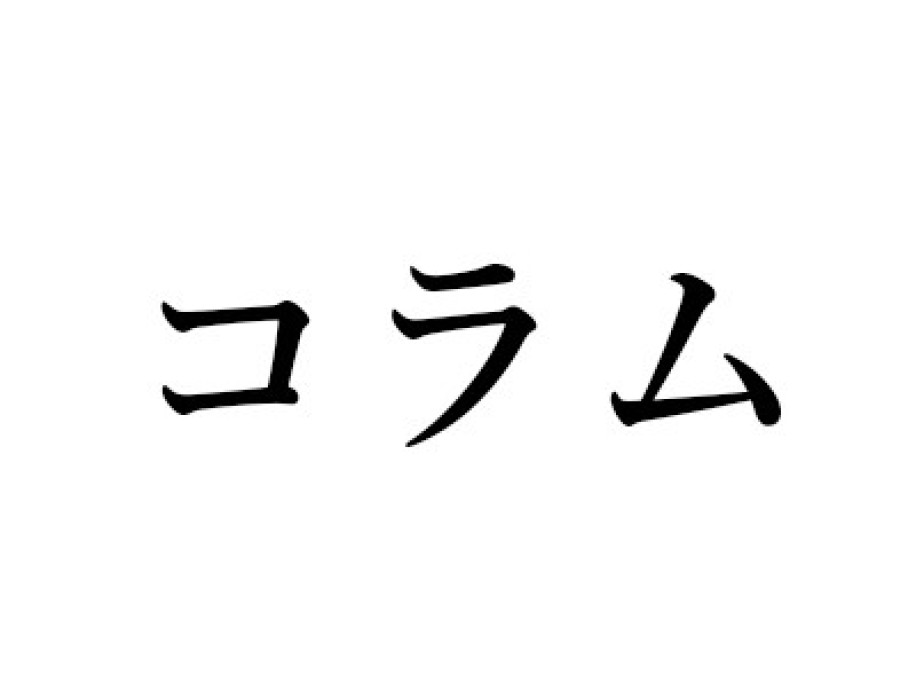書評
『現代語訳 好色五人女』(河出書房新社)
「情」を動かす、恋の哀れみ、切なさ
西鶴の好色物を吉行淳之介と丹羽文雄が現代語に訳しているというだけで、相乗的に色香が濃くなる。本著には、「五人女」の他に「好色一代女」と「西鶴置土産」が収録されているが、五人女を吉行が、一代女を丹羽が、さらに置土産を吉行が訳していて、本著自体が古典の趣き。
性表現も性の自由も制約が無くなってきたおかげで好色への関心も薄れ、それはもはや江戸風俗の中でしか存在しないのだと実感させられた。「好色」を「恋愛」にすりかえてきた近代化西欧化は、精神に対する肉体の矮小(わいしょう)評価をもたらし、文学から下世話な世界を排除してきた歴史でもあると、あらためて思う。
それにしても登場人物は、魅力的な肉体を持っている。肉体の描写は実は少なく、あっても単純なものだが、リアルに目に映るのは、感性が生きているからだろう。
「五人女」は、当時世間の関心を集めた痴情事件を小説として書き留めたものだが、今でいえばワイドショウで取り上げられる話題の人だったのかも知れない。賛美されたり真似されては困るので、悲劇で終わった最後に「悪事は天罰を逃れられぬものである、あなおそろし」というような、感慨が付け加えられているのは世間やお上への配慮か。
恋に殉じて罰せられる者は、哀れみや憧(あこが)れ、同情や軽蔑の対象として、いつの時代もエンターテイナーである。女性週刊誌が読者の近づけない「憧れ」と、自分はその悲惨さを免れていることで安堵を覚える「悲劇」の両方を掲載すれば、ともかく当たる、と言われているのと同じに、当時も西鶴の成功は、決して上等とは呼べない庶民の心情に支えられていたに違いない。
小説のタイトルに女性の名前が使われ、五人女とされているけれど、主人公は女性とは言えないものもある。「お夏清十郎物語」は、モテ男の清十郎にウエイトがかけられているし、「おまん源五兵衛物語」は、唯一のハッピーエンドだが、こちらも男の浮気性がおかしみとともに、生き生きと語られていて、おまんより彫りが深い。この源五兵衛という男はもともと同性愛者で、若衆二人とさんざんトラブルがあった後に出家した身だが、それと知ったうえで、おまんは若衆に化けて押しかけ、床のなかで女だとばれる。それでも深い仲になる。あっちの色もこっちの色も好き。「おもえば、女の躯(からだ)には誰も厭(いや)といえない落し穴がある。お釈迦さまでも、片足くらいは踏込んでしまいかねない」と西鶴のひとこと。「お釈迦さまも大目に見て下さるだろう」とか「文殊さまは師利(しり)菩薩というからには、男色の道だけにご理解があって、女色のほうは一向にご存知ないのでしょうよ」などと、仏法世界も痛快に切られている。
源五兵衛のようないい加減な男と、男装してまで男の床に入り込む冒険女が、最後に使い切れないお金を手に入れて、どうすればお金が減ってくれるかと悩み、江戸や京、大坂の遊郭の太夫を全部請け出してもまだ駄目、と嘆く最後に、西鶴の型破りの開放性がある。悲劇のパターンを壊して、因果応報の転結から遁走(とんそう)している。
恋愛(色事)の主人公は、見目うるわしい女が条件だが、同時に男も美しくなければならず、この美しい男は、男にも愛される構図になっている。
当時の色事は、かなりの部分、男同士で占められていて、またそれが、世間で容認されていたことが良くわかる。女は、女だけを恋敵にするのではなく、男とも闘って恋の勝利者にならなくてはならない。
わびさびの元祖芭蕉が男色の世界に片足を置いていたと知ったときは、いささか異様に感じたけれど、ごくありふれたことでもあったのだろう。
男色がここまで大手を振ってまかり通っていたのは、男社会の権力構造が確固たるものとして存在した証であり、知性や才能も男色の潤滑油だったことがわかる。
それに較(くら)べて女の恋は、遊郭の中か死を覚悟の道行きか、いずれにしてもあまり幸福な色合いはなく、死んだあとで物語として人々のあいだで伝えられる運命、とはいうものの、哀れみや切なさは「情」の中に残された。
恋に狂って火付けを犯してしまうお七の相手吉三郎には、美青年ゆえに衆道の契りを交わした男がいて、西鶴は最後に「さてもさても、男色女色入り乱れての恋であり、あわれな話である」と書いているがその部分はいまや理解の外、純愛部分だけが抽出された。しかし火刑に処せられたお七が当日着ていた郡内縞(ぐんないじま)の小袖の切れ端まで、世間の人は拾い求めて、孫子の代までも物語の種にしようと思った、というのは、いかになんでも小袖の切れ端は無理。西鶴の筆が走ったにしても、社会の弱者であるお七への世間の「情」が、書かせた一文だったのではなかろうか。
ALL REVIEWSをフォローする