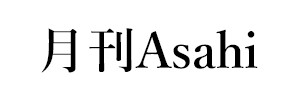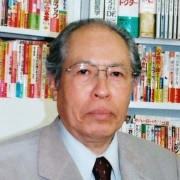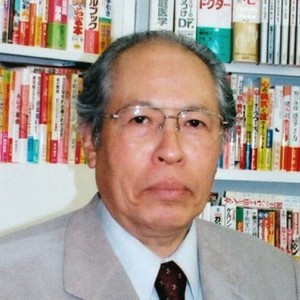コラム
小宮豊隆『夏目漱石』(岩波書店)、江藤淳『決定版夏目漱石』(新潮社)、夏目鏡子『漱石の思い出』(文藝春秋)ほか
文庫で読める漱石のすべて
夏目漱石の作品は各社とも文庫本のロングセラーの上位を占めているが、このほど岩波文庫の『漱石作品集』全二十三冊が刊行された(ALL REVIEWS事務局注:本コラム執筆時期は1991年頃)。従来から出ていた『吾輩は猫である』以下の全作品に、新たに『漱石日記』、『漱石書簡集』、『漱石俳句集』の三点を加えて実質的な全集としたもので、これによりほとんど全著作が文庫で読めることになった。
漱石の文庫判全集としては、すでに小説中心のちくま文庫判があるが、評論、日記なども付した岩波版が有利になった。注も懇切ていねい。この上はふだんに全書目を絶やさないようにして欲しいものだ。
漱石の評伝として基本的なものは小宮豊隆の『夏目漱石』全三冊(岩波文庫)だが、弟子の立場から美化されすぎているというのが専らの評判。たしかに「則天去私」などというあいまいな概念で漱石の思想をくくることには無理があろう。江藤淳の『決定版夏目漱石』(新潮文庫)は、そのような神話や感傷の一切を洗い流し、明治時代の日本の現実を鋭くとらえた文学として再評価をくだしている。この文庫判にはほかに「登世という名の嫂」「鴎外と漱石」など著者の漱石論考十六篇が収められている。
角川文庫から出ていた漱石の妻鏡子の『漱石の思い出』も、漱石を理解するための資料として無視できない。たとえば漱石は体調がよくないときには大きな字を書いていたのが、だんだん重苦しい靄が晴れてくるにつれ、ふり仮名のように小さな字になるといったエピソードが紹介されている。彼女は前記の小宮によって悪妻と断定されていらい、評判がよくないけれども、漱石の次男伸六の晩年の著書『名作の旅 夏目漱石』(保育社カラーブックス)はこれを否定して、「女嫌いの漱石が、自分の細君を特別視するわけもなく、正常な時には、妻の女としての馬鹿さ加減を達観するくらいの常識は持ち合わせていた」としている。この感覚は今日では通用しにくいとしても、全体としてユニークな漱石論となっており、文庫本の穴場といえよう。
小宮と並ぶ漱石の弟子内田百閒の『漱石先生雑記帖』(河出文庫)は、漱石との出会いを綴った「明石の漱石先生」ほか三十篇の短い文章を収めているが、とくに「漱石先生臨終記」は心うたれる。ただし百閒は漱石に気安く口をきけなかったという。同じく弟子の中勘助による「夏目先生と私」という回想が『中勘助随筆集』(岩波文庫)に載っているが、彼もまた交際下手から漱石に疎遠感を抱き続けた人であり、そのため漱石から「彼と対していると真黒な幕が垂れているような気がする」といわれたとされ、中自身もそのように記しているが、近年研究者により中の誤解と判明した。
漱石を目して小説が下手とか、女性が描けていないとかの批判もあるが、明治文化を体現した知識人として、これほどのひろがりを持つ人は、ほかに鴎外あるのみ。そのような文化史上の漱石像を展開した一つの例として、平川祐弘『漱石の師マードック先生』(講談社学術文庫)がある。漱石が一高時代に英語や歴史の授業を受けたマードックは、スコットランドの歴史学者で、未完に終った『日本歴史』という大著がある。平川はこのマードックというあまり知られていない学者の生涯を克明に追うことにより、彼と明治日本ないしは漱石という東西両文明の出会いの意義を跡づけていく。たいへん奥行きのある文明論で、文庫化を喜びたい。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする
初出メディア