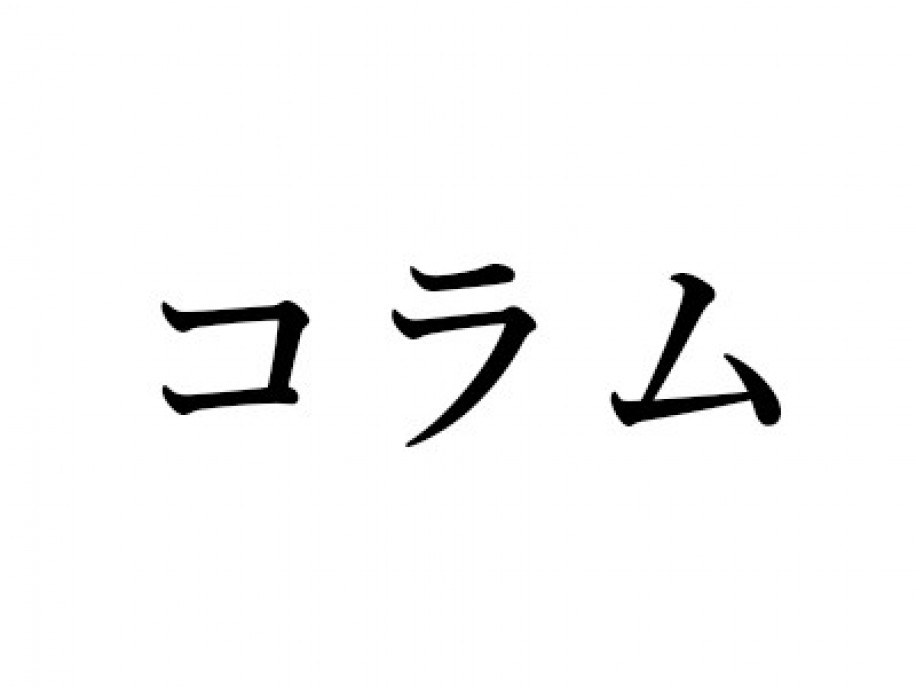書評
『神曲【完全版】』(河出書房新社)
『神曲』を最初に読んだのは、15歳のときだった。文学全集のなかに入っていたものを、さしたる知識もなく読み出したのだが、これは滅法面白かった。なにしろ地獄廻りの記録である。鬼の隊長が家来どもを叱りつけたあとでオナラをしたとか、罪人の誰某がどろどろのアスファルトのなかで悶え苦しんでいるとか、まるで作者が自分の眼で見てきたことであるかのように書かれているではないか。なまじ文学の厳粛なるお手本だなどと考えずに読んだことが、よかったのだと思う。もっとも中学生には地獄編がやっとで、ベアトリーチェと再会して天国に無事到達したダンテが、カトリックのややこしい教義問答を始めるあたりは理解できず、途中を飛ばしてしまったことを記憶している。
イタリア語を齧ったこともあって、現在わたしの家には原書と翻訳、それに朗読のCDなどを含めて、20種類くらいの『神曲』が並んでいる(というより、本棚のあちらこちらに乱暴に差し込まれている)。翻訳は生田長江が病床で訳した古色蒼然たる訳もあれば、映画評論家の北川冬彦がカメラアイの発想から自由に翻案したものまで、さまざまである。もちろん最初に読んだ平川祐弘訳も、全編を仏教の語彙に置き換えた寿岳文章訳もある。訳し方の違いを論じるだけでも、おそらく比較文学の論文が書けてしまうことだろう。原書はデ・キリコのエッチングを頂いた豪華本からペーパーバックまで。もっとも新しいコレクションは、永井豪による全編の漫画化である。この漫画化は世界初の試みであるらしく、知り合いのイタリア人が感激して買って帰った。
わたしがとりわけ愛着を覚えているのは、そのなかでももっともポータブルなもので、大きさはなんと日本の文庫本の半分程度しかない。1911年にミラノのウルリコ・オエプリ書店から刊行されたものの復刻で、中表紙に「一般の読者ならびに学生用」とわざわざ銘打ってある。推測するに、どうやら学校の副読本として使用されることが多かった版かもしれない。薄い紙を用いているせいか、地獄、煉獄、天国の3編を完全に収め、600頁に近い分量をもちながらも、厚さはわずか12ミリ。しかも重さなどほとんど感じない。
もう大分前のことになるが、フィレンツェに語学の勉強に行っていた夏に、アカデミア美術館の近くの書店で、50冊ほど美術書を購入し、船で送ってもらう交渉を店の主人としていた。そのとき何気なくレジの脇の絵葉書用のラックにいっしょに置かれていたのが、この書物である。久しぶりに手に取ってみると、ところどころに傍線が引いてあったりして、なんだか気恥ずかしい。「彼らのことは語るな、ただ見て過ぎよ」とか「不幸のさなかにあって幸福なる日々を思い出すほどに、大いなる悲しみはなし」といった詩句のことである。
この小さな本のことを人と話したことは、これまでに一度しかない。亡くなられた須賀敦子さんがわたしの家に見えられたとき、話題が旅行のことになった。「わたしは飛行機に乗っていてちょっと怖いなと思うことがあると、勇気を出すためにダンテを読むのよ。ポケットに入るくらいの、便利な本があっちにはあってね」と、彼女はいった。いつかそんな風にスラスラと『神曲』が読めればいいなあと、わたしはその言葉をうっとりと聞いていた記憶がある。
【この書評が収録されている書籍】
イタリア語を齧ったこともあって、現在わたしの家には原書と翻訳、それに朗読のCDなどを含めて、20種類くらいの『神曲』が並んでいる(というより、本棚のあちらこちらに乱暴に差し込まれている)。翻訳は生田長江が病床で訳した古色蒼然たる訳もあれば、映画評論家の北川冬彦がカメラアイの発想から自由に翻案したものまで、さまざまである。もちろん最初に読んだ平川祐弘訳も、全編を仏教の語彙に置き換えた寿岳文章訳もある。訳し方の違いを論じるだけでも、おそらく比較文学の論文が書けてしまうことだろう。原書はデ・キリコのエッチングを頂いた豪華本からペーパーバックまで。もっとも新しいコレクションは、永井豪による全編の漫画化である。この漫画化は世界初の試みであるらしく、知り合いのイタリア人が感激して買って帰った。
わたしがとりわけ愛着を覚えているのは、そのなかでももっともポータブルなもので、大きさはなんと日本の文庫本の半分程度しかない。1911年にミラノのウルリコ・オエプリ書店から刊行されたものの復刻で、中表紙に「一般の読者ならびに学生用」とわざわざ銘打ってある。推測するに、どうやら学校の副読本として使用されることが多かった版かもしれない。薄い紙を用いているせいか、地獄、煉獄、天国の3編を完全に収め、600頁に近い分量をもちながらも、厚さはわずか12ミリ。しかも重さなどほとんど感じない。
もう大分前のことになるが、フィレンツェに語学の勉強に行っていた夏に、アカデミア美術館の近くの書店で、50冊ほど美術書を購入し、船で送ってもらう交渉を店の主人としていた。そのとき何気なくレジの脇の絵葉書用のラックにいっしょに置かれていたのが、この書物である。久しぶりに手に取ってみると、ところどころに傍線が引いてあったりして、なんだか気恥ずかしい。「彼らのことは語るな、ただ見て過ぎよ」とか「不幸のさなかにあって幸福なる日々を思い出すほどに、大いなる悲しみはなし」といった詩句のことである。
この小さな本のことを人と話したことは、これまでに一度しかない。亡くなられた須賀敦子さんがわたしの家に見えられたとき、話題が旅行のことになった。「わたしは飛行機に乗っていてちょっと怖いなと思うことがあると、勇気を出すためにダンテを読むのよ。ポケットに入るくらいの、便利な本があっちにはあってね」と、彼女はいった。いつかそんな風にスラスラと『神曲』が読めればいいなあと、わたしはその言葉をうっとりと聞いていた記憶がある。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする