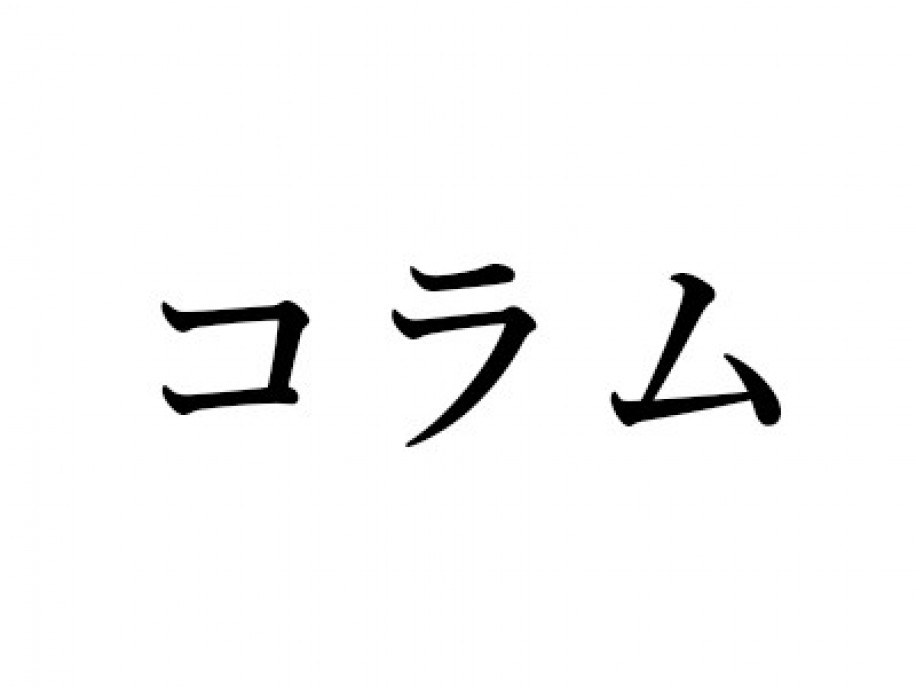書評
『漱石とその時代〈第3部〉』(新潮社)
『漱石とその時代』を読みながら、いろいろ考えた
「漱石ブーム」といわれる中で、真打ち登場といってもいいのが江藤淳の『漱石とその時代 第三部』(新潮社)。今回は『吾輩は猫である』の執筆から『坊つちやん』や『野分』『二百十日』を書いたあたりの漱石が対象となっていて、文学論や作家論としてももちろんためにはなるのだが、ぼくは例によって、読みながら本筋とは関係のないことばかり考えていた。
たとえば、
ここで冗談めいた暗号として付け加えて置けば、実際に猫踊りを踊って見せた実在の猫が、「全身黒ずんだ灰色の中に虎斑(とらぶち)があ」って、「一見黒猫に見える」猫であったということも、なにがしか漱石の興趣を惹いていたのかも知れない。
というところを読んでいて、わが家の前に不意に姿を現し、いまでは「外猫」としてエサをやっているばかりか、出産してしまった子猫五匹の世話(四匹は友人に引き取ってもらい、体の弱い一匹はいまも入院中)までしてやった野良ちゃんも、まさに「全身黒ずんだ灰色の中に虎斑」で「一見黒猫に見える」ということは、もしかしたら『吾輩は猫である』の直系の子孫じゃないかしらん、実は「広告批評」という雑誌に連載(いまは休載)している「タカハシさんの生活と意見」という小説では「吾輩」という名前のしゃべる猫を主人公にしているのだが、やっぱり縁があったんやなあとうっとりしたり、あるいはまた、
正宗白鳥の『自然主義盛衰史』によれば、「当時の青年文学者」は、藤村が「信州の山を下つて東京の郊外住ひして、貧乏生活をしながら長篇小説を書いてゐるといふ噂」に、みな少からぬ関心を寄せていたからである。田山花袋は、その「噂」から藤村の新作の眼目を臆測して、「羨望に堪へぬやうな口吻」を洩らしていた。そして、『破戒』が世に出ると、漱石のみならず「文学的熱意に富んだ文壇人」は、「争つてこれを読」んだのであった。硯友社の末流小栗風葉すら、「早速一本を購つて、熟読玩味して首をひねつた」と伝えられていた。
というところを読んでいると、いま時、他の作家から新作が心待ちにされているような作家がいるだろうかと頭をひねったり、いやいや作品はあるかもしれないけれど、作家の方が他人の作品にぜんぜん関心がなくなっちゃったんじゃないか世も末だねえと溜め息をついてしまうし、
つまり漱石は、四百字詰原稿用紙に換算して二百三十枚ほどになるこの小説(高橋注。『坊つちやん』)を、僅々十日前後、二週間以内のあいだに書き上げたのである。
とか、
漱石は、実質的には交通遮断が解除された九月七日以降、僅々両三日のうちに『二百十日』を書き上げたことになる。
というところを見ては、はやーいと感心したりするのだが、やはりこの本を読んで誰もが驚くのは、漱石の(あるいは森田草平の)どれもみんな長くて、きわめて真剣な手紙ではあるまいか。そんな手紙、最近書きました? 書いてないよなあ。電話もいいが、たまにはきちんとした手紙も書きましょうね。それから、すっかり忘れていたけど『二百十日』には九行の間に「気違」という言葉が五回(内「気狂」一回)も使われているところがあって、いまのこ時勢では差別用語として禁止されちゃいますよと漱石に言ったら、さぞやびっくりするだろう。まあ、ぼくでもびっくりするけれど。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする