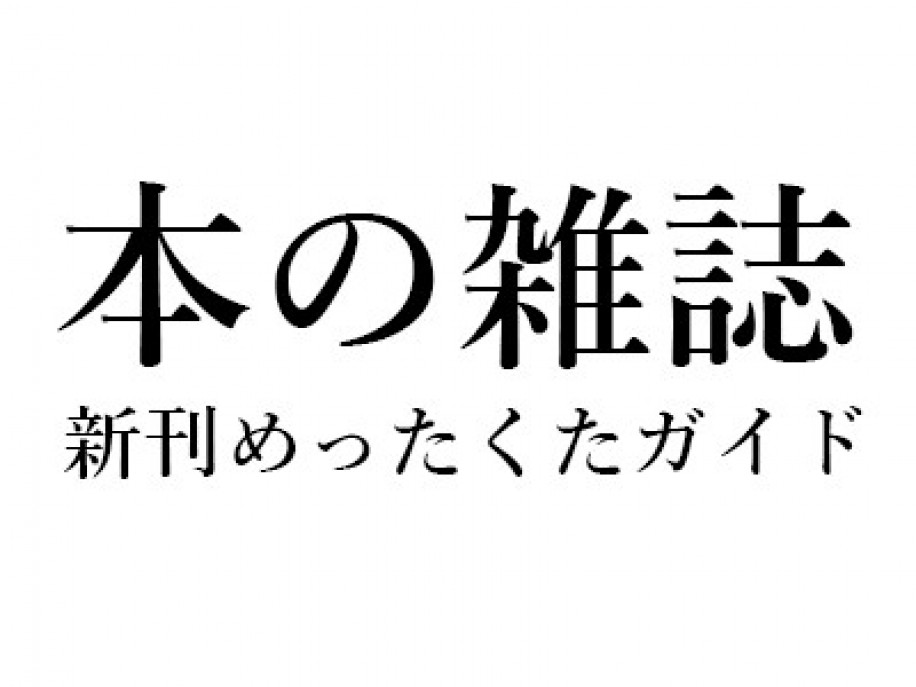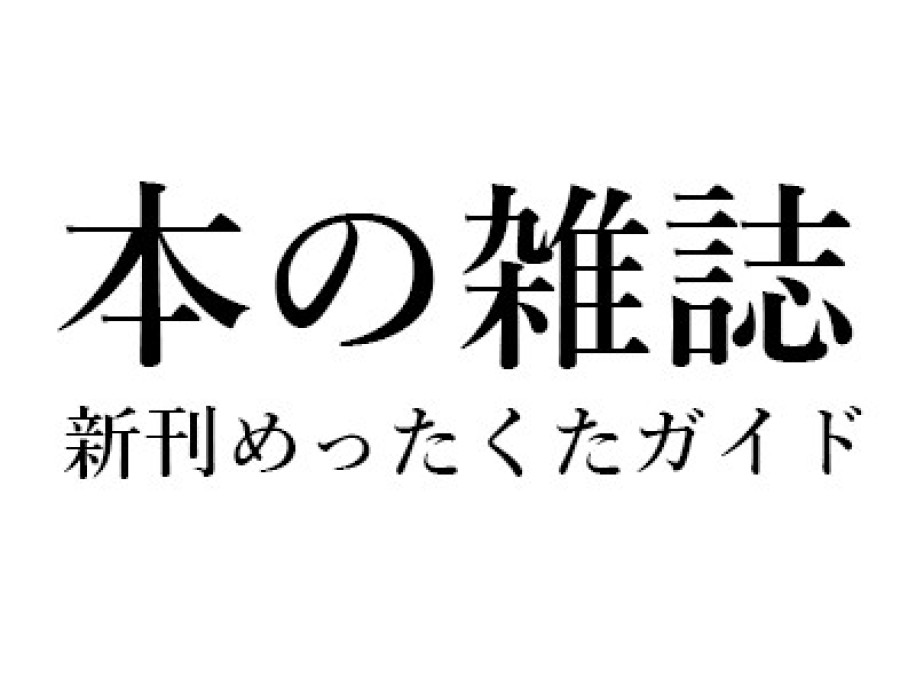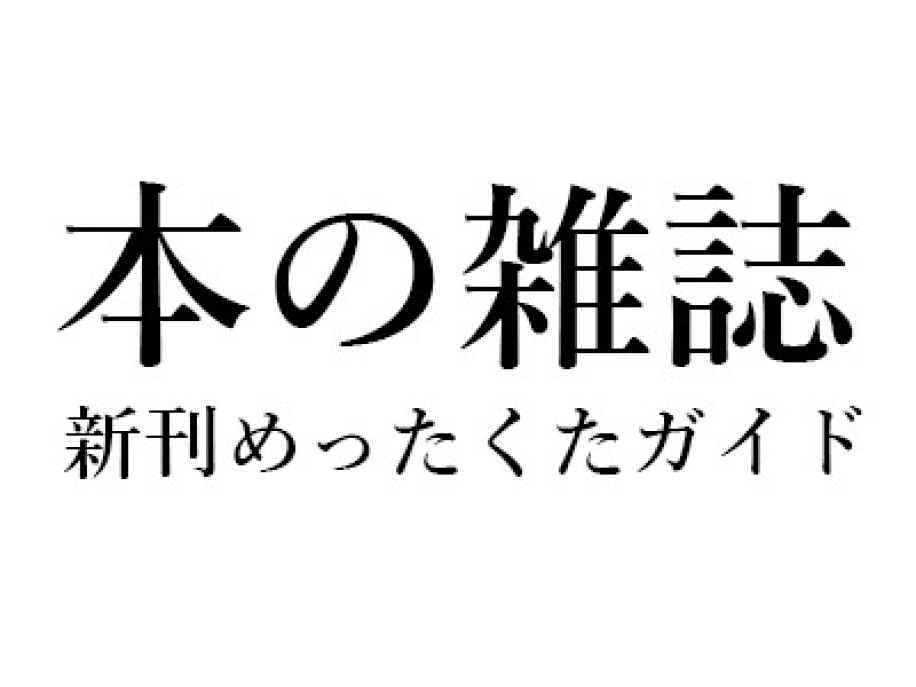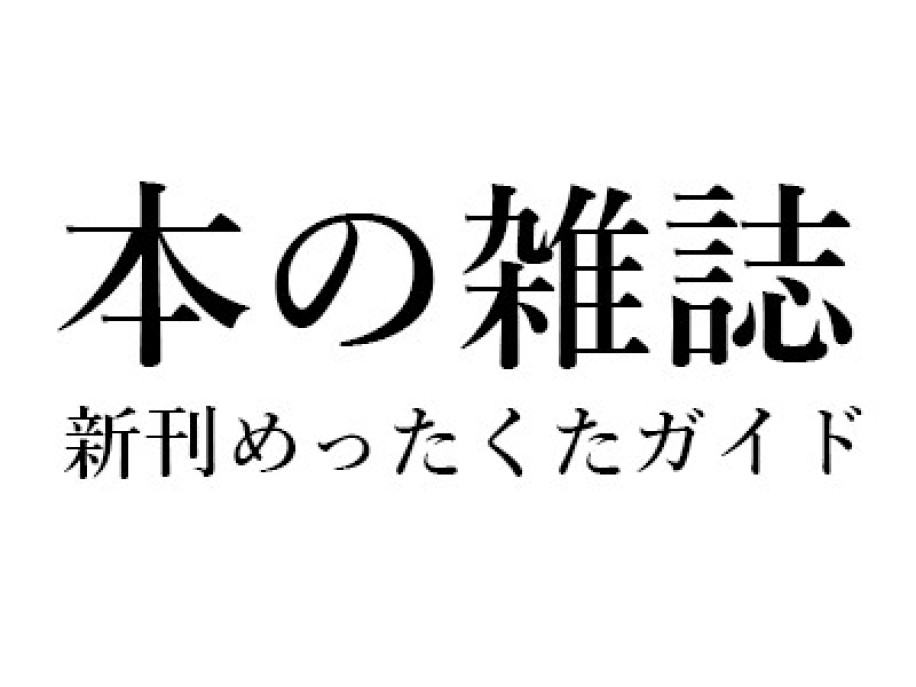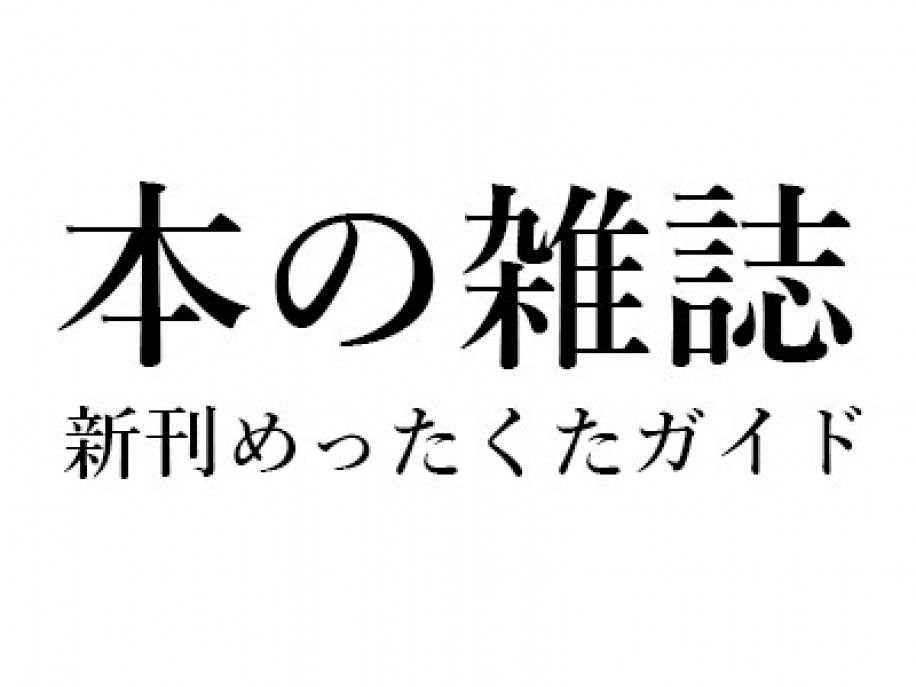読書日記
野阿梓『ソドムの林檎』、川又千秋『反在士の指環』、上遠野浩平『わたしは虚夢を月に聴く』ほか
日本SF史上最強のヒロイン、姉川孤悲のかっこよさに降参!
川又千秋『反在士の指環』(徳間デュアル文庫)★★★のカバーを見て愕然とした中年SF読者は多いんじゃないかと思う。これは、著者の初期代表作『反在士の鏡』に単行本未収録の短篇二篇と新作エピローグを加えた《反在士》シリーズ完全版。『反在士の鏡』と言えば、オレの中では七〇年代日本SFの最先端だったのに、超人ロックみたいなこのカバーイラストはいったいなに? 責任者出てこい!しかし、二十年ぶりに再読してさらに愕然としたのは、このイラストが正しかったこと。燃えるオレンジの髪をなびかせた美少年、その名はライオン。ふ〜ん、こいつが反在士だったのね。キャラなんかすっかり忘れてたよ。鮮烈に覚えてるのは、純粋鏡面を通過する超光速航法アリス・ドライブとか、銀河をゲーム盤に見立てて果てなき戦争を続ける〈紅后〉と〈白王〉とか。ところが、いざ現物を読み返してみると、きらびやかでかっこいいイメージと裏腹に、ディテールはろくすっぽ書かれていない。今の目で見ると、これって〝アイデアとイメージは抜群だけどキャラ立ちとプロットが弱いライトノベル系スペースオペラ〟だよね。しかし逆に考えると、『反在士の鏡』が七〇年代日本SFの最先端だったんなら、昔から日本SFのカッティングエッジはライトノベルだということになる。
実際、デュアル文庫からこれと同時に出た上遠野浩平の新作『わたしは虚夢を月に聴く』★★★☆は、『反在士の鏡』の直系の子孫。虚空牙、相克渦動励振原理、虚空間力場などなどの造語群で想像力を刺激する(が詳しい説明は与えない)手法や、現実/虚構の反転というモチーフは、『反在士』的な文系本格SFのそれと見事に重なる。というか、今の中高生読者は、高校生だったオレが『反在士』にハマったように上遠野浩平にハマり、めくるめくセンス・オブ・ワンダーを味わっているのかも。発表から二十年が経過した『反在士』は、今はもうあまりかっこよく見えないが、その〝かっこよさ〟の精神はライトノベルSFの最先端に受け継がれている。
もっとも、こうした〝かっこいいSF〟が、今やライトノベルの専売特許なのかと言えばそんなことはない。〝革命的武装小説集〟と銘打つ野阿梓久々のSF作品集『ソドムの林檎』(早川書房)★★★★がその証拠。『花狩人』以来、SFのかっこよさを追求しつづけてきた野阿梓は、SFの神もかっこよさの神も細部に宿ることを十二分に承知している。SFマガジンに三回分載された表題作は、『バベルの薫り』の前日譚にあたるが(姉川孤悲(こい)がジョージクと知り合う話)、とりあえずそれは忘れていい。特務機関きっての凄腕サイキック・エージェントが大暴れするスーパーヒロイン小説として、冒険小説ファンや活劇ファンにも推奨したい一大エンターテインメントなのである。凝りに凝ったSF的な設定は巧妙に背景化されて〝かっこよさ〟のオーラを放つ舞台装置となり、その華麗なステージ上でSF史上最強最高のヒロイン、姉川〝ワン・ウーマン・アーミイ〟孤悲が爆裂する。月面都市ケプラーの実力者から依頼を受け、誘拐された少年の奪還任務に月へとやってきた姉川孤悲。恐るべき実力で太陽系内にその名を轟かせるマホロバ機関に法律の足枷はない。中国マフィアを脅しつけ、警察署を粉砕し、単身、敵の本拠地に乗り込んでの大立ち回り。最後は『マトリックス』ばりの空中格闘技まで披露する。このかっこよさに張り合えるのは映画版「トゥームレイダー」のアンジェリーナ・ジョリー様ぐらいか。「それはどうかな」には心底しびれたね。ロシア語、ヴェトナム語、中国語が乱れ飛ぶ無国籍ぶりは最近のアジアン・ノワール流だが、こちらはあくまでも痛快。キャラ立ちとSF的ディテールが完璧にマッチした傑作だ。
話が前後しますが、前述『わたしは虚夢…』と相互リンクする《ブギーポップ》シリーズも、最新刊の『ブギーポップ・アンバランス ホーリィ&ゴースト』(電撃文庫)★★★☆が出ている。こちらは、心ならずもボニー&クライドみたいな犯罪者カップルとなった十代の男女を主役に、ブギーポップ世界の枠組みで巻き込まれ型クライムノベルを語る試み。なにを持ってきてもスマートに処理してしまう上遠野浩平のセンスに脱帽。
一方、若木未生の新シリーズ第一弾『メタルバード1』(徳間デュアル文庫)★★★は、ちょっとオールドファッションドなハインライン流ミリタリー・スペースオペラの枠組みにいまどきのライトノベル・キャラを接合する。主役は、傲岸不遜を絵に描いたような天才航宙士レイアード(榎木津系)+そのお目付役のカイトの幼なじみコンビ。三部作になるようですが、まずは快調なスタートだ。
ここまでキャラが暴走しちゃうとついていけないという保守的SF読者には、岡本賢一の《傭兵グランド》シリーズがおすすめ。第三巻『クレイジー・ウォー』(ソノラマ文庫)★★☆では、宿敵リマンズがいい味出してます。きっちりSFネタを用意する義理堅さもこの著者らしいが、オレはもっと突き抜けたほうが好きだな。
〝新本格SF〟と帯に大書された津村巧のメフィスト賞受賞作『DOOMSDAY』(講談社ノベルス)★★は、『ファントム』meets『宇宙戦争』というか、読後感はむしろキング/クーンツ型の八○年代モダンホラーに近い。筆力はあるものの、中盤はさすがにダレる。古き良き設定を現代に甦らせるって意味では確かに〝新本格〟かもしれないが、これは(SFネタが)時代を遡り過ぎ。
その反面、SFアイテムが一切登場しなくても強くSF性を感じさせる小説もある。たとえば、どことも知れぬ世界で誰とも知れぬ敵と戦う操縦士を描く森博嗣『スカイ・クロラ』(中央公論新社)★★★★は、オレ的には森版『戦闘妖精・雪風』。世界の成り立ちの謎が核になる話はやっぱりSFでしょう。
その意味で今月いちばん仰天した傑作が、小川勝己の第三長篇『眩暈を愛して夢を見よ』(新潮社→角川文庫)★★★★☆。『葬列』『彼岸の奴隷』に続いて、まさかこんな小説を書くとはなあ。九九パーセントまでミステリ(というか新本格)なので、詳述はしませんが、一部ミステリ読者が怒り狂いそうな結末で思いきり感動するSF読者はけっこう多いと思う。そうじゃなくても、「愛はブーメラン」に反応する人は必読。ってそれはネタバレ?
ALL REVIEWSをフォローする