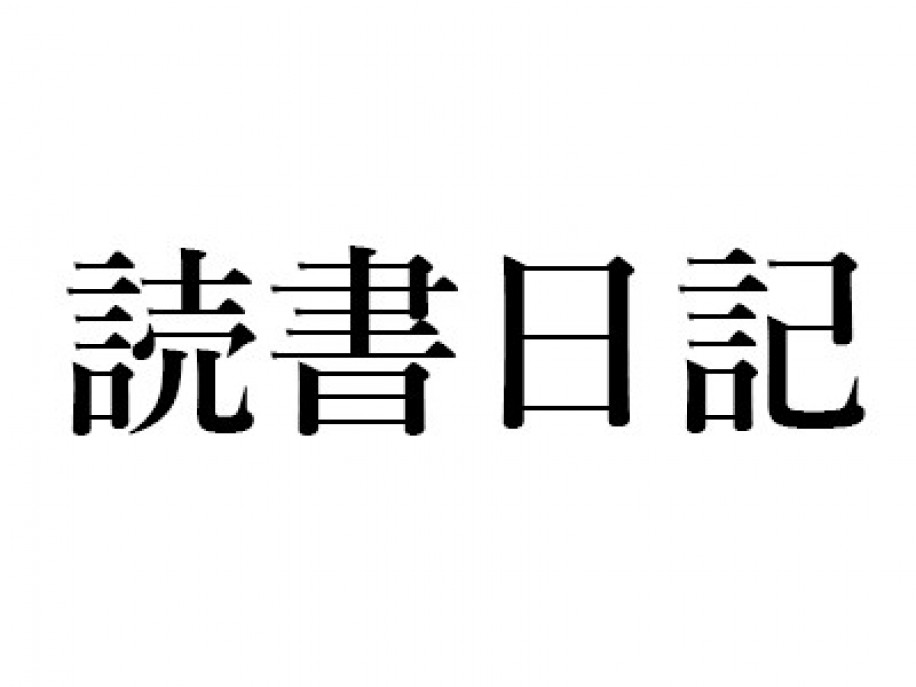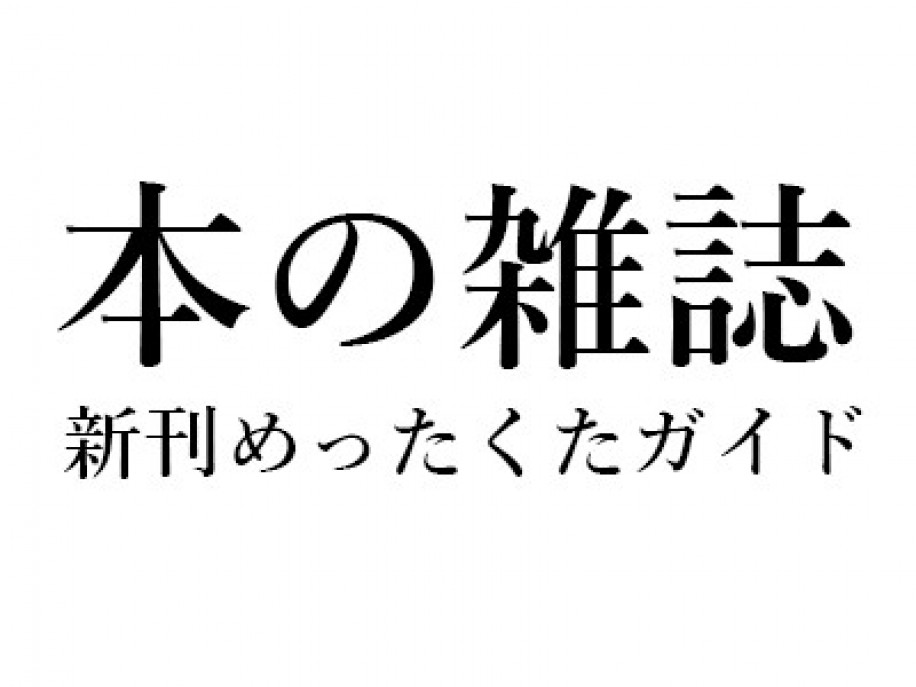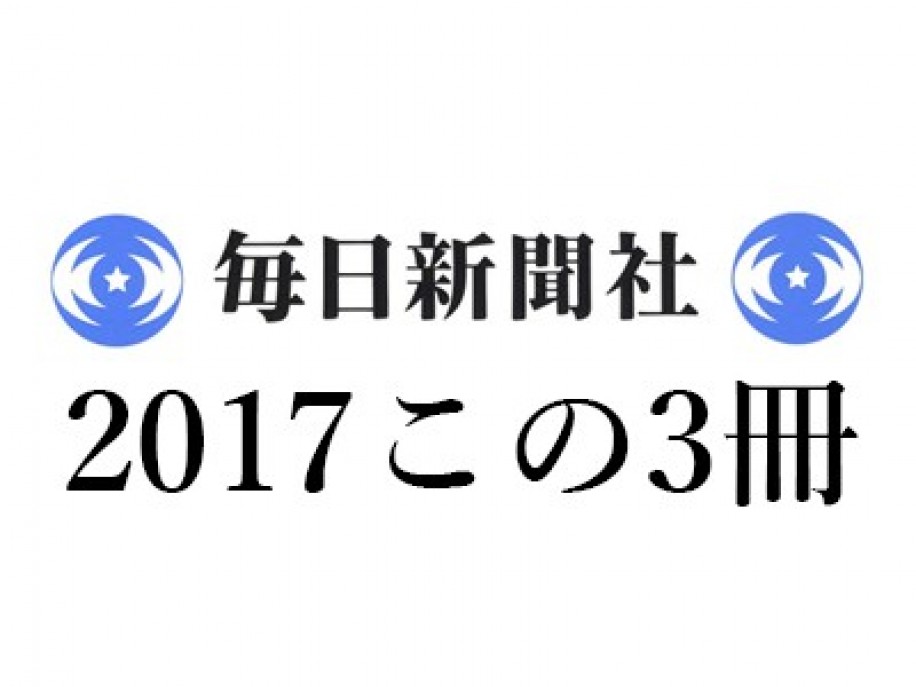読書日記
いとうせいこう×渡部直己×奥泉光『文芸漫談 笑うブンガク入門』(集英社)、エドウィン・S・シュナイドマン『アーサーはなぜ自殺したのか』(誠信書房)ほか
(自分で喋って、その録音を書き起こして、再構成したものを原稿にした。そのほうが楽だと思ってやってみたのだけど、ぜんぜん楽じゃなかった)
今号は、なんといっても、いとうせいこう×渡部直己×奥泉光『文芸漫談 笑うブンガク入門』(集英社/一六〇〇円)を、読んでもらわなければ。読んだ? 読んでない。そう、じゃぁ、読んでください。もう、ぜひ読んでほしい(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2005年)。
『ノーライフキング』『ワールズ・エンド・ガーデン』『解体屋外伝』といった傑作を書きながら、今は、"意味のあることは書けなく"なったと言ういとうせいこうさんに、新作『モーダルな事象』が出る奥泉光さんが、"「とにかく書け」みたいなことは言いたくないけど"「書く」という営みのパワーを解き、そしてボケる、に対してツッコむ! という漫談で文学を語ってるんですよー。これは、実際にお客さんの前でやったものを活字に再現していて、そういった勢いが、活字になっても残ってる。だから、とっても、おもしろい。文章を読んで、クスクス声だして、笑う。保育園の学芸会の「桃太郎ズ」のところなんて、もう思い出しても笑う(クスクス)。で、「桃太郎ズ」の話が、そのまま文学の話になっていることに感動する。具体的に、どういうふうに文学の話になったか、うまく話せないけど、それは、クスクスと共に茫洋(ぼうよう)と残ってる実感がある、マジで。
ぼくね、実際に「文芸漫談」を見に行ったりもして、いつ本になるんだーって待ちに待ってた。正直に書くと、生(なま)と、活字、どっちがおもしろいかといえば、生。生で観てるときは、もうクスクスどころか、ワハワハ笑ってたからね。奥泉さんのフルートにあわせて、いとうさんが「本日のまとめ」を語るっていう伝説の凄いセッションも観たんだから。
でも、活字のよさは、じっくり読めるところ。生で見たあと、あーだこーだって感想を話したときの誤読っぷりよりも、もう少し妥当性の高い誤読にはなったかなぁ? ぐらいに、じっくりと読める。
なにかを作ろうって思っている人、必読。小説が好きな人も、必読。クスクス笑いながらグングン伸びていく自分を実感します。
エドウィン・S・シュナイドマン『アーサーはなぜ自殺したのか』(誠信書房/二四〇〇円)は、三三歳で自殺したアーサーにいる周辺の人たち、父母、恋人、兄、妹、親友、前妻、心理療法家に、彼の自殺について聞いたインタビューが軸になってんの。"映画「羅生門」のように、真実は見る人によって異なり"って帯に書いてあるんだけど、語られるアーサーの人物像がガラっと違ったりするわけじゃない。ひとりの自殺した男性について、いくつかのインタビューが、静かに語られていく。
でもねぇ、一番気になるのは、彼が自閉症スペクトラムである可能性を指摘していながら、それについてはスルーしちゃってるところ。その視点から、きちんと調べていくと、また、まったく違った真実が、現れてくるんじゃないかと思うんだけど。
加藤幹郎『ヒッチコック「裏窓」ミステリの映画学』(みすず書房/一三〇〇円)は、理想の教室っていう新シリーズの中の一冊。ヒッチコックの名作『裏窓』が、どんな構造になっているかを解き明かしていく。この本自体が、ミステリみたいにおもしろい。『裏窓』の主人公が見た殺人事件は本当に起こったのか? って視点から、映画構造の問題、外見と内実の乖離を検討して、映画史的な転換として解説しちゃう。映画を楽しむ新しい切り口を手に入れることができるので、大オススメ。
叶てつこ『くるくるキレキレ人生』(新潮社/一二九六円)は、境界性人格障害で、リタリン中毒で、鬱病で……という女性の手記。オナラ強迫神経症や、レイプ未遂や、精神病院からのプチ脱走や、元彼の部屋に放火したことや、そういったことが綴られているんだけど、すごいのが、これだけヘヴィなことが語られるのに、文体が、たとえば、えーと、"もう、どうにもとまらない? ……by山本リンダになっちゃてたんである(←イヤ、歳がわかるねどうも)。"ってノリなところ。お母さんと対峙しようとして、すかーっとかわされてしまうとこなんて、現実のヘヴィさと滑稽さが伝わってきて、複雑な気持ちになっちゃいます。
佐木隆三『なぜ家族は殺し合ったのか』(青春出版社/七三〇円)は、「小倉少女監禁事件」とそれによって発覚した「一家連続殺人事件」のドキュメンタリィ。「これ以上残虐な事件を私は知らない」って帯にあるけど、もう、本当に、もう、ね。語る言葉を失う、とかって、本の紹介をしている時に言うべきことじゃないけど、本当に、失うどころか、語ることにすごく抵抗があって、もうこうやって喋ってても気持ちが沈んでくる。凄惨な事件が、たんたんと説明される強烈な本です。
天野ミチヒロ『放送禁止映像大全』(三才ブックス/一三〇〇円、のち文藝春秋)は、封印された映像二百六十三作品を、二ページ一作品、ドンドン紹介する本。被爆者に対する差別で欠番となったウルトラマンセブンの第十二話とか、逮捕されたジー・オーグループ会長の大神源太主演の「ブレイズ・オブ・ザ・サン」とか、タイトルでもーあれな「怪猫トルコ風呂」とか、東海村出身の魔獣ゲンシロンが登場する『サンダーマスク』第二十一話とか。封印の理由も、圧力だったり、自主規制だったり、差別問題だったり、出演者の犯罪だったり、著作権の問題だったり、原版がなくなってたり、そのバラエティさ加減が、いい感じ。困るのは、観たい! と思う作品が、ドンドン出てくるけど、観られぬ作品が多いこと。
漫画は二冊紹介。しりあがり寿『ジャカランダ』(青林工藝舎/一八〇〇円)は、がんがん成長する巨大な木の芽が、東京を破壊と混乱の渦に巻き込むっていう物語。四コマを三〇〇ページにのばしたようなって著者が言ってるぐらいのストレートさで、怒濤の三〇〇ページ、神話みたい。
もう一冊は、体が透明になってしまう病気に悩む少女とそれを見守る少年を描く岡本一広『トランスルーセント 彼女は半透明』(メディアファクトリー/五一四円)。だれも自分のことを気にかけてくれなくなるんじゃないかという思春期の気持ちと、透明病という特異な設定が、ストレートにシンクロしてて、直球すぎる描き方も、青春って感じで、いい。ウルウルくるよ。
【この読書日記が収録されている書籍】
今号は、なんといっても、いとうせいこう×渡部直己×奥泉光『文芸漫談 笑うブンガク入門』(集英社/一六〇〇円)を、読んでもらわなければ。読んだ? 読んでない。そう、じゃぁ、読んでください。もう、ぜひ読んでほしい(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2005年)。
『ノーライフキング』『ワールズ・エンド・ガーデン』『解体屋外伝』といった傑作を書きながら、今は、"意味のあることは書けなく"なったと言ういとうせいこうさんに、新作『モーダルな事象』が出る奥泉光さんが、"「とにかく書け」みたいなことは言いたくないけど"「書く」という営みのパワーを解き、そしてボケる、に対してツッコむ! という漫談で文学を語ってるんですよー。これは、実際にお客さんの前でやったものを活字に再現していて、そういった勢いが、活字になっても残ってる。だから、とっても、おもしろい。文章を読んで、クスクス声だして、笑う。保育園の学芸会の「桃太郎ズ」のところなんて、もう思い出しても笑う(クスクス)。で、「桃太郎ズ」の話が、そのまま文学の話になっていることに感動する。具体的に、どういうふうに文学の話になったか、うまく話せないけど、それは、クスクスと共に茫洋(ぼうよう)と残ってる実感がある、マジで。
ぼくね、実際に「文芸漫談」を見に行ったりもして、いつ本になるんだーって待ちに待ってた。正直に書くと、生(なま)と、活字、どっちがおもしろいかといえば、生。生で観てるときは、もうクスクスどころか、ワハワハ笑ってたからね。奥泉さんのフルートにあわせて、いとうさんが「本日のまとめ」を語るっていう伝説の凄いセッションも観たんだから。
でも、活字のよさは、じっくり読めるところ。生で見たあと、あーだこーだって感想を話したときの誤読っぷりよりも、もう少し妥当性の高い誤読にはなったかなぁ? ぐらいに、じっくりと読める。
なにかを作ろうって思っている人、必読。小説が好きな人も、必読。クスクス笑いながらグングン伸びていく自分を実感します。
エドウィン・S・シュナイドマン『アーサーはなぜ自殺したのか』(誠信書房/二四〇〇円)は、三三歳で自殺したアーサーにいる周辺の人たち、父母、恋人、兄、妹、親友、前妻、心理療法家に、彼の自殺について聞いたインタビューが軸になってんの。"映画「羅生門」のように、真実は見る人によって異なり"って帯に書いてあるんだけど、語られるアーサーの人物像がガラっと違ったりするわけじゃない。ひとりの自殺した男性について、いくつかのインタビューが、静かに語られていく。
でもねぇ、一番気になるのは、彼が自閉症スペクトラムである可能性を指摘していながら、それについてはスルーしちゃってるところ。その視点から、きちんと調べていくと、また、まったく違った真実が、現れてくるんじゃないかと思うんだけど。
加藤幹郎『ヒッチコック「裏窓」ミステリの映画学』(みすず書房/一三〇〇円)は、理想の教室っていう新シリーズの中の一冊。ヒッチコックの名作『裏窓』が、どんな構造になっているかを解き明かしていく。この本自体が、ミステリみたいにおもしろい。『裏窓』の主人公が見た殺人事件は本当に起こったのか? って視点から、映画構造の問題、外見と内実の乖離を検討して、映画史的な転換として解説しちゃう。映画を楽しむ新しい切り口を手に入れることができるので、大オススメ。
叶てつこ『くるくるキレキレ人生』(新潮社/一二九六円)は、境界性人格障害で、リタリン中毒で、鬱病で……という女性の手記。オナラ強迫神経症や、レイプ未遂や、精神病院からのプチ脱走や、元彼の部屋に放火したことや、そういったことが綴られているんだけど、すごいのが、これだけヘヴィなことが語られるのに、文体が、たとえば、えーと、"もう、どうにもとまらない? ……by山本リンダになっちゃてたんである(←イヤ、歳がわかるねどうも)。"ってノリなところ。お母さんと対峙しようとして、すかーっとかわされてしまうとこなんて、現実のヘヴィさと滑稽さが伝わってきて、複雑な気持ちになっちゃいます。
佐木隆三『なぜ家族は殺し合ったのか』(青春出版社/七三〇円)は、「小倉少女監禁事件」とそれによって発覚した「一家連続殺人事件」のドキュメンタリィ。「これ以上残虐な事件を私は知らない」って帯にあるけど、もう、本当に、もう、ね。語る言葉を失う、とかって、本の紹介をしている時に言うべきことじゃないけど、本当に、失うどころか、語ることにすごく抵抗があって、もうこうやって喋ってても気持ちが沈んでくる。凄惨な事件が、たんたんと説明される強烈な本です。
天野ミチヒロ『放送禁止映像大全』(三才ブックス/一三〇〇円、のち文藝春秋)は、封印された映像二百六十三作品を、二ページ一作品、ドンドン紹介する本。被爆者に対する差別で欠番となったウルトラマンセブンの第十二話とか、逮捕されたジー・オーグループ会長の大神源太主演の「ブレイズ・オブ・ザ・サン」とか、タイトルでもーあれな「怪猫トルコ風呂」とか、東海村出身の魔獣ゲンシロンが登場する『サンダーマスク』第二十一話とか。封印の理由も、圧力だったり、自主規制だったり、差別問題だったり、出演者の犯罪だったり、著作権の問題だったり、原版がなくなってたり、そのバラエティさ加減が、いい感じ。困るのは、観たい! と思う作品が、ドンドン出てくるけど、観られぬ作品が多いこと。
漫画は二冊紹介。しりあがり寿『ジャカランダ』(青林工藝舎/一八〇〇円)は、がんがん成長する巨大な木の芽が、東京を破壊と混乱の渦に巻き込むっていう物語。四コマを三〇〇ページにのばしたようなって著者が言ってるぐらいのストレートさで、怒濤の三〇〇ページ、神話みたい。
もう一冊は、体が透明になってしまう病気に悩む少女とそれを見守る少年を描く岡本一広『トランスルーセント 彼女は半透明』(メディアファクトリー/五一四円)。だれも自分のことを気にかけてくれなくなるんじゃないかという思春期の気持ちと、透明病という特異な設定が、ストレートにシンクロしてて、直球すぎる描き方も、青春って感じで、いい。ウルウルくるよ。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする