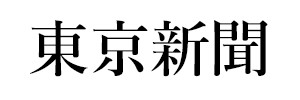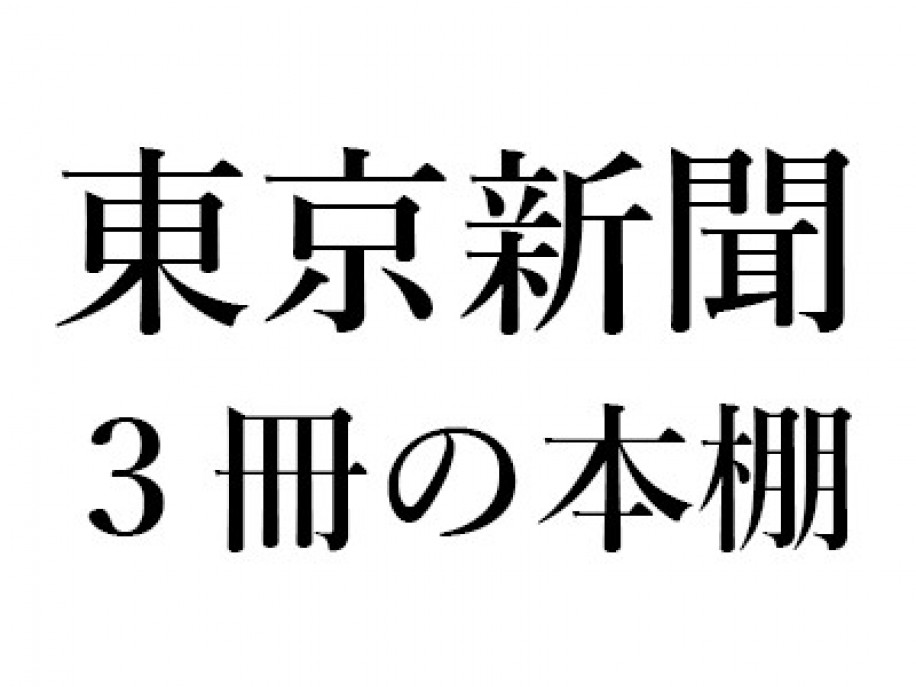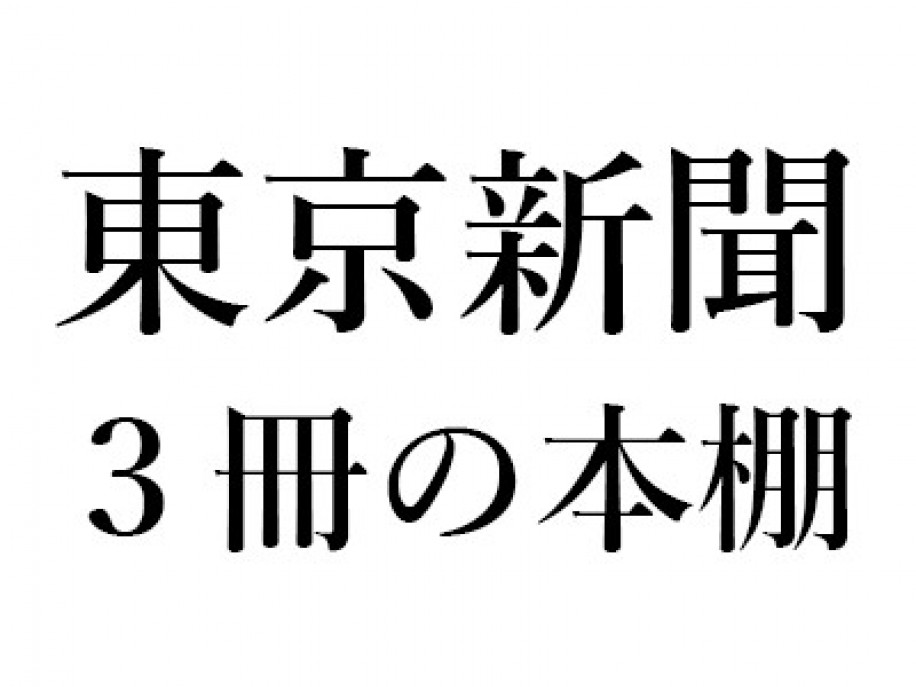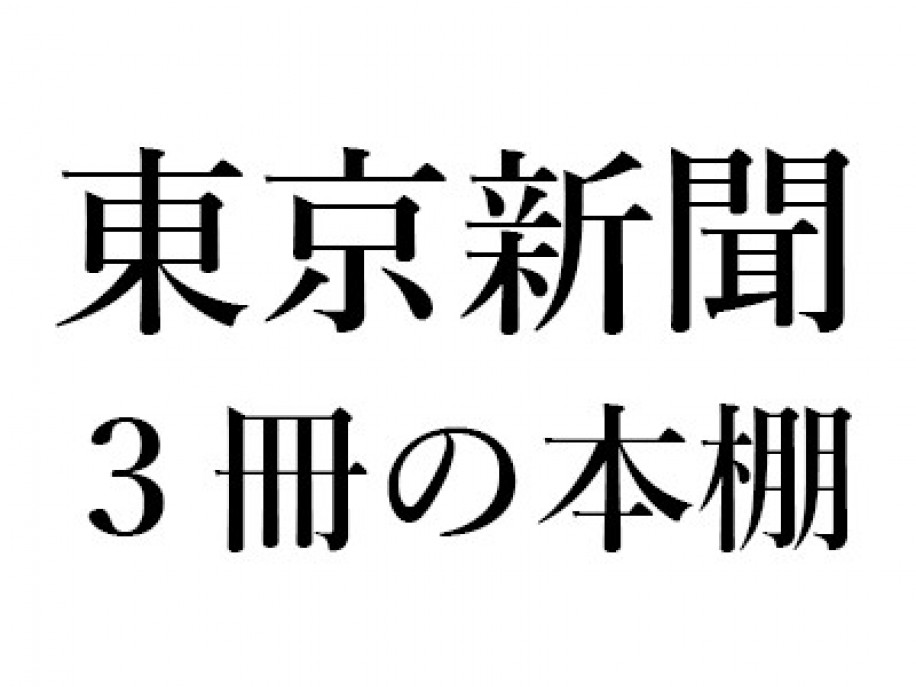読書日記
静岡新聞社・南日本新聞社・宮崎日日新聞社編『ウナギNOW』(静岡新聞社)、黒木真理『ウナギの博物誌』(化学同人)、石川博『鰻』
ウナギに尋ねる未来
ウナギの稚魚であるシラスウナギの記録的な不漁が報じられた。ニホンウナギの激減はだいぶ前から憂慮されていて、2014年に国際自然保護連合(IUCN)が絶滅危惧種に指定した。一六年にはワシントン条約締約国会議でニホンウナギの国際取引に関する調査が決定、輸出入が規制されるのではとの懸念が高まっている。 絶滅が心配されながら、土用の丑(うし)の日が近づくとスーパーやコンビニ、牛丼チェーンなどに大量の蒲焼(かばや)きが並ぶ状況には変化がなく、このままじゃ食い尽くしてしまうぞと毎年騒ぎになる。だが規制が入る気配はなく、水産庁からは、減少の原因が特定できないので食べ控えても意味はないなんて見解が出された。ええっ!? と驚く一方で、自分がウナギにあまりにも無知なことに気づき、じゃあと十冊ばかりウナギ本を読んでみた。まずウナギの現況を知るには、(1)静岡新聞社・南日本新聞社・宮崎日日新聞社編『ウナギNOW-絶滅の危機!! 伝統食は守れるのか?』(静岡新聞社・1,620円)がいい。ウナギの名産地である静岡、鹿児島、宮崎の地方紙三紙が、IUCNの指定を受け合同で進めた企画「ウナギNOW」を書籍化したものだ。産地ならではの養殖の変遷や養鰻(ようまん)業者へのアンケートから、稚魚漁と輸入の実態、中国・台湾・韓国でのウナギの消費と意識調査、ウナギ研究の現在、ウナギを未来へ繋(つな)ぐための提案まで論点を網羅している。新聞記事なので各話題が数ページに収まっており、拾い読みもしやすい。
古来ウナギは不思議な魚とされてきた。卵を持った親ウナギや、生まれたての稚魚が見つからなかったせいで、自然発生するだの、山芋が変身するだの、ばかげた迷信が流布していた。それは歴史としても、生態には依然謎が多い。何しろ、卵の採取に成功し産卵場所が特定されたのは2009年、つい最近のことなのである。
(2)黒木真理編著『ウナギの博物誌-謎多き生物の生態から文化まで』(化学同人・1,944円)は、ウナギという存在について、生物として、食資源として、文化として、の三面から迫っている。これ一冊でウナギの基礎知識と蘊蓄(うんちく)がけっこう足りてしまうお得本である。
ウナギ研究の第一人者・塚本勝巳博士の<2>の担当箇所に、先達の大家である松井魁博士をモデルにした『赤道祭』という小説を火野葦平が書いているとあり、へえと調べたら、(3)石川博編『シリーズ紙礫(かみつぶて)5 鰻(うなぎ)』(皓星社・1,944円)に抄録されていた。荒唐無稽な物語に、ウナギの知識と調査の様子がやけにディテール細かく盛り込まれた、なぜこんなものを書いたのかと首をかしげる珍品でした。
ALL REVIEWSをフォローする