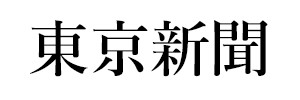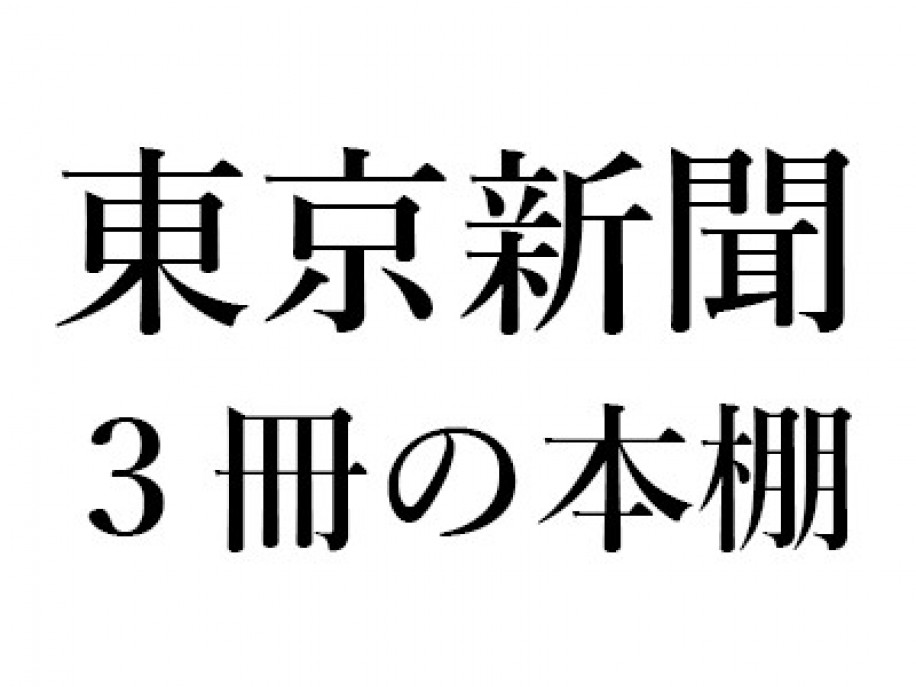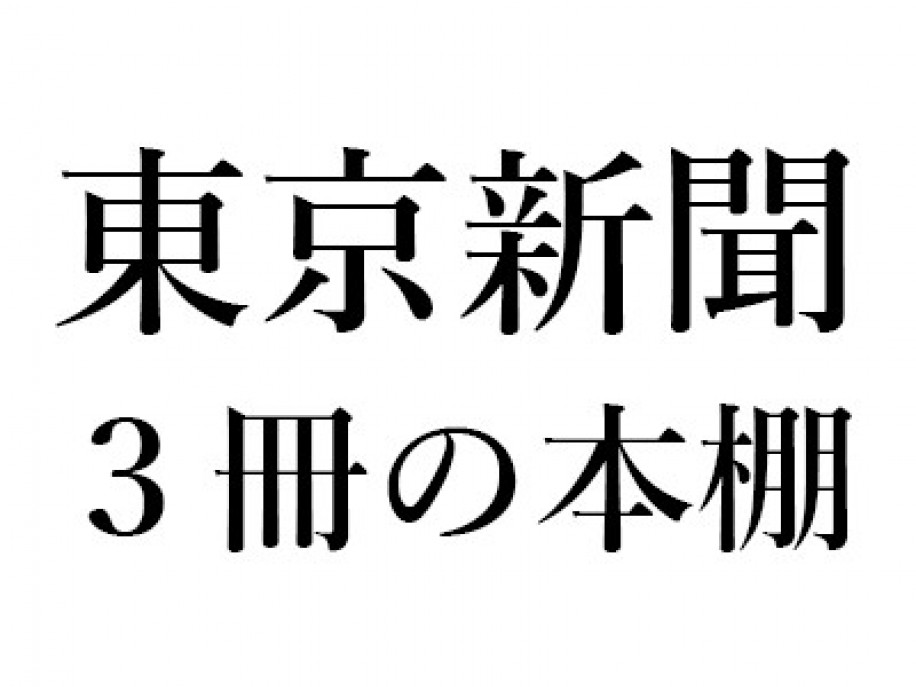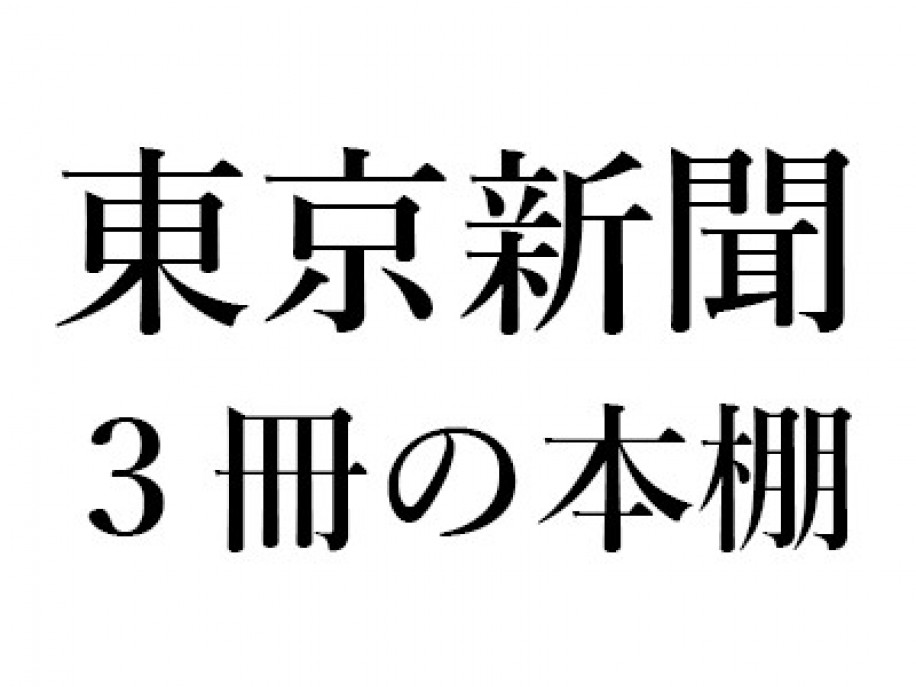読書日記
フィル・ナイト『SHOE DOG』(東洋経済新報社)、デーヴィッド・マークス『AMETORA』(DU BOOKS)、タイラー・コーエン『創造的破壊』(作品社)
グローバル化と文化
ナイキのロゴをあしらった見事な装丁に惹かれて、<1>フィル・ナイト『SHOE DOG-靴にすべてを。』(大田黒奉之訳、東洋経済新報社・1,944円)を手に取った。「そういえばナイキの創業者って誰だっけ?」と思ったのもある。著者こそが創業者その人であり、本書は、起業を決意した1962年から、株式を上場する80年までの同社の歴史を回顧したものだ。70年代にはブランドを確立していたナイキだが、実は上場まで資金繰りに苦しんでいた。明日には倒産かという瀬戸際を切り抜けていく波瀾(はらん)が読みどころだが、加えて創業と存亡に日本企業が深く関わっていたという知られざる事実が、本邦の読者には強く訴えかけるに違いない。その企業とはオニツカタイガーと日商岩井だ。ナイキはオニツカをアメリカで販売する業者として事業を始めたのだが、同社の裏切りによって苦境に陥る。その窮地を日商岩井が救うという奇縁。この物語で一番おいしい役どころを務めているのは、間違いなく日商岩井のイトーだ。
<2>デーヴィッド・マークス『AMETORA』(奥田祐士訳、DU BOOKS・2,376円)も、サブタイトルにうたわれているように「日本がアメリカンスタイルを救った物語」だ。VANの創業者である石津謙介から始まった日本におけるアメリカン・トラッド(アメトラ、IVY)の受容史が描かれるのだが、史観の根底には「グローバル化と文化の関係を見極める」という意識があって、それが本書をユニークなものにしている。
流行は繰り返す。だが、アメリカがトラッドに立ち返ろうとしたとき、最高のお手本となったのは、石津らが戦後、服の情報も実物も乏しいなかで、苦心して作り上げ、残したテキストだった。ジーンズもそうだ。ビンテージの価値が見いだされ、暴騰したあげくストックが枯渇したとき、古き良き時代と同等以上のジーンズを生産するための知識と技術、手段をすべて備えていたのは、ハイクオリティーなレプリカ製造に切磋琢磨(せっさたくま)した日本だったのだ。アメトラやジーンズは、かつて憧れコピーにいそしんだ日本からの逆輸入によって正統性を保つことができたのである。
正統性をめぐるこの事態は、アメリカの経済学者タイラー・コーエンが<3>『創造的破壊-グローバル文化経済学とコンテンツ産業』(浜野志保訳・田中秀臣監訳、作品社・2,592円)で説いた、異文化間交易のもたらす利点の実例になっている。ローカルな文化が破壊される云々(うんぬん)といった悲観論ばかりが強調されがちなグローバル化だけれど、そのプロセスでしか守られない文化、創造されない文化だって一方では確実にあるのだ。
ALL REVIEWSをフォローする