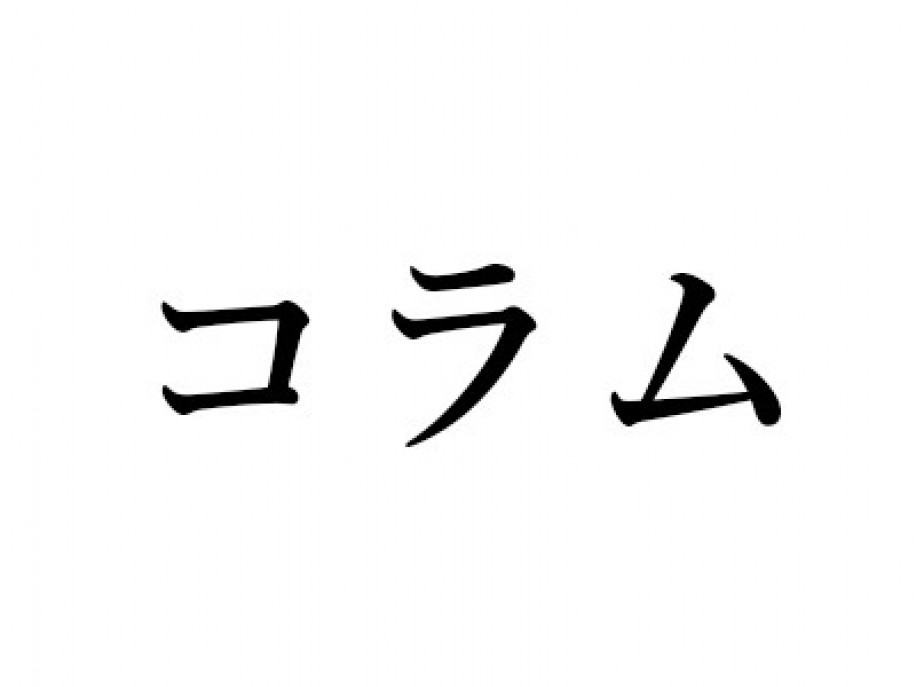コラム
埴谷雄高『死霊』(講談社)、『虚空』(現代思潮新社)、『不合理ゆえに吾信ず』(現代思潮新社)
二〇〇〇億光年の彼方に
埴谷雄高が亡くなった。彼なら、そのことを「二〇〇〇億光年の彼方に去った」と表現しただろうか(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1997年)。つい先日、谷川雁のことを書いたのもなにかの因縁のように思える。六〇年代に高校生であったわたしの周りで「日本人の物書き」といえば、まず埴谷雄高・谷川雁・吉本隆明の三人であった。わたしたちはたぶん彼らから「考える」スタイルを学ぼうとしていた。時代に生きるたくさんの「物書き」の中から、なぜ彼らの「考える」スタイルを選んだのか。それはたぶん、彼らの「孤独」の有り様が信じるに値すると感じられたからであろう。
この三人は一つ一つが孤立した巨峰であった。彼らの前に先行者はおらず、彼らは後に多くの模倣者や崇拝者を生んだ。しかし、同時にこの三人は不思議な友情で結ばれてもいた。
当時、わたしたちの手に入る埴谷雄高の本は限られていた(もちろん、元々寡作の人ではあったのだが)。主著であり唯一の長編、そして「幻の名作」であった『死霊』は、わたしたちが行きつけの古本屋の宝物で、あまりに高くわたしたちには手が出なかった。その代わりに、わたしたちはやはり唯一の短編集であった『虚空』やアフォリズム集の『不合理ゆえに吾信ず』を読んだ。前者には吉本隆明の解説があり、後者には谷川雁と著者との往復書簡が収められていた。いまから三十五年以前のものだが、解説も書簡も変更のしようがないほど正確なものだった。
この点に関して私はただ、この世のいかなる層をも代表しまいとするあなたの決意を読むより他はありません。より大いなるもののより完璧な代表であろうとする欲望は、一般に政治の論理を戯画化するときにだれもが使う説明ですが、その実この根はいいようもなく深いのは自明のことです。代表の論理は政治の論理をつらぬいて、すべて表現とよばれるものの骨髄にまで達しています。したがって、不参加と非代表の論理もまた同じ強さのヴァリュウをもつ。(「作者への手紙」谷川雁)
わたしたちが、彼らを信頼したのはたぶんこの「非代表の論理」のせいだった。政治は、誰かの代表として発言することからはじまる。だが、政治に従事する者はそのことをよく知っている。だから、実のところ被害は少ない。問題は文学なのである。文学もまた政治とまったく同じく、誰かをあるいはなにかを代表して発言する。どんなに孤独に見える私小説作家もそれを免れない。たとえば、彼は「人間」あるいは「弱者」を代表している。代表しているということは、(あるものを代表している)自分を正当化しようとして政治的な発言をしているということである。わたしたちは政治や政治家たちをとことん嫌悪している。ならば、なぜ文学者たちをも徹底して嫌悪しないのか。政治家と文学者はまったく同じことをやっているのである。この三人はそのことを表現の中心に据えた。物書きとしての退路を完全に断ったのである。埴谷雄高はついに唯一の長編小説を完成することなく去り、谷川雁は早々と詩作を放棄し、吉本隆明だけが生き残った。
埴谷雄高が亡くなった日、わたしは久しぶりに彼の作品を読み返し驚愕した。その一つは、彼の作品が難解とは感じられなくなったこと。そして、もう一つは、「存在の不快」や「大暗黒」や「超論理」について語る、かつては浮世離れしているような気もした彼の作品が実は「傷ついた魂」について書こうとしていたことに気づいたからだった。さようなら、傷ついた魂。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする