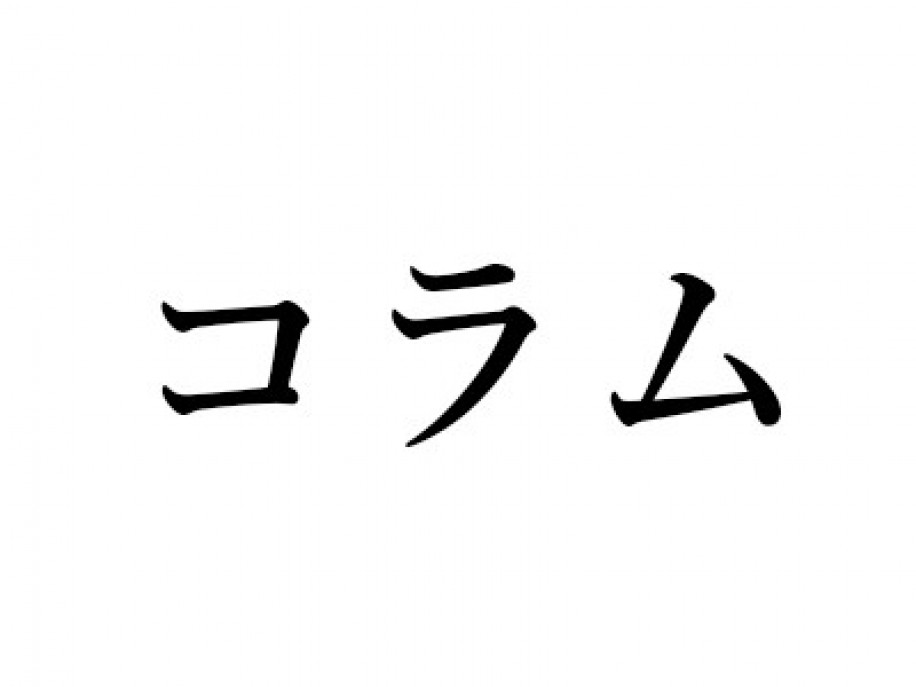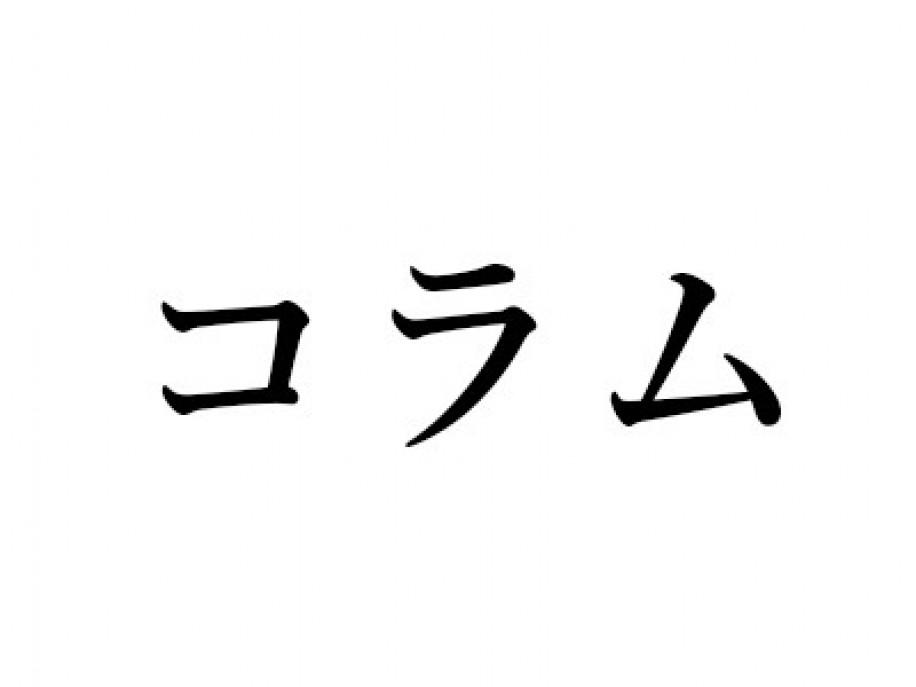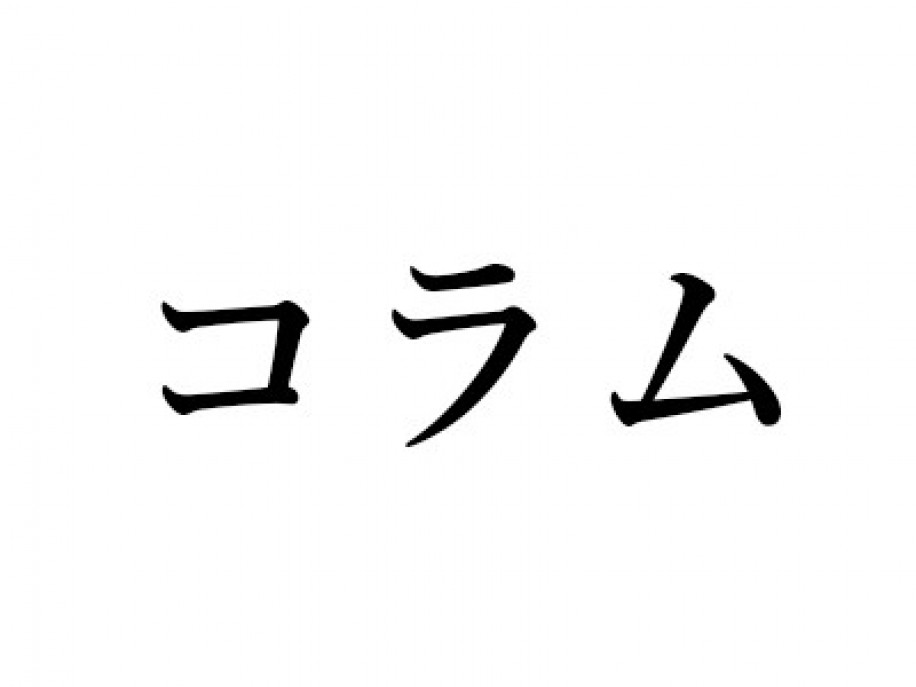コラム
林 芙美子『放浪記』(新潮社)、岸本 葉子『クリスタルはきらいよ―女子大生の就職活動日記』(泰流社)、スタインベック『赤い小馬』(新潮社)、ほか
軍手と文庫本
もの書きになるまでは、私にとって本とは、本屋に行けば並んでいるものだった。そこに至るまでに、どんなプロセスがあるのか、どこでどんな人が作っているのかは、考えたこともなかった。はじめて作り手の側に回ったのは、OL二年めのとき。入社前、出版社に持ち込んであった原稿だ。
卒業前の暇な時間、自分にとってめあたらしいことずくめだった就職活動のできごとを、
「せっかくだから書き留めておくか」
くらいのつもりではじめたら、原稿用紙で三百枚以上になった。持ち込みが制度的に認められているのかどうか知らないが、林芙美子の『放浪記』(新潮文庫から『新版 放浪記』として出ている)にそんなシーンがたしかあったと思い出し、まねしてみた。
持ち込む先の基準はただひとつ、住所が×-×-一〇二のように部屋番号まであること。×ー×だけだと、ビル全体がその社ということであり、受付を通さないといけなかったり、守衛さんに阻まれたりで、編集部までたどり着けないだろうとは、会社回りの例を通して推測できた。人間、どんな経験もムダにはならぬものである。
なんとか受け取ってもらった原稿が、一年を経て出版された。
出す側となってわかったのは、世の中には本と名のつくものが、いかに多いかである。私は考え方を改めた。本ならば本屋に行けばあるものとは、けっして思ってはいけないと。
店頭に到達するまでが、遠い遠い道のりなのだ。平積みになるなんて、ほんの一部に過ぎない。
会社の帰り、
「そろそろ出たはず」
と覗きにいった。勤め先のある渋谷近辺では、もっとも品数の多いであろう大盛堂へ。とりあえず新刊コーナーをめざす。
ない。まるで見当たらない。ジャンル別の棚だろうか。
サブタイトルが「女子大生の就職活動体験エッセイ」となっていたのを思い出し、「就職」コーナーに行ってみた。面接マニュアル、業種別ランキングといった情報ばかりで、エッセイの入る余地はなさそうだ。
女子大生とあったことから「女性」コーナーに足を運べば、フェミニズムとか解放運動の歴史とか、入社試験で滑った転んだの次元より、はるかにシリアス。「エッセイ」コーナーは椎名誠、林真理子といった売れっ子作家が占めているし、「随筆」だと急に小林秀雄と、シブ過ぎる。あの本は、いったい何に分類されるのか?
エスカレーターと階段を上ったり下りたりで疲れ果て、むなしく帰った。
家にはジャンジャン電話がかかってきていた。著者インタビューの申し込みや「第二作をぜひ」といった反響が続々と……ではなく、大学の元同級生からだ。
本が出るので有頂天になったのと、でもまったく売れなかったら困るとの懸念から、私は事前に、一、二年のときのクラスの女子中心に、かなり言いふらしてしまっていた。ところが、いざフタを開けると、
「どこにもないよ」
「ほんとうに出たの?」
苦情や猜疑心いっぱいの問い合わせが、どっと寄せられたのである。
「新宿の紀伊國屋も神保町の三省堂も見たんだよ。探し回る暇ないからさ。代金分の切手を同封するから、送ってもらえない?」
などと「通信販売」を申し込んでくる人までいた。
自分でもまだ売られている現場を見ていない私の胸には、彼女らの発する一語一語が、五寸釘のように突き刺さった。
答に窮し、出版社に電話した。
「あのー、私の本は渋谷、新宿近辺で言うと、どこにあるんでしょう」
受話器の向こうの編集者は、唸(うな)った。
「それは、非常に難しい問題でね」
「取次」という流通専門の会社があることを、そのときはじめて知った。出版社が直に本屋におろすのではないらしい。
同級生の行動パターンから、
「本は本屋にあれば買うけれど、注文までして読もうとする人は、少ない」
ということもわかった。たまたま店に行ったとき、目につくところにあるかどうかが、売れる売れないの分かれめなのだ。出す側にとっては、きびしい条件と言わざるを得ない。全国に書店が何軒あるか知らないが、刷り部数はわずか六千。そううまく行き渡るはずもない。
考えてみれば、日本の人口一億二千万に対して、六千。哀しいほどの少なさだ。出版は、新聞の広告に載るときもあるので、何かすごくメジャーな商売に思われがちだが、実際はほんと、小規模なものである。
本がどのようにしてできるかを、理解したとはとても言い難い。校正刷りを渡され、直して戻し、また渡されて、といったふうに、命ぜられるままに動いていた。装丁なんて言葉を知ったのは、もっとずっと後である。
本好きの同級生でも、編集者なるものからして、何をする人なのかわからず、
「本って、原稿と印刷所があれば、できるんじゃないの?」
と言っていた。
著者ならば、無尽蔵に自分の本をもらえると思う人が、多いことにも驚く。
「探してもないから、送ってよ。どうせタダなんでしょ」
と何人から求められたわからない。
私は私で、本は出版社に行けば、タダとは言わないけれど、いくらでも出てくるものと信じていた。が、会社の住所とは別のところに倉庫があって、そこで管理されている。
それを知ったのは、まとまった数が要ることになったため。同級生の間から、
「こう本屋になくてはしようがない」
と、出身校の学園祭で売る案が持ち上がった。留年して、その春卒業したばかりで、後輩に顔がきく男子がいる。彼から話を通し、後輩たちの模擬店の前に台を置かせてもらうことにした。実行委員会には無届けなので、見回りが来たらすばやく撤収するという段取りだ。サブタイトルでは「女子大生」とうたっていたが、実は共学でむくつけき男どももいたのである。
あの頃を思い出すと、今ではすっかり人付き合いを面倒がり、早々に隠居したみたいな生活を送る私にも、
「青春の日々があったのだなあ」
と感慨深くなる。
自分にとってもまわりにとっても、本が出るなんて、この先たぶんないだろう、めずらしいことであり、
「せっかくだから日の目を見せてやらなければ」
といった気持ちで皆が一致していた。私に、というよりも、本に対する「同情心」といえようか。
売るべき本は、前もって倉庫から編集部の方に搬入しておいてもらった。当日の朝、中古のRXセブンを買ったばかりという男子と取りにいく。車の性能と、運転技術とを危ぶみながら。
社の入口に、運び込まれたばかりの包みがあって、
「これですね。では、お預かりしていきます」
と持ち上げたところ、紙が破れ、『告白小説・私の……』といったタイトルの一部と、半脱ぎの女性の絵の表紙が現れる。
「あ、それは違います」
と会社の人。なんと、同じところが別の社名で、官能小説を出していたのだ。
少数言語の参考書など、志の高い出版物で知る人ぞ知る社だったが、それだけでは採算が合わないのか。編集者の言うには、良心的といわれる出版社が、そうした副業で経営を支えているのは、ままあることと。
苦しい内情を垣間見た思いであった。
今の私の本との関わり方は、一読者としてと、もの書きとしてと、七対三くらいだろうか。
書店に行っても、棚なり人々なりのようすを、完全に受け手だった頃とは別の目で観察していることがある。
もっとも強く感じるのは、自分の買いたい本の書名を正しく言える人が、いかに少ないかである。レジ近くにいると、神経のほとんどを、客と店員のやりとりにとられてしまう。
男性。推定年齢六十五歳。グレーのウールスラックスに、バーバリーチェックのシャツ。定年後とみえ、ネクタイこそ締めていないが、それなりにきちんとしたかっこうだ。読みさしらしい新書を抱えているのが、向学心を感じさせる。成人大学に通うことも辞さないような雰囲気だ。ただし、話し方からして、少々せっかちそうな。
「字の本、探してるんだけど」
「ジ、ですか?」
Tシャツにエプロンの、若い女性店員が聞き返す。
「漢字の字だよ。新聞にも広告が出てた。知らない?」
「漢字検定のテキストでしょうか」
「そんなんじゃなくて、ふつうの本、本。ほら、何てったか、字を研究してる人が書いた」
私は職業がら、出版広告はつい見てしまうので、
(タイミングからして平凡社から出ている白川静さんの本かな。『字訓』『字統』『字通』と、たしかに「字」はつくわな)
と考えた。
「出版社はおわかりでしょうか」と店員。
男性はパッと通じず、あれこれ聞き返されることに、苛立ちはじめている。
「どこだったかは忘れたけどね、とにかく有名な人。新聞に出てたじゃない」
とくり返す。このテの人は、自分にとっての常識は、万人が知らなければ、気がすまないのだ。
「いつ頃の広告ですか」店員が重ねて問うと、
「あー、もういい」
しようがないな、これじゃ、とか何とかつぶやきながら撫然として行ってしまった。
昨今の書店員は不勉強である、もう少し本のことを知ってもらいたい、といった投書が、ときどき載るが、うち三割は、彼のような人からではなかろうか。
レジまわりで耳にする限りでは、客は概して、タイトルに関しアバウトである。辺見庸著『もの食う人びと』(共同通信社・角川文庫)はベストセラーになったが、あの本が新聞雑誌テレビでさかんにとり上げられていた頃私は、客が、
「『もの食う人びと』ってありますか」
とタイトル末の「びと」までちゃんと発音するのを、聞いたことがない。なぜか、『もの食う人』なのだ。「『もの食う何とか』ってありますか」と、「人」の一語さえ出ない人もいる。
あの頃『もの食う人びと』は、「新刊」にも「話題の書」のところにも、どうしたって目につくように積んであった。それでもみつけられないのは、よほど探し方が悪いか、はじめから自分で探そうとしない依存心の強い人かだろう。だから覚えない、とも考えられる。
が、私はやはりそれ以前に、
「新聞に載っているくらいだから、行けばある、聞けば出てくる」
との思い込みが、受け手の側にあると思う。つまるところ、それも、出版というものの規模に関する錯誤、すなわち、読者が想像するよりはるかに、出版点数は多く、一点あたりの部数は少ないことからくる。
ベストセラーはまだしも、そうでない本は、分類の問題も大きい。別の棚をいくら必死になって探しても、あるはずがない。そして、どのジャンルに入れられているかの見当は、店員でも違っていたりするのである。
「『ざけンな、専業主婦』って、ありますか」
後ろのレジで、四十代とおぼしき女性のソプラノが言った。こういうことについては、私の聴覚はやたら敏感になる。
振り向くと、制服を着た丸顔の店員が、
「『ざけンな』でございますね」
復唱しながらメモしていた。新人らしく、受け答えも初々しい。女性客は、
「『ざけンな』で間違いないと思いますけど、いずれにせよ『いい加減にしろ』とか『ぶっ殺すぞ』とか、そんなような感じです」
と、ずいぶん物騒である。
(挑発が狙いのタイトルにしても、ぶっ殺す、はないだろうなあ)
と思いつつ、女性エッセイの棚に沿って歩いていくと、目の前に石原里紗著『くたばれ!専業主婦』(ぶんか社)なる本があるではないか。そのものではないが、限りなく近い。
レジを振り向くと、店員はメモを握り締めカウンターを出るところだった。まっしぐらにこちらに来るかと思いきや、なぜか、ピューッと通り過ぎ、「家庭・教育・心理」の棚へ走っていく。似て非なるコーナーだ。
棚の間を、マッシュルームカットの頭がピョコピョコ動く。上から下までくまなく探しているようだ。
「お客さまー」
息を切らして、戻ってきた。案の定、本は手にしていない。
「申し訳ありません、ないようです」
私はむずむずしてしまった。別の人の本だから関係ないと言えばないのだが、求める人が一・五メートルの至近距離まで来ながら、買われるチャンスをみすみす逃そうとしている。こういうのに居合わせるのは、精神衛生に非常に悪い。
「お取り寄せいたしましょうか」
「そうねえ。でも、かなり時間がかかるんでしょう」
となったとき、がまんできず、
「すみません、ここに似たようなタイトルのがあるんですけど」
と口出ししてしまった。ソプラノの婦人は、
「あら、これ、これ。私ったら、まあ、『ざけンな』じゃなくて『くたばれ』だったのね。
ごめんなさい」
後で調べたら、同じ著者に『ふざけるな専業主婦』(ぶんか社)なる本もあることがわかった。よけいなことを言ってしまって、あれでよかったのかどうか、悩んでいる。
自分で自分の本がみつけられないこともある。出たばかりなのに、新刊にもエッセイコーナーにもない。
第三者をよそおって、店員に聞く。
すると、まるで関係ない棚をめざして、脱兎のごとく駆け出していく人がいるのだ。
あーあ、と首を振る。そっちにはないのに。追いかけるわけにもいかないし。
しかし、その絶対にあるはずのない棚から、
「お待たせしました、ございました!」
と高々と掲げて戻ってくるときがあるから、ぎょっとする。『ちょっとのお金で気分快適な生活術』(講談社+α新書)は「マネー・金融」、『マンション買って部屋づくり』(文藝春秋)は「不動産・ビジネス」コーナーから掘り出されてきた。ないよりはいいが、書いた当人としては、エッセイの棚に置いてほしい。
(みつかるわけないよな)
とうちひしがれつつ、財布からお金を出すのである。
私は本は基本的に買うが、書店にないと、図書館から借りてくる。
驚くのは、本に線を引く人の多さだ。しかも、だいじなところだけにでなく、すべての行に引くのである。
OL時代の上司に、回覧はすべて音読し、かつボールペンでたどりながらでなければ、読めないという人がいた。ペン先にはキャップをしていたが、たまに忘れて、跡がついた。
「そうしないと、どうも頭に入らない」
が、彼の言い訳だった。
図書館の本に線を引く人が、同時に声にも出すかどうかは知らないが、何らかの身体感覚がともなわないと、読んだ気がしないのだろう。単なる落書きにとどまらず、人間にとっての読むという行為の原形みたいなものを考えさせられて、興味深い。にしても、終わったらちゃんと消してもらいたいものである。
意味不明の記号をふる人もいる。漢詩の本では、一字一字の横に✔とか×の印が、万年筆でつけてあった。気にすまいとしても、目につくのでつい、
(返り点でもなさそうだし、何だろう)
と考えて、平灰(ひょうそく)ではと思いあたった。
平灰については、そういうものがあることしか知らないが、その並びを含めて鑑賞したとすれば、かなりの教養人だろう。しかし、万年筆は悪質だ。うっかりの範囲を超えている。
教養と公徳心とが関係しない例である。
私もページのはしを折ってしまっていることは、ままある。買った本については、書き込みもすることがあり、それらは売らずに、捨てている。そうでなくても今の古本屋は、新品に近い本ほど評価するという、逆説的な状況がある。「資源ゴミ」に出すほかない。今は何より得がたいものはスペースだ。本も消費財のひとつと、割り切るべき時代なのである。
子どもの頃、本は跨いでもいけないと言われたのからすると、価値観も変わったものだ。昔の受験生は、英単語を完全に暗記したら、そのページを破って食べたとも聞く。本を損傷するのは、そのくらいの覚悟があってのことだった。
この夏、庭の草むしりをしていて、軍手をしたまま額の汗を拭ったとき、久々に思い出した。
大学一年、九月からの学期がはじまったばかりの、窓から風を入れた教室でのことだ。ひとりの男子が、夏休みのバイト中のできごとを話していた。
仕事は、公民館裏のゲートボール場の草刈りだった。ひたすらしゃがんで、鎌をふるった。
一日じゅう腹を圧迫していたせいか、終わると便意を催してた。ゲートボール場のすみっこにある、掘っ建て小屋のようなトイレに入る。トタン屋根からの暑さに蒸れた、強烈なアンモニア臭にめまいがした。あの頃は、そういうトイレが、まだあった。息を詰めるようにしながら、ジーパンをおろし、膝を折る。
用の方はつつがなくすんで、尻を上げかけたとき、はっと気づいた。
(ちり紙を持っていない……)
ポケットには文庫本が一冊だけ。スタインベックの『赤い小馬』(新潮文庫)だ。と、タイトルまではっきりわかったのは、バイトに来る電車の中で、読んでいたからだ。
読み終えたので、不要といえば不要である。田舎の「おじいちゃんち」では、古新聞をもんで、ちり紙代わりに使っていた。それと同じと考えられなくはない、しかし、本を尻拭きなどに使っていいものか。
進退極まり、中腰のままでいる。
そうするうちにも、汗は垂れ、睫の間からしみ入ってくる。アンモニア臭とあいまって、目がちかちかしてきた。いつまでも、しゃがんだまま考え込んでいるわけにはいかない。
(しかたがない、本を犠牲に……)
意を決し、ポケットに手を伸ばしかけ、ひらめいた。
(そうだ、俺は軍手を持っていたんじゃないか)
草刈りのときはめていたのを、はずして束ね、ベルトにはさんであった。泥だらけだったが、裏返して、なるべく白いところを探し……。
「つまりお前、軍手でケツ拭いたのかよ」
聞いていた別の男子が言ったのを機に、わっとわいて、女子は、
「やだー」
呆れたような軽蔑したような声を上げ、私も思いきりせせら笑ったが、今となっては、懐かしいような。軍手か文庫本か。トイレから出るに出られずにいた彼にとって、苦渋の決断だったのだ。
「あの頃」から、もう二十年。出版物の大量生産、大量消費の中にいるうちに、本に対し自分は「すれて」きてはいないかと、草むしりの手を止めて、少しく思いにふけったのだった。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする
本の旅人 2000年9月号
KADOKAWAの新刊書紹介をはじめ、小説やエッセイの連載・読み切りも充実。直接お届けする年間定期購読を中心に、書店店頭での無料配布により、「本好き」の読者から絶大な信頼・支持を集める読書情報誌です。
【定期購読のお申し込みは↓】
http://store.kadokawa.co.jp/sho