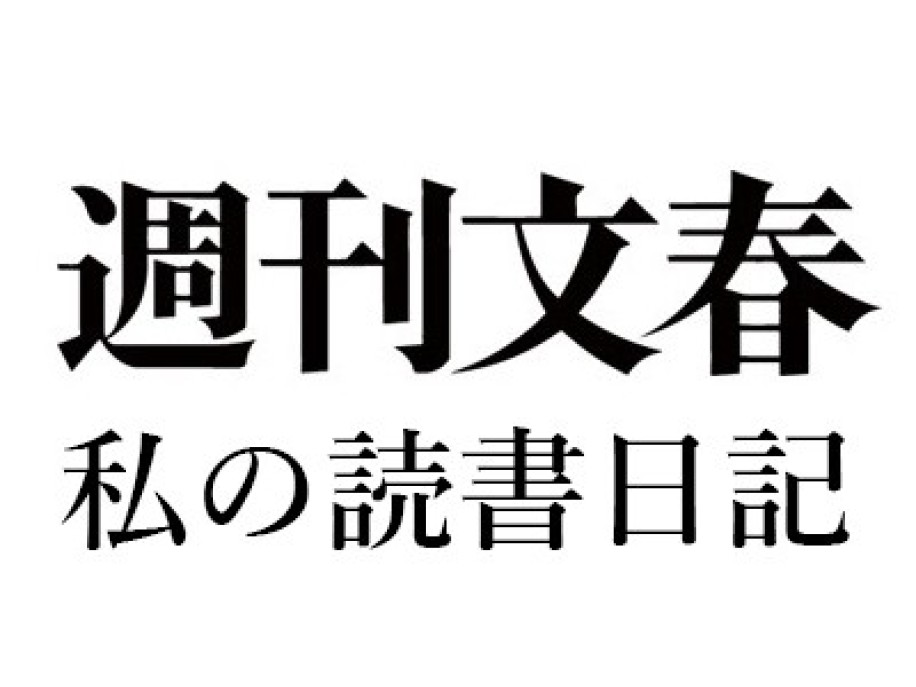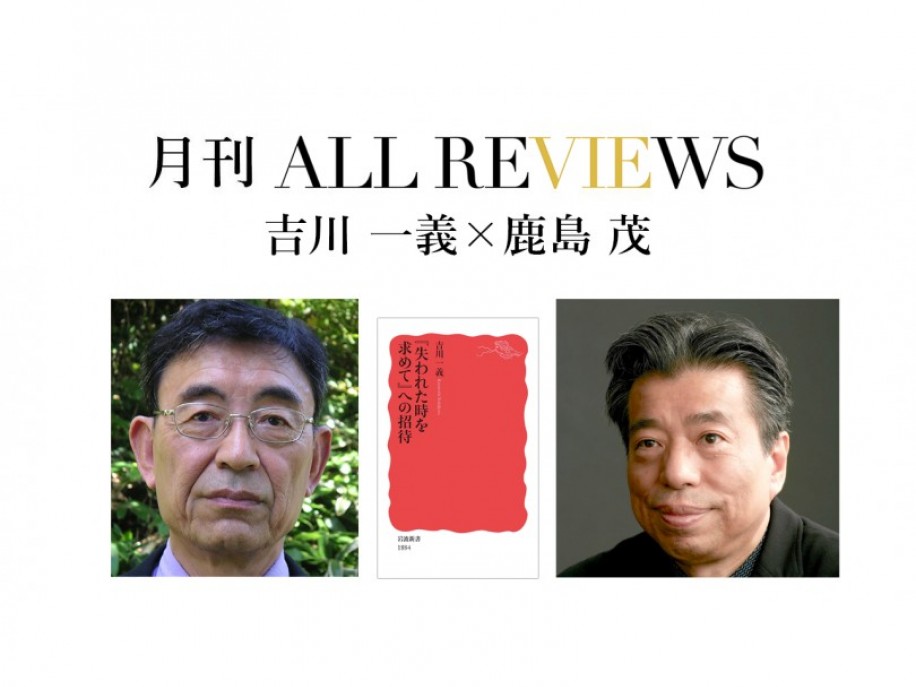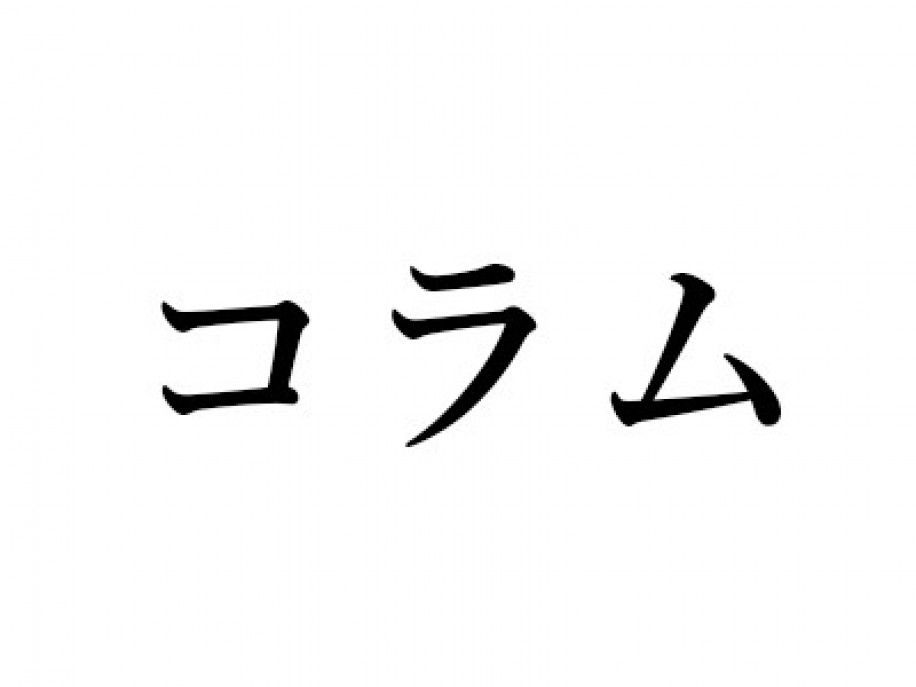コラム
アニエス・ポワリエ『パリ左岸 1940-50年』(白水社)、マラルメ『マラルメ全集』(筑摩書房)、プルースト『失われた時を求めて』(岩波書店/光文社)
「美しい」本、3冊
パリジャンは一見すると貧しく平凡でまったく価値のないように見えるモノや場所に、 ある日突然、 「この美しさがわからないのか? それはあなたがツマラナイ人間だからだ」という、はなはだ唯我独尊的な理由で価値を付与し、実際に、そのモノや場所を特権的なものに変えてしまうという奇跡なような力をもっていると言わざるをえない。たとえば、リーヴ・ゴーシュと呼ばれるパリ左岸。ここは二十世紀になるまで「坊さんと学生の街」として流行とはまったく無縁な場所と考えられていた。
ところが二十世紀に入るやいなや、まずモンパルマスが画家たちに注目される。郊外馬車のターミナルで馬小屋がたくさんあったのがバスやメトロの登場で空き家になったのに目をつけたのだ。次にサン=ジェルマン=デ=プレが注目を集める。 長期滞在できる安ホテルがたくさんあり、 仕事場代わりに使えるカフェがあったからだ。
本書はそうしたパリジャン、 パリジェンヌの「美しい場所」に対する嗅覚の歴史である。
かつて、世界中でフランス文学者がこれほどに多く、しかも、そのレベルが異常に高い国は日本を措いて他にないだろうと言われた時期がある。
その最盛期のフランス文学研究の精鋭たちの叡知が結晶したのがこの全集。
マラルメは世界最難解の詩人である。ゆえに、その全業績を日本語に翻訳しただけでも偉大な事業だが、この全集は内容ばかりでなく装丁もまた世界最高水準の美しい造本となるように努力している。なぜなら、マラルメは自分の詩はタイポグラフィーや造本を含めた最高の美的書籍環境において読まれなければ真に理解されないだろうと考えていた詩人だからである。今後、二度と出版されることがないことが確実なゆえ、目についたら直ちに購入することをお勧めする。
プルーストの『失われた時を求めて』が世界で最も美しい小説であることに異論を唱える人はまずいないと思われる。しかし、その一方で、これほどに読まれない名作というのも珍しい。特に日本では。
その原因はやはり日本語とフランス語の構造的違いにある。関係代名詞や関係副詞を多用して、どこまでも続くプルーストの文体を、関係代名詞や関係副詞というものをもたない日本語で「読める」ようにするのは至難の技であり、これまで何人ものフランス文学者がこの試練に挑んだが決定的な成功には至らなかった。
ところが、二十一世紀に入り、二人の勇気ある訳者がこの難易度の高い試技に挑戦して、ともに見事にこれに成功した。つまり、『失われた時を求めて』を初めて通読可能な日本語に転換したのである。これにより、プルーストはようやく日本でも理解されるに至ったのである。
(初出:WATERRAS BOOK FES 2019)
ALL REVIEWSをフォローする