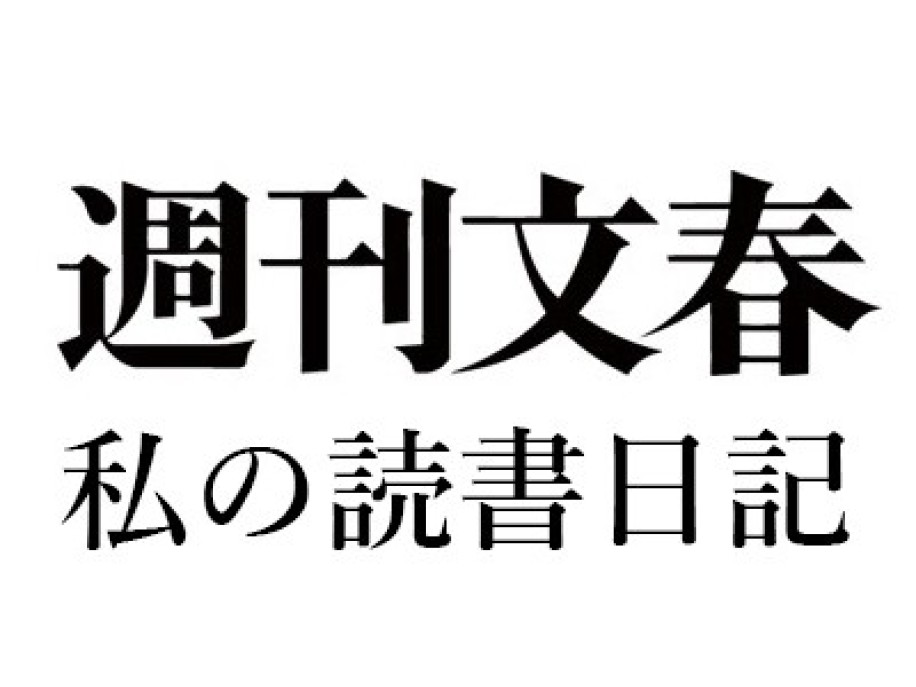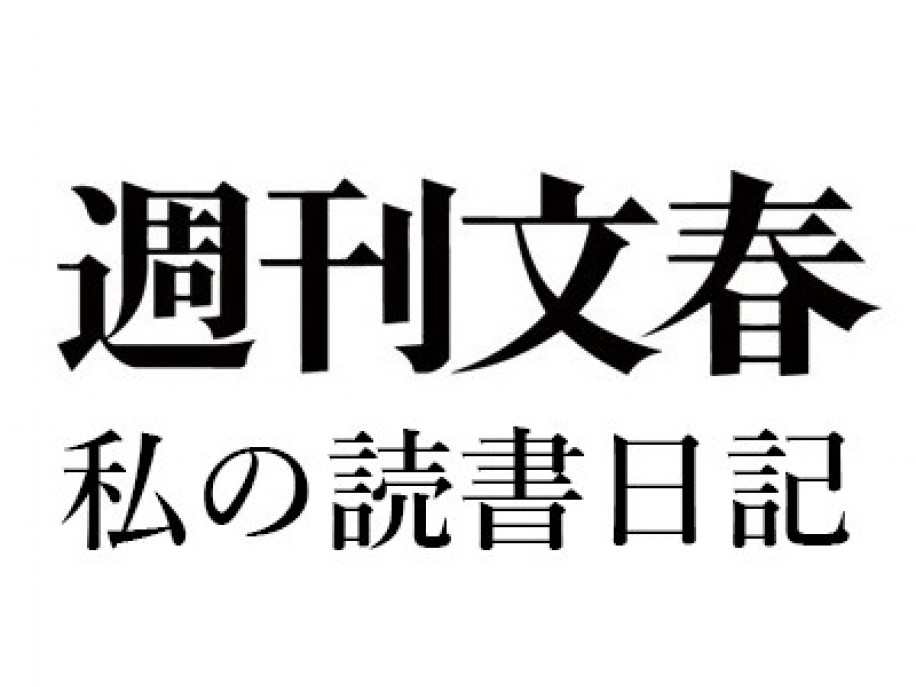読書日記
アンリ・ピレンヌ『ヨーロッパ世界の誕生』(講談社)、ドミニク・チェン『未来をつくる言葉』(新潮社)
ヨーロッパの誕生と「語り得ぬもの」
×月×日
コロナ禍で、文明の後に訪れる大暗黒への予感なのか、にわかに注目されるようになった時代がある。ローマ帝国崩壊後の中世前期である。ベルギー出身の歴史学の泰斗・アンリ・ピレンヌの主著『ヨーロッパ世界の誕生 マホメットとシャルルマーニュ』(増田四郎監修 中村宏・佐々木克巳訳 講談社学術文庫 一六九〇円+税)は、ピーター・ブラウンの『古代末期の形成』に先駆けて、実は「暗黒ではなかった」古代末期に光を当てた古典的名著である。すべては冒頭の一句に要約されている。
ローマ帝国という、人間が作り上げたあの驚嘆すべき建造物のあらゆる特徴の中で、最も顕著なまた最も本質的な特徴は、その地中海的性格であった。
ローマ帝国はゲルマン民族の侵入で崩壊したが、これで一気に無知蒙昧な「暗黒の中世」が訪れたわけではなかった。これがピレンヌが主張する第一のテーゼである。部分的な殺戮や混乱はあったものの全体的にみると旧帝国領がゲルマン各民族の王国に分割されただけで、「ローマ世界 Romania は全く無瑕のまま存続した」のである。原因は、どのゲルマン民族もローマ市民よりも圧倒的な少数(最大限に見積もっても旧帝国領人口の五%)であったうえ、それぞれがバラバラで、征服民に押し付けるべき文明、すなわち言語、文字体系、法体系、宗教(キリスト教アリウス派信仰はあったがこれも弱いものだった)、官僚組織、商業的流通機構、財政・金融システムなどを持たない「蛮族」であったため、あっというまにローマ文化の中に呑み込まれてしまったからである。「ゲルマン民族は帝国を滅ぼそうとも搾取しようともしなかった。蔑視するどころか、かれらは帝国を讃美したのであった」。「ローマ世界 Romania の土壌が、蛮族の生命力を吸い取ってしまったのである」。
では、なにゆえにローマ世界は無瑕でありえたのか? ここで冒頭の一句が蘇る。ローマ世界の心臓部(キリスト教など文化的中心、および貨幣流通などの経済的中心)は地中海にあったから、ローマ世界という船はゲルマン民族に旧帝国領の北半分を侵されても運航を続けられたのである。「古典古代世界の根本を形作っていた地中海的統一が、あらゆる面にわたって明確に維持されていたということである」。
だが、六三二年にマホメットが没し、その二年後からイスラム帝国の猛烈な拡大が始まり、とくにイベリア半島がイスラム圏に入って西地中海が「回教徒の湖」となると、ローマ世界は東方世界(ビザンツ)から切り離されて孤立する。
ゲルマン民族の侵入がそのまま残しておいた地中海的統一を、イスラムが破砕し去った。(中略)古代の伝統の終焉であり、中世の開幕であった。
では、何をもってこう断言できるのか? まずローマ世界の「紙」だったパピルスが消え、香辛料も消えた。ワインも絹も消えた。しかし、それ以上に深刻だったのは金が消えたことである。これによってガリアではソリドゥス金貨が消えてデナリウス銀貨だけになり、国際的な職業商人の支配する大市(フォワール)が消え、近傍の農民と小売商人だけの市場(マルシェ)が生まれる。「商業が衰してしまい、その結果、土地が嘗てないほど経済生活の本質的な基礎になった」。シャルルマーニュのカロリング朝ではメロヴィング朝の国庫財源だったソリドゥス金貨が流通機構ともども消えうせたため、国王は直轄地の収入以外には経常財源を持たない王となったのである。自給自足経済が広まり、教会や修道院は寄進地を拡大し、ローマ教会の影響力が強大となり、かくて封建制と教会の中世ヨーロッパが生まれたのである。
ホイジンガの『中世の秋』と対をなすような不朽の名著である。
×月×日
いまから五十年近く前のこと。登場してきたばかりの構造主義・ポスト構造主義の著作を読もうと四苦八苦していたが、いまになると、そのわからなさの原因だけはよくわかる。フーコーにしろラカンにしろデリダにしろドゥルーズにしろ、その著作が理解困難だったのは、彼らが一様に己のうちなる「語り得ぬもの」を語るには、語るという行為そのものによって語る以外にはないと考えていたからなのである。この意味で彼らの著作はすべて哲学であると同時に文学であり、なおかつ自伝なのだ。これではフランス語をかじり始めたばかりの日本人学生にわかるわけはない。たぶん翻訳者もわからなかったのだろう。ドミニク・チェン『未来をつくる言葉 わかりあえなさをつなぐために』(新潮社 一八〇〇円+税)は自伝というかたちでしか語り得ないものがあると悟ったところから出発して、すべての人に向かって開かれるべきコモンズ(共有知)をどのように構築したらいいかを探ろうとした「哲学であると同時に文学」であるような本である。
著者は台湾出身の多言語使用者(ポリグロット)の父と日本人の母との間に生まれ、東京のリセ(フランス人学校)からパリのリセに転じ、アメリカの大学で学んだ。ファミコンでゲーム世界に惑溺するかたわらコンピュータ言語を習得して「環世界」を拡大していったが、十代はじめに「吃音」というバグを発症する。ところが、この吃音の対処法を考える過程を意識に反転させるうちに一つの「思想」を獲得する。「この後で吃音が生じるだろうという気配が察知されると、その予感の塊が到来する前にもっと口に出しやすい言葉が意識のなかで検索され、準備される。(中略)吃音という、制御不可能な『他者』との対話の結果、選ばれた言葉が発話されるのだとすれば、それを積極的に受け容れた方が良いのではないか、というマインドセットがいつからか生まれたように思う」。
もう一つの思想形成のきっかけは、パリのリセで落第勧告を受け、両親のいるロスに移ってフランス人リセの優秀な哲学教師から正反合の弁証法をたたき込まれたことである。
「正反合を学ぶ際にフランスの教師が教えるのは、あらゆる設題に対して論を構築できる方法論であって、内容は定まっているわけではない」。「構造に十分な強度があれば、たとえ意見が異なっていてもコミュニケーションの回路が開ける」。
この弁証法を完全マスターし、教師から満点の二十点をもらえたことから日仏のアイデンティティの揺らぎに苦しむことがなくなった。
大学はUCLAのデザイン/メディアアート学科に進む。東京のリセ在学中に美術授業でコラージュとフロッタージュのおもしろさに目覚めるとともにデジタル画像処理を独修し、「言葉でしか記述できない事象もあるが、言葉の網からこぼれ落ちる事象もまた、世界に満ち溢れているということ」に気づいたからである。そこから在学中にクリエイティブ・コモンズの運動に参加し、その日本支部の設立へと至るが、さらなる転換は娘が生まれたことによってもたらされた。
彼女の身体がはじめて自律的に作動したその時、自分の中からあらゆる言葉が喪われた。同時に、とても奇妙なことだったが、いつかおとずれる自分の死が完全に予祝されたように感じられた。(中略)求めていきたいのは、娘が生まれた瞬間に体験した、あの不思議な時空を表すための言葉だ。(中略)この奇妙な感覚に名前を与えずして、自分の思考を進めることはできない気がする。
このように、環世界のチェンジで生まれる「奇妙な感覚」を言葉に変えるという孤独な作業をサイバー空間を通じて他者とともに行なっていくこと、これが著者が自らに課した課題である。言葉を介して他者を自己のうちに取り込んでいく未完の自伝というフィードバック形式でしか達成され得ないまったく新しい試みといっていい。
ALL REVIEWSをフォローする