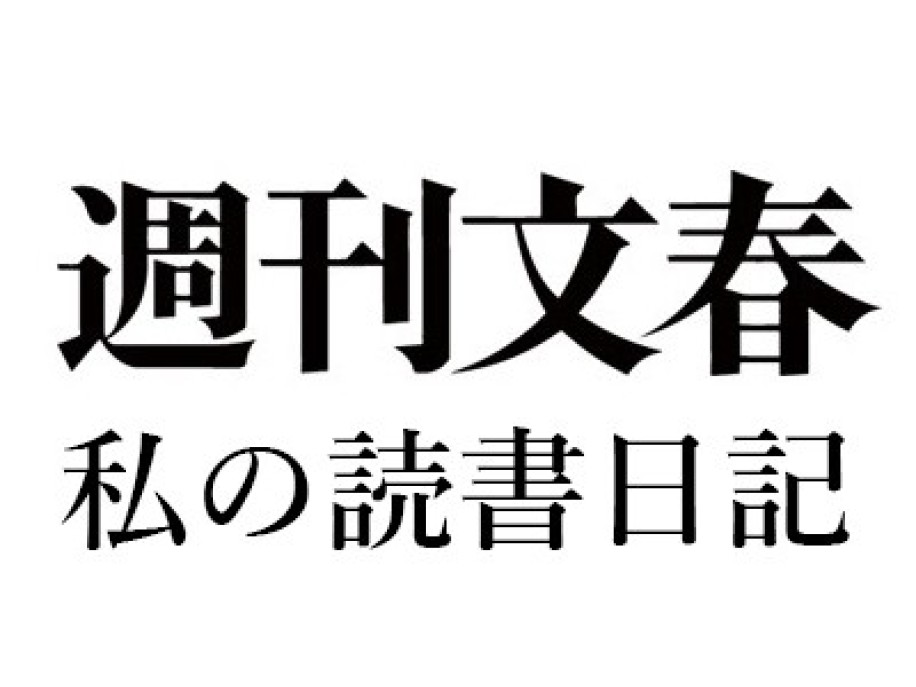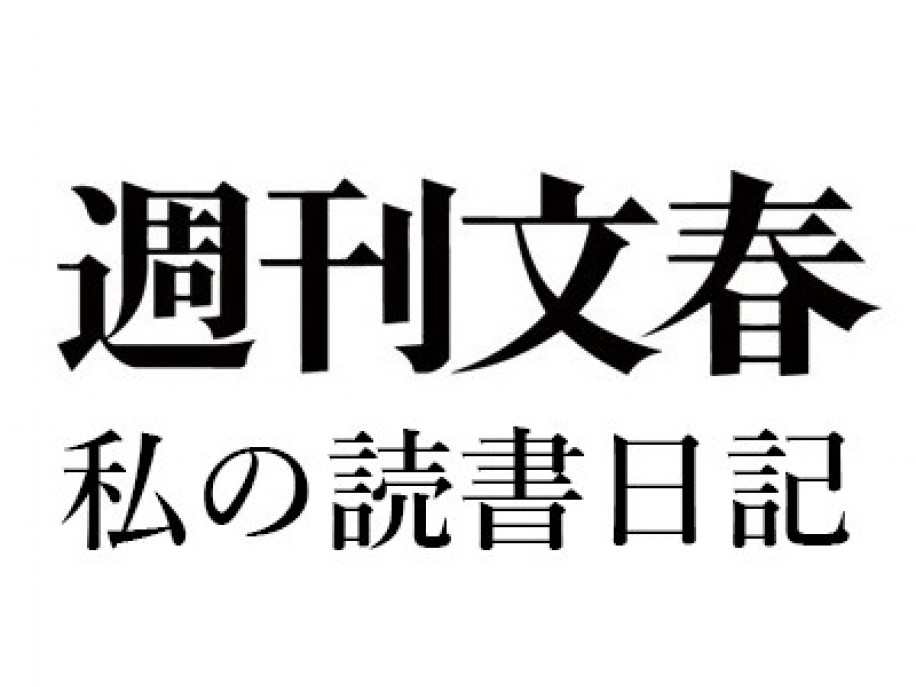読書日記
リード・ヘイスティングス,エリン・メイヤー『NO RULES 世界一「自由」な会社、NETFLIX』(日本経済新聞出版)、じゃんぽ〜る西,カリン西村『フランス語っぽい日々』(白水社)
革命的組織論と異文化考察
×月×日
アメリカ大統領選挙の大混乱を見ていると、アメリカはいずれ中国に覇権を奪われるのではないかと心配になってくるが、しかし、ストリーミング映像配信の大手ネットフリックスの創業者でCEOのリード・ヘイスティングスがINSEAD教授のエリン・メイヤーとの共著で出した『NO RULES 世界一「自由」な会社、NETFLIX』(土方奈美訳 日経BP-日本経済新聞出版本部 二二〇〇円+税)を読む限り、杞憂であると結論せざるを得ない。ネットフリックスで実証されたようにイノベイションを促すのは自由と批判精神しかないが、一党独裁型の中国ではまさにこの二つこそ最大のタブーであるからだ。自由と批判精神のない国ではイノベイションは起りえず、したがって中国がアメリカを追いこすことはない。一九九一年、リード・ヘイスティングスはバグ発見用ソフトの開発会社「ピュア・ソフトウエア」を創業するが、規模が拡大するにつれて業績が悪化したためこれを売り払い、その資金で一九九八年にオンライン郵送DVDレンタルのネットフリックスをマーク・ランドルフとの共同経営で創業する。ネットフリックスは急成長し、店舗型巨大ビデオレンタル会社ブロックバスターとの死闘にも勝利し、ストリーミング配信の開始とともにグローバル企業へと発展してゆく。だが、その間、危機もあった。二〇〇一年のネット・バブルの崩壊である。ヘイスティングスは人事担当のパティ・マッコードとともに社員一二〇人のうち四〇人を指名解雇し、「引き留め組(キーパー)」八〇人で再スタートする。「社員の3分の1がいなくなった。それにもかかわらず社内には突然、情熱、エネルギー、アイデアが満ち溢れるようになった」。この経験からヘイスティングスは教訓を引き出す。社員能力の「密度」が高まり、ヘイスティングス自身も出社するのが待ち切れないほどのワクワク感が生まれたのだ。「能力密度が本当に高い会社こそ、誰もが働きたいと思う会社なのだ、と私たちは気づいた。とりわけ優秀な人材は、全社的な能力密度が高い環境で真価を発揮する」。
いまや「ピュア・ソフトウエア」がなぜ身売りに追い込まれたのか、その原因も把握できた。最高のメンバーと凡庸なメンバーが混在するチームでは前者が後者のレベルに合わせざるをえなくなり、その結果、最高のメンバーがやる気をなくし、全体のレベルが低下、状況はスパイラル的に悪化する。イノベイティブな人材にとって最良の職場とは才能豊かで協調性のある仲間と「だけ」働ける職場なのだ。これが「ネットフリックス」の前提となり、他の社是はすべてここから演繹される。
たとえば、最高のメンバーだけを揃えたいなら、当然、報酬も業界最高とならなければならないが、報酬財源には限りがある。どうするか?「ロックスター」の原則を適用するのである。すなわち、プログラミングのような職種では平均的エンジニア一〇〜二五人に匹敵するロックスター級のエンジニアを雇いたいなら、一〇〜二五人分の給料を一人のロックスター級エンジニアに渡すしかない。「最高のプログラマーの価値は凡人の10倍どころではない。100倍はある」。もちろんこの原則が適用されるのはクリエイティブ部門だけで、現業は別体系だ。
しかし、「ネットフリックス」が凄いのはこの先だ。社員が自分の市場価値を把握できるようにヘッドハンティングを受けたら、オファーされた給与を会社に知らせるように指導するのだ。会社は人材の市場価値に見合った額を再提示する。また、出張経費や休暇などの規定は創造性発揮に妨げがあるので、これを撤廃するが、代わりに遵守すべきコンテキスト(おおまかな倫理)を最初に示し、自由と責任を内面化させる。「自由を与えることで支出が少し増えたとしても、社員が飛び立てない職場をつくるのに比べればまだ安い」。もっとも、こうしたシステム改善なら他社でも模倣できる。模倣困難なのは「ネットフリックス」が長年かけて築き上げた透明性の文化だろう。社員に対し、自分も経営陣の一員だと思わせるために財務透明性を重視。さらに社員に財務教育を施して会社のオーナーという当事者意識を持ってもらうが、その分、大幅な自由裁量権も与える。専門分野の「情報に通じたキャプテン」は賭けるに値すると判断した事業計画には上役の承認なしでサインできる。しかも、失敗しても、次の成功への布石となるようなフィードバック(率直な意見の交換とそれを自己改善に生かすこと)がなされるならば、むしろ励まされる。これだけでも普通の会社は容易に模倣できないが、しかし、ネットフリックスの神髄はフィードバックを縦と横の人間関係にも適用したことである。「ネットフリックスは率直なフィードバックを促すだけでなく、頻繁にそれをするよう求めている」。しかし、こうした率直なフィードバックは傷つけ合いになるからリスクが高い。とくに上司に対するフィードバックは普通の会社なら高リスクである。そのため、ネットフリックスでは上司はフィードバックが期待される行動であることをまず部下に伝え、さらに部下からフィードバックがなされたら帰属のシグナル(あなたは率直さにより仲間になった)を送る。さらにネットフリックスではこのフィードバック文化の徹底のために四つのガイドラインをたたき込む。すなわち、フィードバックを与えるときは①イライラを吐き出したり意図的に傷つけるのではなく、相手を助ける気持ちで行い、②それを受けた相手が行動を変えられるようにする。またフィードバックを受けたら③自己弁護せずに感謝するが、④受け入れるか否かは、本人次第であることをフィードバックの与え手も受け手も理解しておく。いずれも、普通の会社ではそう簡単には達成できることとは思えないが、しかし、ネットフリックスの急成長がまさにこのフィードバック文化の醸成によって支えられたのはまぎれもない事実なのである。
政党や学校、NPOなど、他分野にも応用可能な革命的な組織論である。
×月×日
バイリンガルな家庭の子供の言語的発達を記述した本はどれもおもしろいが、日本人の漫画家のじゃんぽ〜る西さんとフランス人の奥さんのリベラシオン特派員カリン西村さんの『フランス語っぽい日々』(白水社 一八〇〇円+税)は、漫画とエッセイによる鏡像的異文化考察という点でかなり異色である。夫妻は、子供をバイリンガルに育てるには、父親は日本語で、母親はフランス語で話しかけるべしという知人の日仏カップルのアドヴァイスに従う。観察していると、話し始めた子供はある概念を表現するのに単語が短い方の言語を使う。たとえば、象はéléphantではなく「ぞう」、電車は「でんしゃ」ではなく「たん(train)」という具合。保育園に行くようになると日本語でしか話さなくなったが、母親の妹が来日して仏語環境がかたちづくられると、突然、フランス語を話し始め、最後に「Nao aussi va en France!(七央もフランス行く!)」と言ったのが興味深い。フランス人の子供なら自分の名前Naoを主語に立てることはないはずだ。いっぽう、母親が「Tu veux manger?(食べたい?)」と尋ねると、「Tu veux manger(食べたい)」と答えた(正しくはJe veux manger)のは、フランスの子供でもあり得る間違いだろう。母親は否定疑問への日本式答えにも戸惑う。「わたしが息子に『寒くない? Tu n'a pas froid?』と聞くと、彼は『うん oui』と答えます。(中略)フランス語では、寒いのなら《si はい》、寒くないなら《non いいえ》」。
連載媒体が語学雑誌の「ふらんす」だったこともあり、子育てを通した立派な比較言語研究となっている。
ALL REVIEWSをフォローする