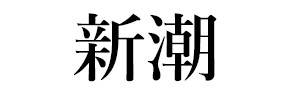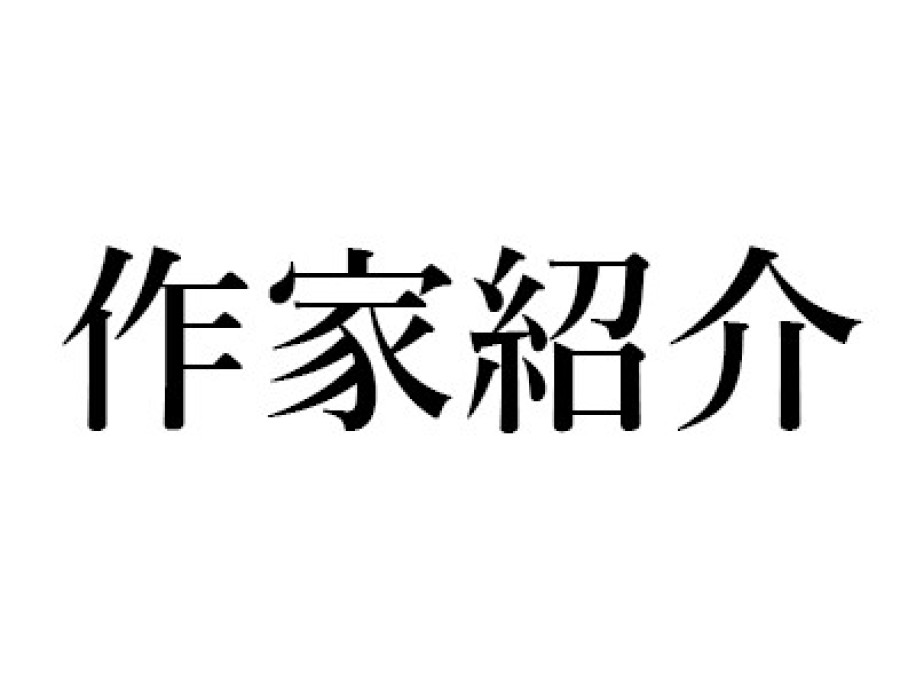対談・鼎談
星野 智幸『目覚めよと人魚は歌う』(新潮社)|星野 智幸×野谷 文昭による対談
クレオールと混血
野谷 僕は星野君の小説を読んでいると、ときたま笑ってしまうんです。ユーモアがあるんだけれども、ギャグによって笑わせようというのではない。文章自体から立ち上がってくるユーモアなんですね。これは今の作家にはあまりない特徴です。特に受賞作はそうで、冒頭の文章は笑ってしまうね。星野 ああ、そのご指摘、とても嬉しい批評です。発話し行動している登場人物は至って真面目なんです。でも、読む側までその真面目さにシンクロする必要はないんですよ。
野谷 マルケスやセルバンテスの場合、極めて深刻に書いている部分がもっともユーモラスだったりするんですね。星野君も、その二人を読むことによってこの感覚を身につけたんでしょう。
星野 これはラテンアメリカというよりスペイン的なのかもしれないけれども、強烈なリアリズムが行き過ぎておかしさが生まれることがありますよね。
野谷 その系譜はスペインだとセルバンテスやブニュエルだけれども、日本でも向こうでもマイナーだね。やはり真面目な方が主流ですから。
星野 受賞作の冒頭は、安っぼいポエジーの言語ととられれば文学主義と排斥されるでしょうし、ズレを出すための言語と見做されれば好意的に受け取ってもらえるようです。そこが評価の分かれ目なんでしょう。きちんとユーモアにまで昇華しきれているかどうかは、自分では判断つかなかったわけですが。
今回の受賞作を執筆中、特に確認事項としていたのは、小説内での現実レヴェルはしっかり固めておくということでした。そうすれば、糖子の言葉は現実からズレたものとして読まれうる可能性があるわけです。しかし、どれが現実か分からんよこれでは、と言われてしまえば、終わりですね。真面目にズレているのに、単なる何でもありの状態と捉えられてしまう。
野谷 言葉同士がぶつかり合って出てくるショックを、すごく感じますね。ただ、“ラテン系日本語”という評もあったようですが、実際には、“混血”と言っても、ラテンアメリカ人や日系人の深層心理にまで入りこんで書いているわけではないとも言える。あくまでも想像の世界に過ぎないと。
星野 それを言ったら、作家は全て自分のアイデンティティしか書けないということになってしまいます。逆に、日系人のことは日系人にしか分からないということになりますね。僕は、それを越えたいと思って書いているんです。僕が“混血”というのは、混血していない人も混血だ、という意味も含まれています。そういう意識に、全てを並べてしまいたいんです。
野谷 それは日本の差別問題と関わってきそうですね。でも、星野君の場合、リアリズム的に混血というパターンを作ってしまって、それを動かしているわけではない。むしろ、運動体としての“混血”をやっていると思うんです。混血のバランスが作品の中でも変わってゆくんですね。
星野 “混血”という言葉に固定したイメージや観念がありますから、この用語を使うのは本当は適切でないのかもしれませんね。
野谷 混血というのは、もともとどんどん動き、変化してゆくものでしょう。あなたの作品を見ていると、動くものとしての混血が描かれていますね。クレオールという概念と近いところがあります。また、常に動いていないと、長所が死んでしまう。
星野 なにしろ、トポスがないわけですからね。
野谷 形ができた時には、それが同一性になってしまうでしょう。
星野 ないことをないままやっていって、どう生き延びるかという問題なんです。
問題意識を持つ作家
野谷 星野君は、作品を発表しはじめてから、結果的には最短距離でこういう賞を受賞してしまった。そのため、これまでの小説は、すべて、“混血”という考え方の範疇に入ると思うんです。そしてその中で実験をしてきた。したがって、この枠組み自体をどう壊してゆくかという問題があります。以前、『最後の吐息』を書評したときにも指摘しましたが、このまま書き続けてゆくことの危うさをやはり感じるわけです。今の形でどこまで続くのかと。
確かに、初期の作品と比較すると、同じ混血といっても、地に足がついてきて、リアリティがでてきましたね。アイデア先行だったのが、具体的なものとして書けるようになってきた。これからまだ同じ路線でゆくのか、クラシカルなことをするのか、あるいは、立松和平さんや藤沢周さんみたいに、文体を壊すために、ポルノ的な作品を書くのか。いろいろな方法を見てみたい気もするし、このままの路線で長篇を書いてもらいたい気もする。松浦理英子さんの「波」の書評も、この素材でなぜ長篇が書けないのか、という気持があったと思います。
ただ、今のスタイルで長篇を書くのは難しいかな。コルタサルの『石蹴り遊び』のような形にしないと続かないかもしれない。挑んでみる気はありますか?
星野 もちろん、長篇を書いてみたいという気持はあります。ただ、今回の作品で、最初の作品からやりたいと思ってきたことを、一応実現したと思っているんです。それと同時に、書きながら感じていたことですが、少し機械的というか、惰性になってきたという気がしている。これを続けていれば楽になるのかもしれませんが、やはり、まずいと思います。せっかく受賞させて頂いたことですし、まったく新しい試みを導入してみたいと考えているところなんです。どういうことを試みるかはまだ固まっていないので、上手く説明できないのですが、長篇に繋がるものだと思います。長篇は、骨組みや場所をしっかり構築しないと書けませんからね。その点に重点的に取り組んでみたいと思っています。
野谷 ポスト中上、という批評にはどう応えますか。
星野 僕は中上健次のこだわっていた問題をずっと考え続けて います。特に、未完のままで終わった晩年の作品群について考えることは多い。しかし、中上健次については今、一つの語られ方のフォーマットが決まっている気がするんですね。新しい読みと言いながら、実際は縮小再生産だという印象がある。そういう面にはもうコミットしたくないですね。また、そのフォーマットの延長で僕の作品を論じてもらっても、何も言っていないに等しいと思います。僕は、今語られている中上の外側の可能性について考えたいです。だから、今後の小説でも中上の抱えたテーマは引き継ぐと思いますが、最初の作品のように、出典をあからさまにするようなことはもうやらないでしょう。必要もないし。
野谷 中上だって、初期は大江健三郎そのままだと分かるような事をやっていましたからね。あるいは、フォークナーからの影響もはっきりしていた。ただ、それはもともと持っている文学的な現実と合致したから、彼の世界ができたんだと思います。いくらある作家に心酔したとしても、自分の持っている資質や素材に合わなければいい作品はできないでしょう。星野君の場合は、もともと持っている問題意識が、マルケスや中上を呼び寄せたのであって、単に真似をしたということではないと思います。
星野 確かに、自分の問題の方が先でした。
野谷 星野君のいいところは、問題意識を持っていて、実験を厭わないところですね。でも今回の作品では、ちょっと上手くなりかけているんですよ(笑)。それはそれでいいことなんだけれども、危ういところに来ているとも思う。上手くなってしまうと、惰性で書けてしまいますからね。それを自己批評して、また別のステージに抜けようとしているわけで、頼もしい限りです。むしろ、これからの期待が大きい。どんな新しいステージが現れるのか楽しみです。
星野 新ステージで上手く踊れるよう、またサルサを練習しておきます。
ALL REVIEWSをフォローする