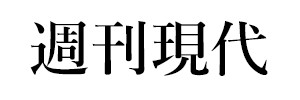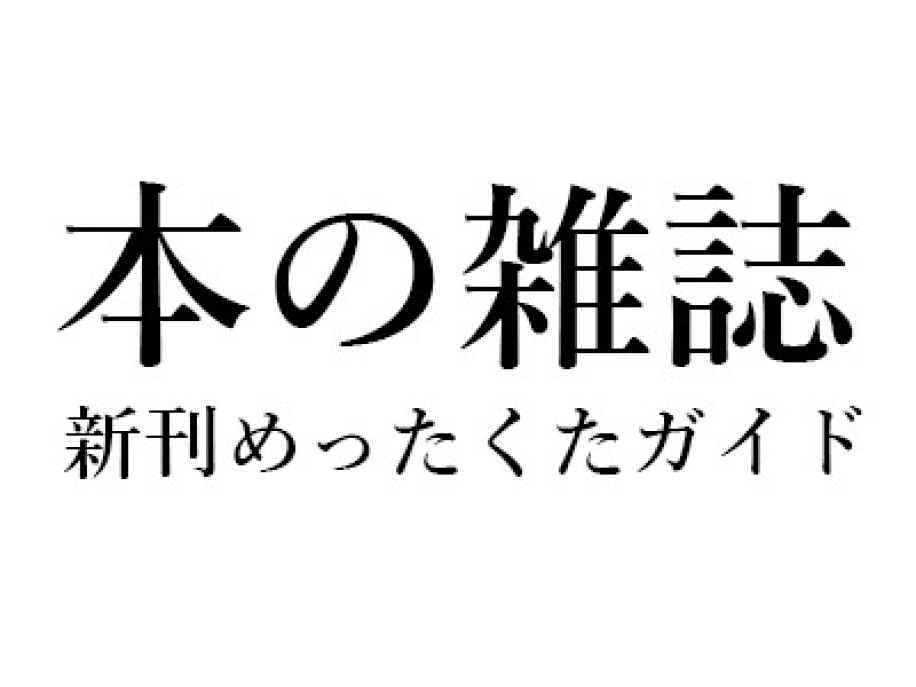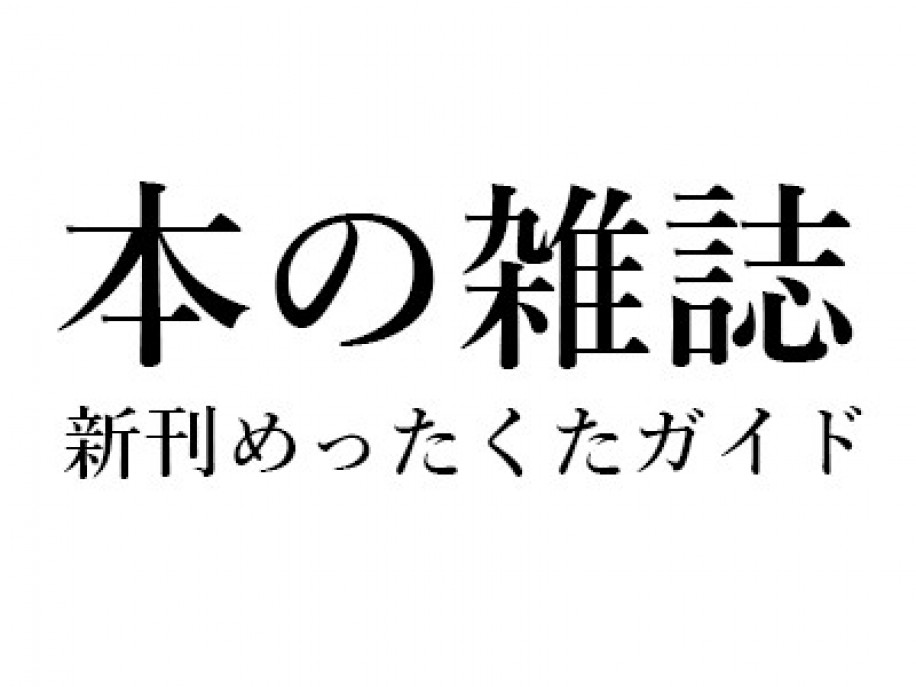書評
『ねたあとに』(朝日新聞出版)
避暑地の山小屋に集まってひたすら風変わりな遊びに興じる”大人たち”のひと夏の黄金時代
毎年、夏の数日を避暑地の山小屋で過ごす小説家ナガヤマコモローとその父ヤツオ、そしてこの山小屋にやってくる友人やそのまた友人たちの遊ぶ様子”だけ”を描いた、考えようによってはかなり挑発的な長編小説なのである。朝日新聞夕刊に連載されていた(‘07年11月から’08年7月)当時、読者の間で「もしかして明日も遊んでるとか?」「いやずっとそうかも」と、不安と期待が混じった予測が飛び交ったらしいのだが、それは多分、新聞小説としては明らかに異色の「大人がひとところで遊び続ける話」を、堂々と飄々と書き続けた長嶋有という作家の過激さを見抜いた愛読者からのエールだったのだと思う。
避暑地での遊び、と言ってもアウトドア系ではなく室内限定、しかもナガヤマ家の面々が編み出したオリジナルなものばかり。麻雀牌の数と性質をうまく使った「ケイバ」、サイコロの目の数で人間のプロフィールを作ってゆく「顔」など、アナログ感あふれる遊びの数々がコモローの友人・久呂子(クロコ)さんの視点で紹介されていくのだが、ナガヤマ父子のどこか意固地で大人げない興じ方に笑わされながら読んでいくうちに、遊びのルールを久呂子さんが理解するのと同じスピードで読み手側も理解していくという”時間の速度調整”がなされていることに気付いてはっとさせられる。目が文字を追う速度と分かる速度が重なっていくよう、言葉の量と順序が注意深くコントロールされているのだ。
的確な言語の凄さ
”場所と感情の相関関係”も、小説の重要なポイントだ。山小屋で久呂子さんが感じたことはすべて、山小屋という場所と分かち難く結びついている。ある場所で得た気持ちはそれが生まれた場所と切り離せないということを、久呂子さんは毎夏、山小屋を訪れるたびに知る。誰にでも覚えがあるであろう”自分の感情を再訪問する”という感覚を、著者はきちんと言葉にしてみせてくれている。小説の面白さはどんでん返しや意外な犯人が登場することだけにあるのではなく、日々の中で言葉にしないようなことが的確に言語化されている文章に出会えることにもあると思うのだけれど、この『ねたあとに』はまさにそんな文章が詰まった、著者の信念と自信が窺える一冊なのだ。
ALL REVIEWSをフォローする