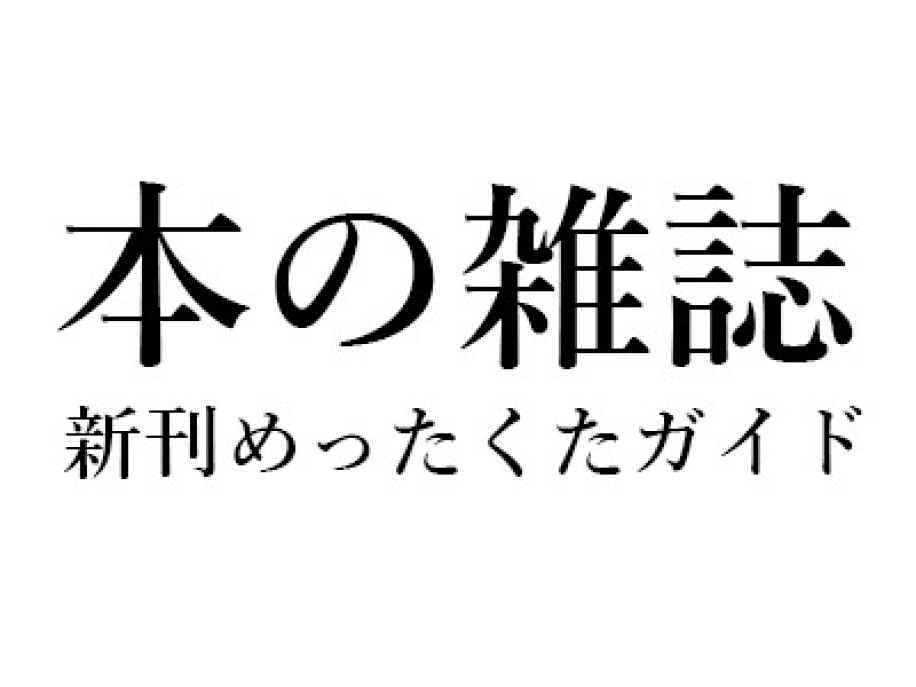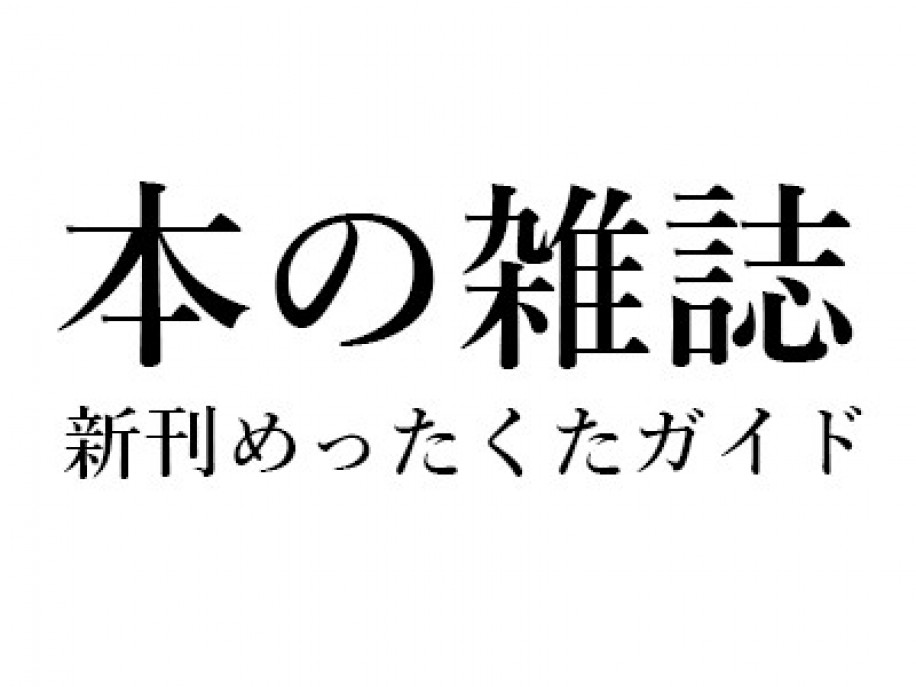書評
『パラレル』(文藝春秋)
〈なべてこの世はラブとジョブ〉。大学在学中にバブル崩壊を経験し、不景気のまっただ中に働き盛りの三〇代を迎えた世代の、ラブ&ジョブの一〇数年を、いくつかのパラレルな男×男、男×女関係に託して描く長嶋有の新作小説は、読み手を宙ぶらりんな気分にさせずにはおかない。この作品は、右から左へ物事を整理してパッケージングするために書かれてはいないからだ。むしろ、あらゆる判断や価値観に留保をつけたがっているような気配さえ漂う。そこが面白い。
語り手の〈僕〉が呟くこの言葉は、安保がどうの権力闘争がどうのと政治意識の有無を声高に語る世代や、その手の物言いにへきえきしてサブカルチャーに逃げこんだ世代、また就職に苦労もせず、ハブルに浮かれ消費の快楽を覚えた世代といった、〈僕〉たちよりも年長の世代に対するささやかな意義申し立てのようにも感じられ、そこがまた面白い。
九一年、〈「災害時の非難場所は『東大』です」と大書されて〉いる〈さほど偏差値の高くない私立大学〉(多分、新入生歓迎パンフレットに載せる周辺地図で東京大学のことを”頭の狂った大学”と表記し、自分たちの学舎を”頭の幼い大学”と自嘲する、あの大学のことでしょう。わたしもそこの学生でありました)で知り合いになった〈僕〉と津田。どちらかといえば、自己主張の激しくない〈僕〉と比べて、津田は野心家で女性関係も派手。物語はこの二人を軸に進行していく。
大学在学中からゲーム業界にもぐりこみ、ヒット作も飛ばしたものの売れればいい式の創造性を否定するやり方に嫌気がさし、ゲームデザイナーとしての仕事は休業状態に入っている〈僕〉。父親が事業に失敗したせいで大学を中退、インターネットがなかった時代にパソコン通信の会社を興し、死にものぐるいで働いた結果、いっぱしの社長になった津田。性格的にパラレルなこの二人は、しかし、要所要所で接近し、今現在お互いがどんなふうに社会と向き合い、女とつきあっているかを確認しあう。
離婚後も連絡をとり続けてくる元妻との暖昧な関係にとまどっている〈僕〉。結婚はせずに、複数の女を〈パラで走らせている〉キャバクラ好きな津田。〈僕〉と津田のパラレルな関係、〈僕〉と津田の女性とのパラレルな関係。平行するふたつの人生の間で、たくさんの感情や理屈がそれぞれを持て余しているかのように、ふらふらと漂っている。
そのパラレルな状態が、最後、あるエピソードによって平衡を崩すシーンが見事だ。倒産してしまった津田。自殺するんじゃないかと心配した〈僕〉は、津田が母親と二人で住んでいた千葉の団地にタクシーを飛ばす。その団地の屋上で二人が交わす会話がいい。津田と〈僕〉、二本の平行線が一本に重なりあう、すっきりと清潔な絵が目に浮かぶのだ。でも、それはおそらく一瞬の重なり合いで、〈僕〉と津田の人生はまたパラレルな状態に戻ってしまうのだろう。二人はこれからも、人生で思いがけず起きることや、そこから生じる想いに暖昧に翻弄され、そうした感情のほとんどは、はっきりとした決着を見ないに違いない。
でも、それでいい。いや、生きるということは、そもそもそういうどっちつかずの宙ぶらりんな日常を、肯定するでも否定するでもなく、諦めるでも抵抗するでもなく、たくさんの感情と理屈に動揺しながら“こなして”いくことなのかもしれない。……とか何とか、そんないろいろなことを読み手に考えさせるだけの力が、この作品にはあるのだ。どちらかといえば、脱力系の語り口にもかかわらず。曲者ですね、長嶋有は。
【この書評が収録されている書籍】
どんな事柄であれ、正しさを主張する人間は色気を失う
語り手の〈僕〉が呟くこの言葉は、安保がどうの権力闘争がどうのと政治意識の有無を声高に語る世代や、その手の物言いにへきえきしてサブカルチャーに逃げこんだ世代、また就職に苦労もせず、ハブルに浮かれ消費の快楽を覚えた世代といった、〈僕〉たちよりも年長の世代に対するささやかな意義申し立てのようにも感じられ、そこがまた面白い。
九一年、〈「災害時の非難場所は『東大』です」と大書されて〉いる〈さほど偏差値の高くない私立大学〉(多分、新入生歓迎パンフレットに載せる周辺地図で東京大学のことを”頭の狂った大学”と表記し、自分たちの学舎を”頭の幼い大学”と自嘲する、あの大学のことでしょう。わたしもそこの学生でありました)で知り合いになった〈僕〉と津田。どちらかといえば、自己主張の激しくない〈僕〉と比べて、津田は野心家で女性関係も派手。物語はこの二人を軸に進行していく。
大学在学中からゲーム業界にもぐりこみ、ヒット作も飛ばしたものの売れればいい式の創造性を否定するやり方に嫌気がさし、ゲームデザイナーとしての仕事は休業状態に入っている〈僕〉。父親が事業に失敗したせいで大学を中退、インターネットがなかった時代にパソコン通信の会社を興し、死にものぐるいで働いた結果、いっぱしの社長になった津田。性格的にパラレルなこの二人は、しかし、要所要所で接近し、今現在お互いがどんなふうに社会と向き合い、女とつきあっているかを確認しあう。
離婚後も連絡をとり続けてくる元妻との暖昧な関係にとまどっている〈僕〉。結婚はせずに、複数の女を〈パラで走らせている〉キャバクラ好きな津田。〈僕〉と津田のパラレルな関係、〈僕〉と津田の女性とのパラレルな関係。平行するふたつの人生の間で、たくさんの感情や理屈がそれぞれを持て余しているかのように、ふらふらと漂っている。
そのパラレルな状態が、最後、あるエピソードによって平衡を崩すシーンが見事だ。倒産してしまった津田。自殺するんじゃないかと心配した〈僕〉は、津田が母親と二人で住んでいた千葉の団地にタクシーを飛ばす。その団地の屋上で二人が交わす会話がいい。津田と〈僕〉、二本の平行線が一本に重なりあう、すっきりと清潔な絵が目に浮かぶのだ。でも、それはおそらく一瞬の重なり合いで、〈僕〉と津田の人生はまたパラレルな状態に戻ってしまうのだろう。二人はこれからも、人生で思いがけず起きることや、そこから生じる想いに暖昧に翻弄され、そうした感情のほとんどは、はっきりとした決着を見ないに違いない。
でも、それでいい。いや、生きるということは、そもそもそういうどっちつかずの宙ぶらりんな日常を、肯定するでも否定するでもなく、諦めるでも抵抗するでもなく、たくさんの感情と理屈に動揺しながら“こなして”いくことなのかもしれない。……とか何とか、そんないろいろなことを読み手に考えさせるだけの力が、この作品にはあるのだ。どちらかといえば、脱力系の語り口にもかかわらず。曲者ですね、長嶋有は。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
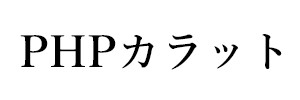
PHPカラット(終刊) 2004年12月
ALL REVIEWSをフォローする