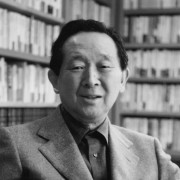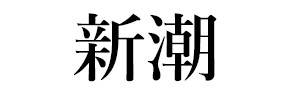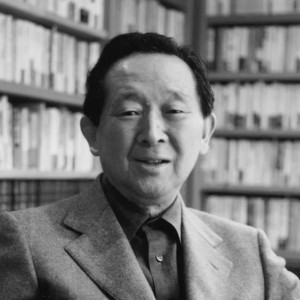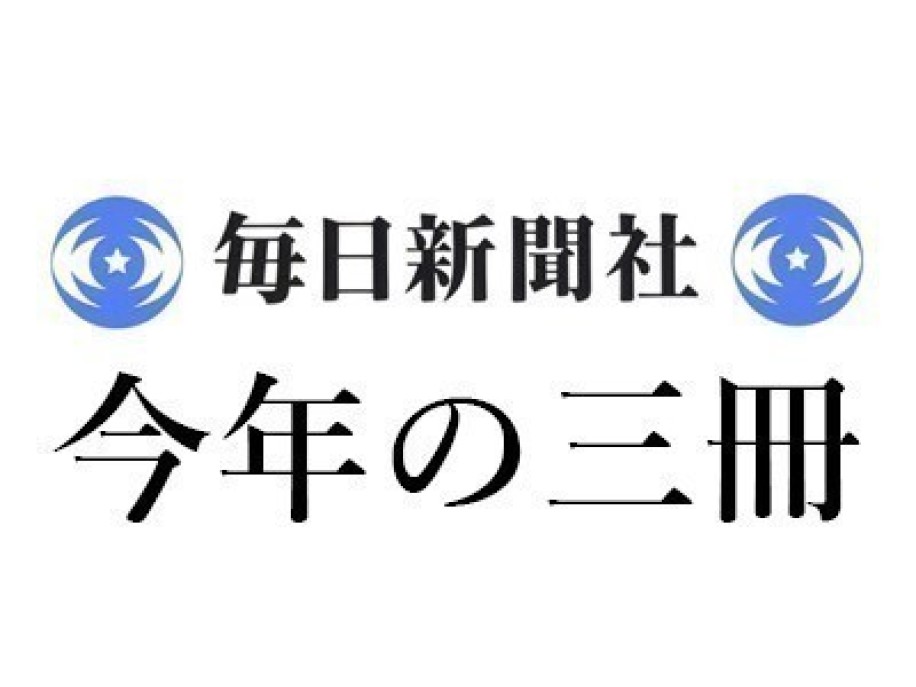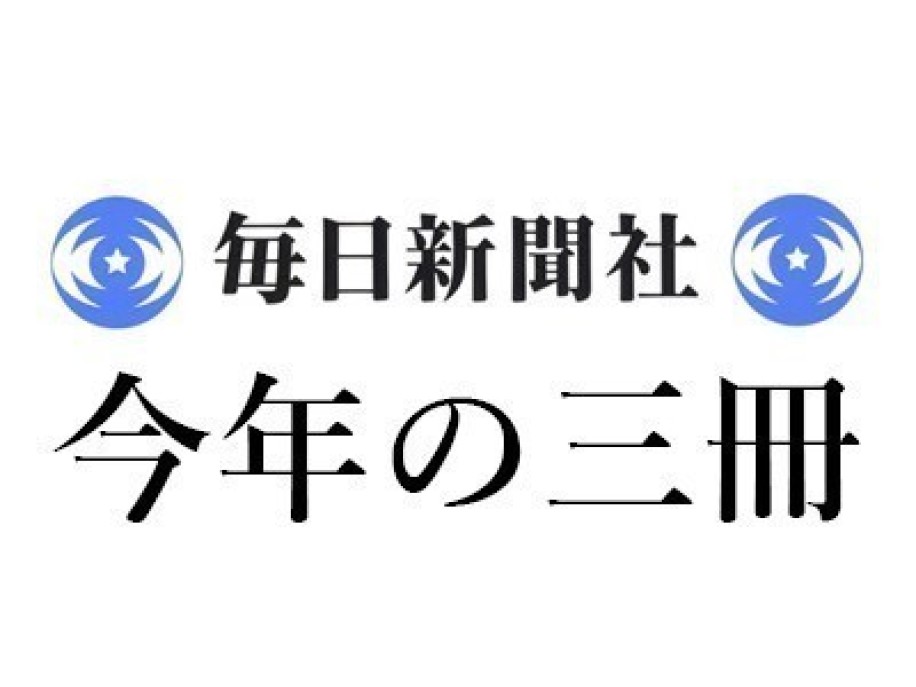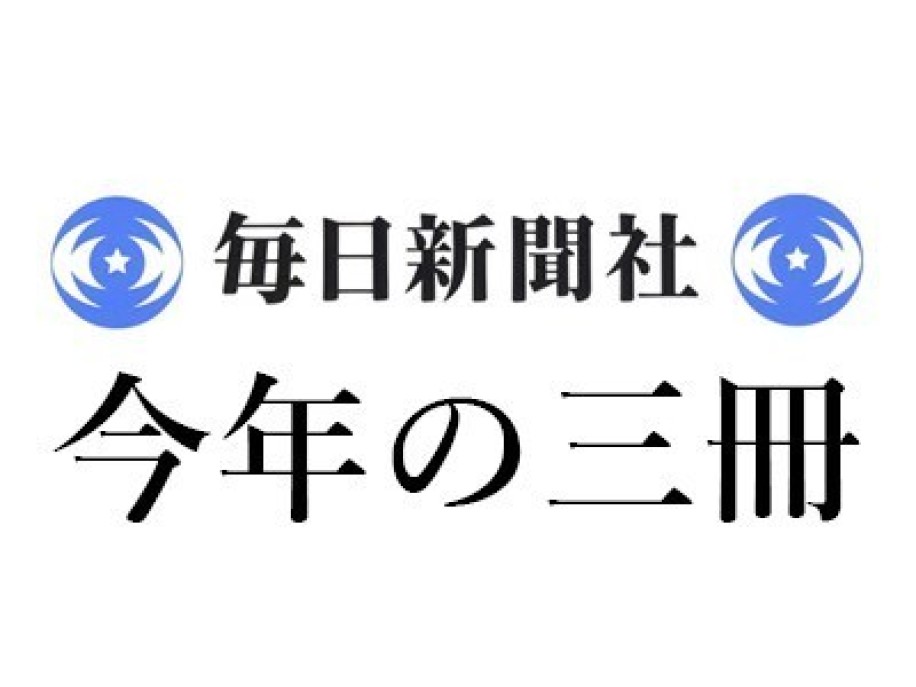書評
『浮橋』(講談社)
かつて小島信夫が『抱擁家族』を書いたとき、この作品が、アメリカ文化の存在を前提にしての〝近代化〟が、日本の家にどんな影響を与えているかの鏡のような効果を、期せずして発揮していたのを覚えている。その際、変化にエネルギーを与えていたのは、輝かしい、進歩した生活への上方志向であったように思われる。それは妻の時子とアメリカ青年との情事、家政婦みちよがもちこんだ、日本の近代文学には珍らしい、悪役としての振舞い等々に象徴されていた。
それから二十七年が経った(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1992年)。岩橋邦枝の『浮橋』はその間に日本がすっかり変ってしまったことを教えている。
夫の急死に会って俄に寡婦になった康子は、放埒とも言える学生時代、週刊誌の取材記者だった頃、そして英語の飜訳者としての生活を通して、彼女の前に現れては消えた男達との交渉を折にふれて想起する。
康子は、行動に現れているよりは、はるかに律義な、どちらかというと古風な性格のようである。それは、作者の計算によって、なるべく抽象的な存在に描かれることになった亡夫との、想像上の対話のなかにもよく現れている。
彼が急死した時、康子は寡婦の役割におさまりきるには若く、かといって新しい恋を作っていくほどには若くなかった。昔の言葉を使えば、充分に残り香を持っていた。これは今日の寡婦の、ひいては大多数の中年主婦の姿なのではないだろうか。
中篇の連作の形をとったこの作品は、「幻火」では女子学生の頃同棲した人気俳優、根岸功との、表題となった四作目の「浮橋」では、中年の劇作家との……といった具合に、主人公のそれぞれの人生の段階に応じて、それらしい男との恋を重ねてゆく。相手の性格や、また年齢が進むに従っての康子の恋心の様態の変化は、まことに巧みに描き分けられていて、快いリズムが伝ってくる。しかし、この作品の魅力は主人公の恋愛遍歴にあるのではない。現在進行形や、半過去、過去といった手法で恋を語りながら、作者の視点はそこに時代の変化を点描させ、それらが次第に
という、我国の美意識に収斂してゆく。読む者はその哀しさに魅き込まれるのだ。
康子のなかには、かつての日本の主婦にあった、より豊かな輝かしい生活、進歩への上方志向はない。一度それに気付くと、時代が消費社会に向って変化しはじめた時、自らを劇中の登場人物に見たててはしゃぎまわって見せた学生の康子は、成長という名の狂騒曲に乗ってステップを踏んでいた社会そのものの象徴のように見えてくる。
母の喪失に続いて父とか夫とか権威の総称としての神が全て失われたかに見える現在、若者達にはまだ恋を作ってゆくエネルギーが残されているのだろうか。この作品を読んで『抱擁家族』が消滅して寡婦のような人々の宴が残ったと思うのは私だけであろうか。
【この書評が収録されている書籍】
それから二十七年が経った(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1992年)。岩橋邦枝の『浮橋』はその間に日本がすっかり変ってしまったことを教えている。
夫の急死に会って俄に寡婦になった康子は、放埒とも言える学生時代、週刊誌の取材記者だった頃、そして英語の飜訳者としての生活を通して、彼女の前に現れては消えた男達との交渉を折にふれて想起する。
康子は、行動に現れているよりは、はるかに律義な、どちらかというと古風な性格のようである。それは、作者の計算によって、なるべく抽象的な存在に描かれることになった亡夫との、想像上の対話のなかにもよく現れている。
彼が急死した時、康子は寡婦の役割におさまりきるには若く、かといって新しい恋を作っていくほどには若くなかった。昔の言葉を使えば、充分に残り香を持っていた。これは今日の寡婦の、ひいては大多数の中年主婦の姿なのではないだろうか。
中篇の連作の形をとったこの作品は、「幻火」では女子学生の頃同棲した人気俳優、根岸功との、表題となった四作目の「浮橋」では、中年の劇作家との……といった具合に、主人公のそれぞれの人生の段階に応じて、それらしい男との恋を重ねてゆく。相手の性格や、また年齢が進むに従っての康子の恋心の様態の変化は、まことに巧みに描き分けられていて、快いリズムが伝ってくる。しかし、この作品の魅力は主人公の恋愛遍歴にあるのではない。現在進行形や、半過去、過去といった手法で恋を語りながら、作者の視点はそこに時代の変化を点描させ、それらが次第に
年月につれて順に過ぎて行く、そこから始まって続いていく暮しがある。
という、我国の美意識に収斂してゆく。読む者はその哀しさに魅き込まれるのだ。
康子のなかには、かつての日本の主婦にあった、より豊かな輝かしい生活、進歩への上方志向はない。一度それに気付くと、時代が消費社会に向って変化しはじめた時、自らを劇中の登場人物に見たててはしゃぎまわって見せた学生の康子は、成長という名の狂騒曲に乗ってステップを踏んでいた社会そのものの象徴のように見えてくる。
母の喪失に続いて父とか夫とか権威の総称としての神が全て失われたかに見える現在、若者達にはまだ恋を作ってゆくエネルギーが残されているのだろうか。この作品を読んで『抱擁家族』が消滅して寡婦のような人々の宴が残ったと思うのは私だけであろうか。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする